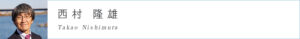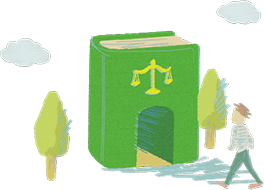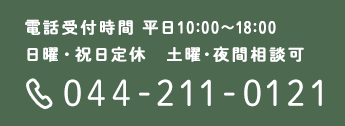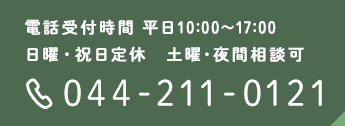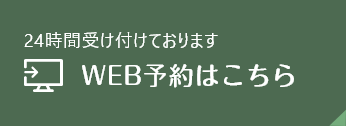ケーススタディー
酒酔い、赤信号無視… 起死回生の逆転劇(弁護士 西村隆雄)
2025年10月21日 火曜日
はじめに
事故が起きたのは、7月下旬深夜1時過ぎでした。川崎区の幹線道路上で、自転車に乗って道路を横断していたNさんに乗用車が衝突。Nさんはその場で救急搬送され、骨盤骨折、左足骨折、左前十字じん帯損傷などの重傷を負って、入院2か月、通院11か月の長期加療を余儀なくされました。
ご相談を受け、早速相手方との交渉を持ったのですが、相手方は、横断歩道上での当方赤信号無視の事故で、酒酔いの上でのものと主張してきました。
当方はお酒が入っていたことは事実ですが、酒気帯び程度で酒酔いには至っておらず、交差点から20m以上離れた地点での衝突とのことで、お互い主張がかけ離れています。
そこで裁判を提起することとなりました。双方とも川崎在住で、事故現場も川崎ですので、当然横浜地方裁判所川崎支部での裁判となるところでしたが、あえて横浜地方裁判所(本庁)に提訴することにしました。その心は、私は弁護士になる前の修習で、本庁第6民事部に配属されました。ここは交通専門部で、交通事故を一手に扱うこととなっており、当時から交通事故に関してはしっかりした審理を行い、また被告側につく保険会社の代理人に対してもはっきりとモノを言っていく傾向があったのを見てきたからです。
案の定、なんで川崎支部ではないのですかと聞かれましたが、事案複雑なのでお願いしたいと話して、受け付けてもらえました。
事故態様
夜間の事故で、第3者の目撃者、ドライブレコーダー映像等の客観的な証拠も存在しない中、双方の主張は大きく対立しました。
交差点の手前20m以上離れた地点を横断していて衝突したとの当方の主張に対して、相手方は、横断歩道上を赤信号で進行してきた当方に衝突したと主張。ここで問題なのは、本来であれば双方立ち会いの下で作成されるはずの実況見分調書が、当方は重傷を負い搬送されてしまったので、相手方立ち会いのみで作られ、その後当方立ち会いでの調書が作られていない点です。相手方はこの実況見分調書に基づいて主張を展開してきました。
さてここで重要なのが、過失割合です。当方(被害者側)にどれだけの過失があったかというのが問題になり、例えば80パーセントの過失ありとなれば、全体の損害が1000万円であったとしても、1000万円×(1-0.8)=200万円しか賠償が認められないのです。これを過失相殺といいます。
ここで本件についてみると、衝突地点が横断歩道上となれば当方の基本過失割合は80パーセントとなるのに対して、交差点外での衝突となれば基本過失割合は30パーセントとなり大きく異なってくるため、ここが最大の争点となってくるのです。
当方の主張
客観証拠が限られている中、現場に残されていた被害者のものとみられる血痕の位置(片側2車線の外側車線の外側)と相手方車両の破損状況(左前部フロントガラスに同心円状のひび割れ破損)を重視すべきと主張しました。
すなわち当方は相手方車両のバンパー等で跳ね飛ばされることなく、相手方車両の前部左側ボンネット上に持ち上げられ、左前部フロントガラスに衝突し、その後落下しそのまま倒れて流血し、外側車線の外側に血痕が残された。この血痕の位置は、中央車線を走行して交差点内で衝突し、その後中央車線上で停止したとの相手方主張とは明らかに矛盾することを強調しました。
一方当方が搬送された病院のカルテに、医師による「赤信号で横断歩道を渡り受傷」などの記載があると、相手方が主張してきました。これに対して、当方は、事故直後は意識レベルが悪く聴き取りは不能であり、一般に搬送されてきた場合、受け入れ医師は救急隊員から事故状況を聞き取るのが普通であり、救急隊員は現場に居合わせた関係者、本件でいえば相手方から事故状況を聞き取っている可能性が大であると主張しました。
裁判所和解案
以上の審理を踏まえて、裁判所は事故態様と過失割合についての所見を示したうえで、和解案を提示しました。概要は以下のとおりです。
「実況見分調書の相手方車両の停止位置と血痕の位置が離れすぎており、この停止位置、ひいては相手方主張の衝突位置が必ずしも正確とは認められない。そもそも相手方は当方自転車に気づかなかったからこそ衝突したのであり、相手方が当時衝突地点を正確に認識できたとは認めがたく、本件事故の衝突地点は、横断歩道の付近であったという程度では採用できるものの、横断歩道上で衝突したとまでは認めがたい。」
上記カルテの記載についても、「当方に事故の記憶がない以上、この記載は相手方の説明に基づくものと認められ、相手方は衝突地点を正確に把握していたとは認められないので、この記載も採用できない」
「以上から本件事故の衝突地点が横断歩道上であったとまでは認めがたく、当方の基本過失割合は30パーセントと認めるのが相当である。」
なお当方の酒酔い運転についても、「酒酔い運転に至らなかった可能性があるとしても、酒気帯び運転の状態であった可能性は否定できず過失修正するのが相当」と提示しました。
相手方はこの所見と和解案を全面的に受け入れて、和解成立に至りました。
健康保険の適用
ところで当方が加入していた健康保険組合は、途中まで、本件は酒酔い運転で、かつ横断歩道上での赤信号横断であるので、健康保険法116条により、健康保険は適用できないとの見解でした。
しかし裁判所の上記所見が出たため、健康保険組合は見解を改め、酒酔い運転、横断歩道上の赤信号横断はいずれも認定できないとして、健康保険適用の判断となりました。
このため非適用であれば約400万円となっていた医療費が、適用となったため自己負担分のみの約120万円に減縮できたばかりでなく、限度額適用認定申請による高額療養費制度を利用できることとなったため、さらに医療費を大幅に縮減できることとなったのは大変に大きかったといえます。
私は弁護士経験40年以上となりますが、交通専門部での修習をきっかけに、多く交通事故案件を扱ってまいりました。今回もその経験が生かされたと思います。どうぞ、交通事故でお悩みの方、ご相談ください。
投稿者 | 記事URL
日本に住むフィリピン人がなくなったとき、相続放棄はできるの?(弁護士 長谷川拓也)
2025年9月9日 火曜日
人がなくなったときには、様々な手続を要しますが、その中でも、意外と大変なのが相続放棄です。
ご家族がなくなったとき、その方に有益な財産があるなら良いですが、借金はもとより、山林原野といった処分の難しい事実上のマイナスの財産については、相続をしないとい
う選択肢がありえます。
このとき、意外と知られていないのは、相続放棄については、家庭裁判所を通じた手続が必要ということです。しかも、この相続放棄の手続については、原則として、相続の開
始を知った時(その多くは、ご家族がなくなったことを知った時でしょう。)から3カ月以内に行う必要があり、この期間を過ぎてしまうと、相続放棄ができなくなる可能性があります。
ところで、ご家族の中には、日本国籍ではない方がいる場合もあるでしょう。そういう方がなくなったときには、相続放棄はできるのでしょうか。
日本国籍以外の方がなくなった場合は、その相続の取り扱いについては、なくなった方の国の法律がどういうルールになっているかが問題となりえます。必ずしも、相続について、日本と同じように定めているとは限りません。
たとえば、フィリピンでは、フィリピン民法16条第2文では、相続に関し、フィリピンの本国法を準拠法とする旨定めていることから、日本で長らく暮らしているフィリピン人がなくなった場合でも、フィリピン法が準拠法となります。
さて、フィリピンでは、日本とは異なり、相続放棄という概念がありません。そもそも、フィリピンには、マイナスの財産を相続するという概念がなく、必然的に、相続放棄自体もないのです。
したがって、以上を前提とすると、原則、日本に住むフィリピン人がなくなったときには、日本で相続放棄が出来ないこととなります。
しかしながら、このような帰結は、ときに様々な問題を生じさせます。たとえば、私がご相談を受けたケースで、フィリピン人の配偶者がなくなったので、その相続放棄につき
依頼したいというものがありました。ご依頼者様のお話をうかがうと、なくなった配偶者様には、日本での借金があり、相続人であるご依頼者様に督促が届いているので、なんと
か相続放棄したいということでした。ご依頼者様は、ご自身で相続放棄手続を進めようとして、裁判所に申立てを行ったそうですが、相続放棄が裁判所を通じた複雑な手続である
こと、ましてや、原則、フィリピン国籍の方について相続放棄ができないということもあり、裁判所で上手く対応してもらえず、困っていました。
さて、このケースでは、もし、相続放棄ができないとすると、ご依頼者様は、借金の宛先であるカード会社など各社に対し、配偶者様がフィリピン国籍であり、相続手続については、日本法ではなく、フィリピン民法の適用があること、そして、フィリピン民法では、負債については、相続の対象ではなく、日本では、原則、相続放棄ができないものの、相続自体はしていないこと、よってしたがって、配偶者様の借金について相続をしておらず、支払義務がないことなどをいちいち説明することとなるでしょう。しかし、カード会
社など各社では、必ずしも、フィリピン民法について理解がある訳ではないでしょうから、場合によっては、こうした説明に納得せず、貸金返還請求訴訟などを起こしてくることもあるでしょう。
そこで、上記のケースにおいては、小難しい話になってしまいますが、国際私法上の公序(通則法42条)により、相続放棄制度を有しないフィリピン法の適用を排除し、日本法により、相続放棄を認めるべきであることを裁判所に説明、説得し、例外的な取り扱い
として、日本法による相続放棄を認めてもらうことができました。
以上のとおり、日本に住むフィリピン人がなくなったとき、相続放棄はできるの?というタイトルの答えは、原則不可、ただし、例外的にできる場合があるということになります。もっとも、この例外的な場合を認めてもらうには、ハードルがありますから、フィリピン人のご家族がなくなった際には、ぜひ、弊所にご相談いただくことをお勧めいたします。
When there are no Filipinos living in Japan, can I give up my inheritance?
Lawyer Takuya Hasegawa
When a person disappears, various procedures are required, but among them,
inheritance abandonment is surprisingly difficult.
When your family disappears, it is good if you have useful property, but you can choose
not to inherit not only debts but also de facto negative assets that are difficult to dispose of,
such as mountains and forests.
At this time, what is surprisingly not known is that inheritance renunciation requires
procedures through the family court. Moreover, as a general rule, this procedure for
renunciation of inheritance is done when you know that the inheritance has started (most of
them are when you know that your family is gone). After this period, you may not be able to
renounce your inheritance.
By the way, there may be people in your family who are not Japan nationals. When such
people are gone, can I give up my inheritance?
If there is no longer a person other than Japan nationality, the law of the country where
the inheritance is no longer available may be a problem. Inheritance is not necessarily the
same as in Japan.
For example, in the Philippines, Article 16, Paragraph 2 of the Philippine Civil Code
stipulates that the home law of the Philippines is the governing law regarding inheritance,
so even if a Filipino who has lived in Japan for a long time disappears, Philippine law will be
the governing law.
Now, in the Philippines, unlike Japan, there is no concept of inheritance renunciation. In
the first place, there is no concept of inheriting negative property in the Philippines, and
inevitably there is no abandonment of inheritance itself.
Therefore, based on the above premise, in principle, when there are no Filipinos living in
Japan, it is not possible to renounce inheritance in Japan.
However, this consequence sometimes leads to various problems. For example, in a
case where I was consulted, there was a case where a Filipino spouse was gone, and he
wanted to request an abandonment of his inheritance. When I listened to the client's story,
he said that the deceased spouse had a debt in Japan and had received a reminder from
the client, who was the heir, so he wanted to give up the inheritance somehow. The client
filed a petition with the court in an attempt to proceed with the inheritance renunciation
procedure on his own, but the court was in trouble because the inheritance renunciation
was a complicated procedure through the court, and in principle, it was not possible to
renounce the inheritance for Filipino nationals.
Now, in this case, if the inheritance cannot be renounced, the client must tell the credit
card company and other companies to whom the debt is addressed, that the spouse is a
Filipino citizen, and that the inheritance procedure is subject to the Philippine Civil Code,
not Japan law, and that the debt is not subject to inheritance, and in principle, in Japan, the
inheritance cannot be waived. You will explain that you have not inherited the inheritance
itself, so you have not inherited your spouse's debts and that you have no obligation to pay.
However, credit card companies and other companies may not necessarily have an
understanding of the Philippine Civil Code, so in some cases, they may not be satisfied
with this explanation and file a lawsuit to claim the return of the loan.
Therefore, in the above case, although it is a bit difficult, we were able to explain and
persuade the court that the application of Philippine law, which does not have an
inheritance renunciation system, should be excluded by public order under private
international law (Article 42 of the General Clauses Act), and that the Japan law should
allow the renunciation of inheritance under Japan law.
As mentioned above, can I renounce my inheritance when there are no Filipinos living in
Japan? The answer to the title is that in principle, it is not possible, but it may be possible in
exceptional cases. However, there are hurdles to be recognized in this exceptional case, so
if you lose a Filipino family member, we recommend that you consult with us.
投稿者 | 記事URL
離婚事件を通して知り合った女性の話(弁護士 三嶋 健)
2025年8月27日 水曜日
三嶋健弁護士については、こちらから。

1 専門は何ですか
専門は何ですかと、よく人から問かれます。多分、交通事故とか、離婚とかという回答を期待されていると思いますが、私は「法律」と答えることにしています。
特殊領域でも、専門知識は勉強すれば得られますし、事件の帰趨を左右するのは、やはり法的センスですので、専門は何かと聞かれれば、法律ということになります。
2 様々な人との出会い
弁護士の仕事をしながら、たくさの人と出会いました。様々な人生があり、そこで培われた人柄に接して感銘をうけました。
今回、皆様に紹介するのは、離婚訴訟で出会い、専業主婦でありながら、子ども連れて離婚するという過酷な経験を乗り越えて、自分の人生を取り戻した女性の姿です。
3 区役所の相談
その人との出会いは、区役所の法律相談でした。可憐な雰囲気で、幸せな家族に恵まれた健気な主婦という印象でしたが、相談の内容は、深刻でした。
夫の言葉による暴力がひどく、子どもにも向かうので、子供らを守りたい。そのためには、二人の子どもを連れて離婚するしかないというのです。
夫は頭が良くて議論しても負けるので、たとえ裁判をしても勝てないかもしれないと不安を訴えました。それを聞いて、その人は、離婚を決意した後も、なお夫の呪縛に囚われていると感じました。
区役所の相談は30分と限られています。手続の概略を説明し、別居し、収入を確保するなどの準備が必要だとアドバイスしたところで制限時間がきてしまいました。
4 電話
相当の時を経て、突然、その人から電話がありました。離婚の準備を終えたので、手続き始めたいと言ってきたのです。
相談が終わるとそのとたんに相談者のことは忘れますが、相談の内容は覚えています。電話の内容から、すぐに、区役所の相談者だとわかりました。
相談時は専業主婦でしたが、今は医療事務の仕事を得て、その収入でアパートを借りて、子どもを連れて別居していました。
別居するときは、トラブルを避けるために、夫の不在中に、置き手紙をして出ることを勧めるのですが、その人は、夫に対し、まず離婚を求め、同意は得られなかったが別居の承諾を得て家を出たと報告しました。
その報告に接して、<怖くても正面から向き合う>というその人の姿勢を感じました。
5 家庭内の出来事の立証
離婚訴訟は、離婚の原因となる出来事は閉ざされた家庭内で起こるので、目撃者はいません。その立証が問題となります。
ただ、相手が巧妙に嘘をついても、依頼者が記憶している事実を詳細に聞き取れば、ほころびが見え、書面や尋問での応酬を通じて相手の主張を崩すことができます。
そのためには、事実を詳細に聞きとる必要があります。しかし、離婚にいたる経緯は依頼者にとって辛く忘れたい記憶であり、その掘り起こしは、苦痛のはずです。しかし、その人は私の質問を通して真摯に過去と向き合い、私と共に、事件の本質を解き明かす努力をしてくれました。
裁判は、夫の抵抗はありましたが、終始有利に進行し、離婚することができました。
6 離婚して
婚姻中、夫の助けを得られず、苦しくてうずくまり泣いている姿を、子どもらが見て、近所に助けを呼ぶということがありました。その人が囚われている婚姻の過酷さを示すエピソードです。しかし、そのような夫婦関係であっても、子ども連れて、夫から自立することは、不安であり決意のいることだったとその人はいいます。ただ、別居後、仕事・家事に疲れて畳の上に横たわるとき、それをとがめる夫の視線がないので、安心して微睡むことができると語り、不毛な婚姻から自立して得た幸せを伝えてくれました。
7 久々の再会
先日、その人と会う機会がありました。小学生だった二人の子どもは大学に進学していました。未だ、正規の職が得られないと悩みを語っていました。非正規であるがゆえに人間関係に気を遣い、いやな目にもあったと言っていました。
それでも、非正規なりにキャリアを積み、収入も伸び、いつかは夫の年収を超えるかもしれないと微笑んでいました。ただ、子どもを現に育てているにもかかわらず、離婚した夫が養育費を支払っているため、扶養控除を受けられない理不尽を指摘し、それを是正したいと言っていました。
深刻な病気にも見舞われましたが、将来を共に歩めそうな人との出会いもあったと報告してくれました。
8 その人の半生をみて
その人の歩みを見ると、専業主婦の離婚の困難、女性の自立の難しさ、能力があっても正当に評価されない非正規労働者への差別を感じます。社会が未だに自立する女性に対して冷淡であることを思い知らされます。
その人は、世間の理不尽を自らの意志で乗り越えてきたのであり、そこに感銘します。そして、その人の自立の第1歩を、弁護士として法的知識で支えることができたことは嬉しかったし、誇りに思いました。
投稿者 | 記事URL
「事実婚のままでは相続できない!?」 ~大切なパートナーに財産を遺すために遺言書を作りましょう~(弁護士 前田ちひろ)
2025年7月31日 木曜日
事実婚のパートナーに財産を遺したい方へ、遺言書が必要な理由をやさしく解説します
最近は、戸籍上の結婚にこだわらない「事実婚」を選ぶカップルも増えています。
生活スタイルは結婚と何ら変わらなくても、法律の上では違いがあり、その違いは相続の場面で大きな問題となります。
この記事では、事実婚の方に向けて、以下のポイントに着目しつつ、遺言書を作っておくことがいかに大切か、解説していきます。
・法定相続人ってだれ?
・法律婚と事実婚のちがい
・パートナーに財産を遺すには?(遺言書の役割)
■ 相続人って決まってるの?~「法定相続人」について
人が亡くなると、その人が持っていた財産(不動産や預貯金など)は、一般的にはそのご家族が相続します。誰が相続をするかについて、法律には定めがあり、ここに定められているのが「法定相続人」です。
法定相続人として、まずは「配偶者」が定められ、その他には、亡くなった方の子ども、親、兄弟姉妹などが順番に定められています。そこで、法律婚をしている場合には、結婚相手は、配偶者として相続人になることができます。
■ 同じ夫婦でも違う?~法律婚と事実婚のちがい
ところが、事実婚の場合には、パートナーは法律上の「配偶者」には含まれていません。そこで、たとえどれだけ長く一緒に暮らしていても、法定相続人となることができないのです。
法律婚(入籍している夫婦)の場合には、たとえば子どもがいる場合でも、配偶者には財産の半分を相続する権利があります。一方、事実婚の場合は、亡くなった方に子どもや兄弟姉妹などの法定相続人がいると、それらの法定相続人が相続をすることになり、パートナーは財産を一切もらえなくなってしまう可能性があります。
では、そのような事態を回避するためには、どうしたら良いのでしょうか。答えは、「パートナーにも相続させる」という意思を、生前にしっかりと残しておくことです。
その方法として、遺言書の作成をおすすめします。
■ パートナーに財産を遺すには?~遺言書の役割
遺言書には、「誰に」「どの財産を」「どのくらい」渡すかについて、自分の意思を書いておくことができます。
特に、事実婚のパートナーのように、法律で相続人とされていない相手に財産を渡したい場合には、遺言書がなければ相続をすることはできませんので、遺言書の作成がとても重要になります。
遺言書には、自分で書く「自筆証書遺言」もありますが、法律に決められた形式を守っていないと無効になってしまうこともあります。確実にパートナーへ財産を遺したいとお考えであれば、弁護士に相談し、法的に問題のない遺言書を作成するのが安心です。
■ まとめ~大切な人のために、準備をしましょう
事実婚は、お互いを尊重した自由な生き方を実現するための一つの方法です。しかし、法律上の保障が不十分な部分があることを理解し、特に相続については、きちんと対策をしておくことが大切です。
「自分がいなくなったあとも、パートナーが安心して生活できるようにしておきたい」
そう思う方は、遺言書の作成を前向きに検討してみてください。
当事務所では、遺言書の作成や相続のご相談を丁寧にサポートしています。初めての方にも分かりやすくご説明いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
投稿者 | 記事URL
無戸籍児の特別養子縁組~解決事例のご紹介~(弁護士 畑福生)
2025年2月13日 木曜日
こんにちは。弁護士の畑福生です。
不幸にも出生届が出されず無戸籍状態となってしまった子どもが、特別養子縁組に至り家庭において幸せに暮らせるようになるという事案を担当させていただきました。
無戸籍児の特別養子縁組の事案の手続きに関してまとまった文献も見られなかったため、同じような状況で悩む方の参考になればと思い、依頼者様の許諾の下、解決事例の報告をいたします。
なお、特定を防ぐために事実関係を一定程度抽象化し変更を施しております。
1 無戸籍状態にいたる経緯及び弁護士につながるまでの経緯
⑴ ある年の1月、某T県でその子(Aさん)は生まれました。Aさんの母 親は夫によるDVから逃れるために夫と別居していましたが、別居期間中に、別の男性との間でAさんを身ごもりました。母親は夫と離婚をし、離婚から4か月後にAさんは生まれました。
母親は、残念ながらAさんを育てられなかったため、特別養子縁組をあっせんするNPO法人にその子を預けることとしました。
NPOの付添いで母親が出生届を提出しようとしたところ、窓口で対応したT県の市役所職員から、離婚後300日以内の出産であるため、戸籍上は元夫との子として扱われ、その子は元夫の戸籍に入らざるを得ないとの説明を受けました。血のつながりもない元夫の戸籍にその子が入ってしまうことは嫌だ、DVから逃れているのに出生が知られると何をされるか分からないと考えたものと思われますが、窓口での説明を受けた母親は出生届の提出をやめてしまいました。その後母親は音信不通となってしまいました。
結果として、Aさんの出生届は提出されず、戸籍が無い状態となってしまいました。
⑵ NPOは、母親が音信不通となる前に某S県に住む特別養子縁組を希望する夫婦(依頼者様)にAさんを預けていました。出生届が出されなかったため、Aさんは無戸籍状態となってしまい、健康保険含む様々なサービスを利用するにも困難が伴いました。依頼者様が困りながらも役所に相談している際に、S県の日本共産党の市会議員さんが依頼者様とつながり、そのご縁で私に相談いただくこととなりました。
役所においては、無戸籍であっても母子手帳の交付や健診の受診等の行政サービスについては提供できるよう対応をしてくれましたが、結局無戸籍状態では今後の生活に支障も多く、畑において依頼をお受けし、特別養子縁組の前提として無戸籍状態の解消を目指すこととなりました。
2 無戸籍状態解消のための取り組み
⑴ 無戸籍状態解消のためには出生届を出すことが考えられます。戸籍法において出生届は父または母、そして同居者や出産に立ち会った医師、助産師等が出生届を提出しなければならないと定められています(戸籍法52条)。
父または母による提出が困難な本件において、幸いにも出産が行われた病院は判明していたため、出産に立ち会った医師に連絡し出生届を提出してもらうよう働きかけることを検討しました。
しかしながら、その場合は上記の市役所窓口の説明どおり母親の元夫の戸籍に入ることとなってしまいます。
本件では、戸籍ができた後に特別養子縁組の手続きが予定されており、その際に母親の元夫の戸籍に入っていると多くの不都合が生じる(どのような不都合があるかについては後記第3項にて紹介しています)ことや、そもそも一切面識のない戸籍上の父の戸籍に入ることの不当性を踏まえ、元夫以外の戸籍に入るようにできないか検討する必要がありました。
⑵ 畑において調査し、各所に問い合わせを行っている中で、まず特別養子縁組が予定されていることから、養子縁組時に養子の新しい戸籍を作る旨の戸籍法20条の3を用いて、特別養子縁組の審判によっていきなり子どもの新戸籍編成をすることができないか法務局に確認しました。
法務局としては養子縁組に伴い新戸籍を編製するとしても出生事項の記載が必要であるため出生届も出されていない本件では形式的にも困難であるし、そもそも同条は一度元親との関係を断絶させて追えなくするためのものだから実質的にも法の趣旨と合致しないため、そのような新戸籍の編製はできないとの回答を得ました。
そのようなやり取りをする中で、法務局より内密出産の場合の通達を踏まえ、子どもの新戸籍を編製することができるかもしれない旨の情報提供を受けました。それが子発0930第1号・令和4年9月30日通達「妊婦がその身元情報を医療機関の一部の者のみに明らかにして出産したときの取扱いについて」です。
熊本市の慈恵病院に赤ちゃんポストが設置され親が育てられない赤ちゃんを匿名でも預かる取り組みが行われた関係で、熊本市においては内密出産の子に職権で戸籍を作るという方針を出しており、そのような取り組みを踏まえ出された通達です。
本件も実の父親はもとより母親も行方がしれない状況となっていたため、この通達を踏まえ新戸籍を編製できないかと考えました。
⑶ 通達どおりの運用ができないか、出生地であるT県の児童相談所及び役所に連絡を行いました。
しかしながら、T県T市においては関係各機関にて協議を行ったところ、本件では、母親が市役所の窓口に少なくとも一度は出生届の提出のために来ていることから病院以外に出産の事実を明かさない内密出産とは異なるとして、通達に記載された取り扱いはなされないこととなりました。
畑からも母親の元夫の戸籍に入ることの不都合を繰り返し丁寧に説明したものの、難しいとの結論に至りました。
⑷ 他方で、T市も無戸籍状態の解決の必要性については重視してくださり、市区町村長の職権による戸籍作成(戸籍法44条3項)を行う方針となりました。
T市は法律上必要な催告(同条1項、2項)を行ったものの、いずれの催告時においても実母は不在の状況であり、二度の催告後、T市は戸籍記載許可申請書を管轄の法務局に提出し、法務局から法律上必要な許可を得て、その年の7月に職権での戸籍記載を完了しました。
⑸ 以上のとおり、時間がかかったものの、無戸籍状態の解決に至りました。
もっとも、出生届が出された場合と異なって、職権での戸籍記載の場合は市において命名権がないことから、「名未定」として名前が空欄のまま戸籍記載がなされるに至りました。
この点についてもどうにか名前(母親がつけた名前があり依頼者様もその名前にしたいとの意向でした)が付いた状態で戸籍を作りたいとのことでT市と繰り返し交渉したものの、法律に基づいて戸籍記載を行う関係で、法律上権限のないことはできないという結果でした。
T市としては実の母が命名について承諾し、そのとおりの命名を行うという実体的な正当性があるとしてもそのための手続が法定されておらず、形式的な正当性がないとのことでした。「名未定」であることについては、戸籍記載完了後、特別養子縁組が認められてから養親において名の追完(戸籍法45条)を行ってほしいとのことでした。
Aさんが母親の元夫の戸籍に入ってしまったことや名前が記載されないことなど不十分な点も多く残ってしまいましたが、無戸籍状態の解消が急務であることから、その後の手続きを進めることとしました。
3 特別養子縁組手続について
⑴ 無戸籍状態を解消できたことから、早速同じ年の8月には、家庭裁判所に特別養子適格の確認申立て及び特別養子縁組申立てを行いました(以下これらをまとめて「特別養子縁組手続」と呼びます)。
依頼者様は当初、Aさんがご自身の子どもになるための手続きであることから、ご自身で特別養子縁組手続きをなさりたいとの意向をお持ちでしたが、無戸籍状態解消に至るまででも一筋縄でいかなかったことや、母親の元夫の戸籍に入ってしまったこと等による難点が予想されたことからご依頼いただくこととなりました。
依頼者様の想いを踏まえ、申立てに際しての提出書類においては、依頼者様がいかにAさんをこれまで愛情豊かに監護してきたか分かるように努めました。
⑵ その後、特別養子縁組手続に関し、申立書を確認した裁判官から連絡を受けました。
裁判官としては、戸籍は母親の元夫の戸籍に入っているが、真実の親子関係がないものであるから、まずはその解消をしなくてはならない、具体的には親子関係不存在確認の手続き(調停及び訴えの手続きをまとめてこのように記載しています)を行わなくてはならないとの見解を示していました。
⑶ まさしく母親の元夫の戸籍に入らざるを得なかった不都合が顔を出すこととなりました。
しかし、親子関係不存在確認の手続きを行うにしても、Aさんはもちろんできず、親権者としての母親も連絡が付かず、かつ事前に元夫に戸籍の記載及び特別養子縁組手続に協力いただきたい旨手紙を出していましたが連絡が付かない状況でしたので、そのような手続きを行うことは困難でした。
裁判官の見解がいかに本件に不適合であって、児童福祉を害するかについて交渉を続けたものの、裁判官の意向は変わりませんでした。裁判官は現状のままでは申立てを却下するとの意向さえ有しているようでした。
⑷ そのため親子関係不存在確認の手続きについての検討を進めました。
ア 手段の一つは、Aさんの未成年後見人選任を申立て、Aさんの代わりに未成年後見人が親子関係不存在確認の手続きを行うというものです。
しかし、この手段でいくとすれば特別養子縁組手続のための親子関係不存在確認の手続きのための未成年後見人選任申立て手続きをしなくてはならず、費用や時間の面からして不相当と考えられました。また、そもそも、法律上、依頼者様において未成年後見人選任の申立てをする権限があるか(利害関係を有するか)についても問題となりました。
ちなみにこの点について、担当の裁判官に、「それでは、親子関係不存在確認の手続きのための未成年後見人選任申立てについて、養親候補者の方の申立適格が認められるのですか?私の調査の限りでは認められませんよ?」と尋ねたところ、担当裁判官は「私はその判断をする部署でないからわからない。」「実際に申立てをしてもらわないと分からない。」との不合理な回答に終始していました。担当裁判官には児童福祉に関する資質が欠けているのではないかと危惧せざるを得ませんでした。
イ もう一つの手段としては、一時保護をした場合に児童相談所長が親権を行える旨の児童福祉法33条の2を踏まえて、児童相談所にAさんを一時保護してもらい、依頼者様のもとで暮らすために依頼者様に一時保護委託をしてもらい、その上で児童相談所長が親権を行使して親子関係不存在確認の手続きを行うというものです。
この方法に関し、管轄の児童相談所に問い合わせを行いました。児童相談所としては当初はAさんの置かれた状況に同情を示してくださったものの、常勤の弁護士が対応することとなり、当該弁護士としては、「そもそもこのケースは児童虐待等で保護しているケースではない。」、「手間も費用もかかる。」、「費用について負担いただけるのか」といった調子で、上記方法については採用いただけませんでした。
私も児童相談所において過重な負担がかかっている状況にあって、余裕がない常態に置かれていることは承知しておりますが、このような対応には閉口してしまいました。
親権者は音信不通で特別養子縁組手続も完了していない宙ぶらりんな状況の中、依頼者様が万が一Aさんを養育することができなくなったら、Aさんはどうなるのでしょうか。裁判所も、あまつさえ児童相談所においてもAさんのことを親身に考えては下さらず、大人の都合や利害にばかり目をやって、一番弱くて不安定な立場の子どもの事を考えてないのではないかと依頼者様も絶望を露わにされていました。
⑷ このような状況で裁判官の求める親子関係不存在確認の手続きはやはり相当でなく、裁判官の見解自体を変えなくてはならないと思い至りました。
そのため、本件のような戸籍上の親と実の親が異なる場合の特別養子縁組手続に関する審判例の調査を進めておりました。もっとも、原則非公開の手続ですから判例集での調査は困難を極めました。
そこで、依頼者様を通じて特別養子縁組をあっせんするNPOに同様の事例がないか確認いただきました。すると、NPOは同様の事例をご存知であり、当該事案の養親の許諾の下、審判例を提供いただくことができました。当該事案においては、親子関係不存在確認の手続きを求めず、家裁から戸籍上の父親に照会を掛け、戸籍上の父も特別養子縁組手続に同意していたことを踏まえて特別養子縁組を認めるに至っていました。
同じ年の11月、私の方から当該事案の養親の方に連絡し、本件において当該審判の家裁への提出許可を得て、家裁に対し当該事案同様に戸籍上の父(母親の元夫)に連絡をし、同意を得る手続きを踏めば特別養子縁組が可能であることの説明を行いました。
すると、家裁も審判例の存在に安心したのか、この方法で手続き進めてくれることとなりました。当該審判例は一筋の光明となりました。
⑸ その後早速家庭裁判所は母親の元夫に連絡を取ろうとしましたが、ここでまた障壁が生じました。
申立前に私が母親の元夫に手紙を出した際には手紙が確かに届いていたのですが、11月の段階で家裁の調査官が元夫に手紙を出したところ「宛所に尋ねあたらず」として手紙が戻ってきてしまったというのです。
ここで改めて母親の元夫の居場所を調べる必要が出ました。もともと元夫と連絡を取るために様々調査はしていたのですが、これといった手がかりもつかめず、またT市は遠方のため出向いて探すというのも現実的ではありませんでした。
検討を重ねているうちに、ふとAさんが記載された母親の元夫の戸籍の附票を確認すると、元夫の住所地と元夫とAさん母親との間の別の子(異父きょうだい)の住所地が異なることに気づきました。その住所地の不動産登記を調べると、元夫と同じ名字の方の所有地であって、Googleマップのストリートビューで確認したところ民家が建っていることが確認できました。
もしやその方は元夫の親類であって、その方が異父きょうだいを元夫の代わりに養育しているのではないかと考え、早速その方宛に手紙を発出しました。すると、その方は元夫の父であって、しかも元夫が現在は当該住所地に住んでいるとの回答が得られました。お電話でお話したところ、手続についても協力的であって、元夫が手続きに協力するようサポートして下さるとのことでした。
このことを家裁に伝え、家裁から当該住所地宛に手紙を出してもらったところ、元夫と連絡が取れ、速やかに手続きに協力いただけたとのことでした。
以上の次第でAさんが生まれた翌年の2月にようやく特別養子縁組が認められました。
4 おわりに
ご相談をいただいてから1年程度かかりましたが、なんとか無戸籍状態の解消及び特別養子縁組に至ることができました。
本件においては、やり取りを行うべき関係各所も多く、弁護士だからこそ取得できた情報が解決には必要であり、かつ様々な法的知見を踏まえて方法を探っていくアプローチが有用でした。
もちろん依頼者様の真摯な努力あってこその解決ではありますが、依頼者様ご本人のみでは行き詰まる点も多かったでしょうから、手前味噌ながらご依頼いただけてよかったものと思っています。
あくまで一例ではありますが、同じような状況に置かれた方の参考になりましたら幸いです。
長くなりましたが、最後に依頼者様からいただいた感謝のメッセージを紹介してこの記事を締めたいと思います。
無戸籍から始まって、裁判を却下されそうになったりと、進む先々で障壁が立ち塞がり、一時は八方塞がりかとも思いましたが、ここまで辿り着けたのも畑さんのおかげです。
親身になって手を尽くして助けていただき本当にありがとうございました!!
特別養子縁組が認められた報せを見た時には涙が出て、子どもを抱きしめて喜びました!
入籍手続きが完了して住民票が発行され、続柄の欄に「 子 」と書かれているのを確認した時は、思わず涙がこぼれてしまいました。
これもひとえに畑さんがあらゆる可能性を模索してくれ、都度立ちはだかる障壁をクリアしてくださったおかげです。
子どもが成長した時には、「畑さんが情熱を持って解決まで導いてくれたんだよ」と伝えていきたいです。
文字で書くと陳腐な言葉になってしまいますが、感謝の気持ちでいっぱいです。
ありがとうございました!!
投稿者 | 記事URL
孤立出産による乳児死体遺棄・殺人事件で執行猶予判決を獲得!(弁護士 長谷川 拓也)
2024年9月30日 月曜日
1 はじめに
昨今、全国各地で乳児死体遺棄事件は後を絶たず、弊所弁護士においても、乳児死体遺棄事件の弁護人を務めた経験が複数あります。
とくに2022年、神奈川県では、乳児死体遺棄事件が4件も発生しました(うち、1件は、弊所長谷川弁護士が担当、もう1件は、弊所川岸弁護士及び長谷川弁護士が担当しました。)。
今回は、2022年、神奈川県で発生した乳児死体遺棄・殺人事件において、異例の執行猶予判決を獲得し、各種報道でも取り上げていただきましたので、そのご報告をさせていただきます。少しでも、この記事が孤立出産に関係する事件で悩んでいらっしゃる方の助けになることを望んでいます。
2 事件内容等
事件は、2022年4月、神奈川県川崎市にあるマンションで発生しました。マンションのごみ捨て場に出生したばかりの乳児が遺棄してあることが発覚、その後、乳児を出産したという成人したばかりの若い女性(以下「Aさん」と言います。)が死体遺棄の被疑事実で逮捕となりました。
Aさんは、一人で自宅の浴槽で乳児を水中出産したものの、出産後、気を失ってしまったことから、Aさんが意識を取り戻したとき、乳児は、出生後、水中に沈んだ状態のままになっており、すでに亡くなっていたのです。
しかしながら、捜査機関は、もともと、Aさんが乳児を殺害するつもりで、実際に乳児を水中に沈めて殺害したとして、殺人の被疑事実で逮捕しました。そして、その後、Aさんに対し、乳児に対する死体遺棄と殺人の被疑事実で起訴、市民の皆様も裁判員として参加する、裁判員裁判になりました。
3 孤立出産の問題
さて、この事件は、どうして起きてしまったのでしょうか。もっと言えば、どうして、Aさんは、たった一人、自宅で出産することとなったのでしょうか。
妊娠した女性が病院等における検診を受けず、未受診のまま、したがって、医療機関が介入しないまま、一人出産することを「孤立出産」と呼んでいます。まさに、今回のケースも、この孤立出産にあたるものと言えますが、この孤立出産の背景には、次のようなものがあります。
つまり、妊娠した女性が幼少期に家族から虐待を受けたことがあるなどして、家族、とくに妊娠や出産について、先輩であり、一番の模範となるべきである母親との関係が良くないこと、女性に発達、知的な障害があることなどです。
こうした特徴を抱えた女性においては、妊娠や出産に直面した際、周囲の人に対して、そのことを相談することができず、一人で抱えこんでしまい、かといって、自身で解決することもできずに、現実逃避してしまう結果、行き辺りばったりの出産を迎えてしまうことが多く、孤立出産に繋がるという訳です。
そして、残念なことに、結果的に、こうした孤立出産が乳児死体遺棄や殺人事件に繋がってしまうことも少なくありません。
一般的には、「周りへの相談くらい、普通はできるでしょう。」という感覚があり、こうした女性に対する理解は難しいと思いますが、乳児死体遺棄事件で逮捕勾留となった女性と対面した際、実際に、こうした特徴を持っている女性は多いのです。
4 Aさんの抱えていた問題
こうした孤立出産に繋がってしまう女性の特徴については、今回のケースのAさんにもよく当てはまるものでした。
Aさんは、幼少期から、シングルマザーの母親の元で育ちましたが、母親は、昼夜、働いており、Aさんの面倒を見ることはできず、Aさんの面倒は、母親の友達が交代で見ている状態でした。もっとも、面倒を見ているとは言っても、Aさんに対する教育などは一切なく、Aさんは、日本語の勉強などは、テレビを見て、自然に覚えるという状態でした。そのうえ、母親は、Aさんの出生届について、Aさんが小学5年生になるまで出せておらず、結果、Aさんは、そのころまで、法律上はしない子でした。当然、Aさんは、幼稚園(保育園)には通えておらず、小学校についても、小学5年生から通いはじめるという、極めて特殊な生い立ちでした。
まして、Aさんの母親は、シングルマザーの重責から、精神的に不安定な時期があり、Aさんに対し、ひどい言葉を浴びせることも多く、ときには、叩いたりすることもありました。また、母親は、外国籍であり、日本語の理解が乏しかったことから、Aさんとのコミュニケーションも少なく、ほとんどネグレクトの状態でもありました。
こうした生い立ちのAさんにおいては、知的な課題もありました。裁判前、Aさんの知能指数を診断したところ、Aさんは、ほとんど軽度知的障害にあたる境界知能の状態であったことが分かったのです。
この境界知能というのは、数値上、軽度知的障害ではないものの、知能指数的には、その状態に近いというものであり、臨床的には、軽度知的障害として処理することもあるものです。境界知能は、軽度知的障害とは異なり、見た目には、あまり分からず、周囲からは、「内向的」などと、性格の問題として、問題を理解してもらえないことも多く、社会生活において、孤立出産のように、大きな事態になってからはじめて明らかになることも少なくありません。
Aさんにおいては、こうした生い立ちや境界知能の特性として、妊娠出産を母親含め、周囲の人に相談することができず、乳児の父親(以下「お父さん」)などに気付いて、何とかして欲しいという受け身の状態でいることが精一杯な状態でした。しかしながら、実際には、Aさんは、誰からも、妊娠の事実に気付いてもらうことができず、結果、行き辺りばったりで、自宅にて孤立出産をしてしまい、結果として、乳児が亡くなってしまったのです。
5 裁判の焦点
さて、今回のケースでは、Aさんが乳児を水中出産したこと、亡くなった乳児を遺棄したことに争いはなく、裁判では、Aさんが乳児に対し、殺意をもって水中に沈めたのかどうかという点に争いがありました。
裁判では、この焦点を判断するべく、弁護側からは、赤ちゃんポストや裁判への専門家証人としての出廷などのご活動により、孤立出産の問題に精力的に取り組んでいらっしゃる、熊本県の慈恵病院の蓮田健医師や同県の人吉こころのクリニックの興野康也医師に出廷、証言をいただき、医学的な観点から、Aさんの行動を裏付けていただきました。
また、今回のケースでは、Aさんの抱えている問題に即して、今後、孤立出産など、悩みを一人で抱え込まず、同じようなことが起きないようにすべく、罪を犯してしまった方への更生支援などを行っている、社会福祉法人UCHIの川瀬悦副理事長にもお越しいただき、Aさんに対する社会復帰後の更生計画を示していただきました。
更には、Aさんの母親や、当時Aさんの交際相手(乳児のお父さん)にも出廷、証言いただき、、Aさんの生い立ちや、今後は、上記更生支援計画に沿ってAさんの更生を支えていくことなどをお話いただきました。
裁判では、裁判員の方々や傍聴の方々などがすすり泣く姿もあり、まさに、孤立出産の問題について、少しでも、ご理解いただけたものと思っています。
6 裁判の結果
こうしたご家族、専門家のご協力の下、2024年7月18日、Aさんに対する判決がありました。
結果としては、冒頭のとおり、執行猶予判決であり、死体遺棄、殺人の事件では、異例のことであったため、各種ニュースや新聞でも、大きく取り上げていただきました。
残念ながら、判決では、死体遺棄だけではなく、殺人の点についても認めるものでしたが、一方で、殺人を認めたうえで、執行猶予判決という異例の判断になったのは、まさに、孤立出産の問題をきちんと理解していただいたことによるものです。その点では、全国各地、社会で起きている乳児死体遺棄事件に対し、今後、大きな影響を及ぼす重要な判断であったと確信しています。
7 社会を変えていくためには
本件で、Aさんが孤立出産に追い込まれた背景には、日本で出生した外国籍の子どもやシングルマザーの問題、境界知能に対する社会的認知や支援の問題、そして孤立出産に追い込まれる女性の問題など、多くの重要な社会問題が重なった結果、不幸な事件が起きてしまいました。逆に言えば、このような問題が社会に十分に認知され、これに対する社会的支援が広がっていれば、本件のような最悪の結果は、どこかで回避することができたといえます。
そのような想いで、本件をただの事件として終わらせず、社会に伝えたいと、熱心に取材・報道してくれた記者の方々もいて、私たち弁護団もその想いに応えるべく、弁護活動を尽くしてきました。
刑事事件で被告人とされた個人を罰するだけでは、事件の再発を防ぐ社会を作るには不十分です。事件を事件で終わらせず、背景・原因を理解し、多くの方と協力して事件のを再発を防ぐ社会をいかに作っていくかが問われています。
投稿者 | 記事URL
追突事故の後遺障害につき、後遺障害等級12級該当として解決した事例(弁護士 小林展大)
2023年10月3日 火曜日
小林展大弁護士については、下記をご覧下さい。
1 受任に至る経緯
依頼者は、自動車を運転して一時停止している時に、後方から追突される交通事故(以下「本件事故」といいます。)に遭いました。依頼者は、すぐに病院に行って診察、治療を受け、その後も継続して通院し、治療を受けていました。そのような経過の中、依頼者から相談を受け、受任することとなりました。
2 受任後から後遺障害等級の認定の申請までの動き
依頼者に交通事故証明を取得してもらうと、人身事故になっていましたので、警察署及び検察庁に問い合わせをして、刑事記録の一部を謄写しました。また、依頼者の傷害は、いわゆるむち打ち症でしたので、被害者請求により後遺障害等級の認定の申請を行うこととし、後遺障害診断書等の必要書類を取得しました。
必要書類の準備ができたところで、後遺障害等級の認定の申請をしました。
3 異議申し立て
しかし、結果は後遺障害等級非該当でした。
そこで、依頼者と協議し、この結果に対して、異議申し立てをすることとしました。依頼者には通院していた医療機関からカルテ開示をしてもらい、協力してもらえる医師(以下「協力医」といいます。)を探しました。
そして、協力医が見つかり、後遺障害診断書、意見書等の書類を作成してもらいました。このような追加資料を準備した上で、異議申し立てを行いました。
その結果、依頼者は後遺障害等級14級に認定されました。
4 さらなる異議申し立て
しかしながら、従前から依頼者のカルテ一式等の資料を検討していると、依頼者については後遺障害等級12級に該当する可能性があるのではないかと考えられました。
そこで、さらに追加の医証を準備した上で、さらに異議申し立てをしました。
しかし、その結果は、前回の異議申し立てにより認定された後遺障害等級14級のままでした。
5 訴訟提起
ここで、2回の異議申し立ての結果に記載された理由、依頼者に取得していただいた診療記録一式、謄写した刑事記録、協力医から今後得られそうな協力等を踏まえて、依頼者とその後の方針について協議しました。
訴訟であれば、被害者請求により認定された後遺障害等級に拘束されるわけではないものの、一般的にむち打ち症で後遺障害等級12級に認定されることは少ないこと等も踏まえて、依頼者と協議した結果、訴訟提起することとしました。
訴訟では、後遺障害等級については、証拠として提出した診療記録一式、CT・MRI等の画像資料、医師意見書、後遺障害診断書等をもとに立証していきました。加えて、医療過誤事件と同様に医学文献の収集につとめ、医学文献も証拠として提出していきました。
また、損害については、逸失利益につき、いくつか対応が必要な問題点があったことから、その都度、依頼者に証拠資料の有無を確認し、援用できそうな証拠資料の準備をお願いして、立証につとめました。
そして、裁判所の考えが開示され、後遺障害等級については12級該当を認めてもらうことができました。その後は、裁判所の考えをもとに、少し交渉をした上で、解決に至ることができました。
6 最後に
本件は、むち打ち症につき、当初は後遺障害等級非該当との判断がされたものの、異議申し立てにより後遺障害等級14級該当が認められ、訴訟では後遺障害等級12級該当が認められて解決に至ったものです。
診療記録に、依頼者の主張を裏付ける記載があっただけでなく、協力医の適切なサポートがあったこと、依頼者が迅速に証拠資料の収集、確保につとめたことも良い結果につながった要因ではないかと考えられます。
以上
投稿者 | 記事URL
性暴力が性暴力と認められた─Aさんの5年間のたたかい─(弁護士 川口彩子)
2022年8月31日 水曜日
2014年6月、Aさんは多摩区の有限会社ローカストに事務員として入社しました。ローカストは映画やCMの操演や特殊撮影などを行う会社です。入社してすぐの 8 月後半、Aさんは会社の飲み会で会社役員でもある社長の息子から強い酒をたくさん飲まされて意識を失い、そのまま社長の息子から性暴力を受けました。内容が内容だったため、Aさんは誰にも相談することができず、当時は警察に行くということも思い至りませんでした。2015年になると社長の息子はAさんを「夜の世話もしてくれる忠実な部下」として周りに見せびらかすかのように、Aさんを深夜までスナックに付き合わせ、そのまま自宅に連れて帰り、自分本位な性暴力を繰り返しました。もともと身体の弱かったAさんは、連日に及ぶ深夜までの飲酒と寝不足、不衛生な性行為で体調を崩し、意識が朦朧としたまま襲われる日々でした。避妊なしの性行為により、3 度の流産も経験しました。そして、2017 年 2 月、Aさんは社長の息子から深夜に無理矢理呼び出された際、「持病を持ってない人でも、毎晩連れ回されてたら病気になりますよ」と初めて口ごたえをしました。すると社長の息子はその晩Aさんに対し、Aさんの首が絞まるように暴行を加え、「とりあえず辞表書こっか」「誰にも分からないように荷物なくしてくれよ。そんで誰にも分からないように死んでくれる?」などと言って、解雇を通告したのです。社長の息子はAさんに「ほかにセックスできる女ができたから」とも言いました。
2017年10月、Aさんは解雇無効と未払賃金の支払い、会社と社長の息子に対し慰謝料を請求する裁判を起こし、2021 年6月、横浜地裁川崎支部の判決が出されました。しかし、この判決は、Aさんと社長の息子は交際していたのだから性行為についても同意があったと認定し、社長の息子と会社を免罪したのです。Aさんはすぐさま控訴
し、2022年2月、画期的な東京高裁判決が言い渡されました。
東京高裁は、Aさんが立場上社長の息子に反抗できない心理状態にあったことを正面から認め、Aさんは受け入れていたわけではなく、性暴力を受け続けてきたのだということをきちんと認めてくれました。そして、解雇も無効であると判断し、Aさんに、慰謝料と未払賃金を支払うよう命じたのです。
性暴力の被害者は、その内容がセンシティブかつ深刻なものであるため、被害を訴えることは困難な状態にあります。これまでどれだけの性被害者が、自分にも落ち度があったのではないかと考え、泣き寝入りしてきたことでしょう。控訴審では、「上司と部下」「教師と生徒」といった地位・関係性を利用した性暴力の構造や、被害者のおかれている心理状態、そして、合意がなければそれは性暴力なのだということをあつく主張しました。それが今回の判決につながり、安堵しています。被告側は上告し、現在は最高裁の決定を待っているところです。
投稿者 | 記事URL
相談者にとって今本当に必要なことは何か(弁護士 藤田温久)
2021年8月6日 金曜日
Aさん(65歳)は夫Bさん(68歳)とお二人で戸建の建物にお住まいでした。戸建の土地、建物(以下「本件土地建物」)はいずれもBさんの名義でした。Bさんはご自宅で病気療養中のことで、Aさんがお一人でご相談にみえられました。
ご相談は、Aさんご夫婦のお隣にお住まいのBさんの弟Cさんと同人所有のお隣の土地との境界を巡る争いが続いており、Bさんのお元気なうちに境界問題を解決したいので、境界確定のためにはどうすれば良いのかというご相談でした。
私は、先ず、境界を確定するためには、当事者同士の話し合いがつかないのであれば、弁護士を代理人として交渉しそれでもだめな場合は境界確定訴訟(裁判をするということです)などの法的手続をとることで境界を画定することができること等をお話ししました。
しかし、私はBさんが病気療養中で相談にもみえられなかったことが気になり、病状について遠回しに伺ったところ、Aさんは「実は・・」とBさんが癌で余命2~3ヵ月と医師から言われていることを打ち明けて下さいました。私が心配していた以上の病状であったため、Bさんの家族関係をお聞きしたところ、ご両親は亡くなられており、お子さんはいらっしゃらず、Aさんの外はCさんのみが法定相続人(法律で決められている相続人)であること、相続財産は本件土地建物と若干の預金のみであることが分かりました。
そこで、私は、「気を悪くしないで聞いていただきたいのですが、もしご主人(Bさん)が亡くなられた場合、相続財産は貴女(Aさん)とCさんで相続することになってしまいます。しかし、「貴女に全部相続させる」旨の遺言を書いていただければ、ご兄弟には遺留分減殺請求権(遺言があっても、法定の割合を自分に渡すように要求することができる権利)もないので、貴女が単独で相続することができます。「どのように考えられますか。」と聞きました。すると、是非遺言を書いてもらいたいというご希望でした。私は、弟Cさんと境界争いをしている現状からすると、Bさんが亡くなられた後にCさんから「遺言はAさんがBさんに無理に書かせたものだ」「遺言は偽造された(勝手にAさんが書いた)ものだ」等といわれる可能性があるので公正証書遺言にした方がいいとお勧めしました。公正証書遺言は、公証人が作成するものであり、「偽造」「無理に書かせた」等というクレームを付けて遺言が無効だと争うことは非常に困難なものであることを説明させていただきました。もちろん、証人には当職と当事務所の事務局員1名を充てること、費用等についても説明させていただきました。その結果、AさんはBさんに公正証書遺言を書いてもらうことでその内容、手続を当職に依頼されることになりました。
当職は、一刻を争うと考え、その場で公証人に電話し、公証人がBさんの病室にゆくことのできる日程を確保し、遺言原案を作成し、公証人と打合せをした後、数日後無事公正証書遺言を作成することができました。その1ヵ月後、Bさんは様態が急変し亡くなられてしまいました。
私は、Aさんから依頼を受け、遺言執行(本件土地建物の相続登記や預金の名義変更等を行う)をAさんの代理人として行いました。更に、Aさんから依頼を受け、Bさんと交渉し境界を確定することにも成功しました。
Aさんには、「相談していなければどうなったか・・本当に有り難うございました」と大変感謝していただきました。
法律の専門家ではない方には、今本当に必要なことは何かが分からないことが往々にしてあります。私は、これまでの30数年の弁護士生活と同じく、常に相談者にとって「今本当に必要なことは何か」をこれからの真剣に考えていきたいと思っています。
以上
投稿者 | 記事URL
雇止め(更新拒絶)されても、働きつづけることができる場合もあります!(弁護士 山口毅大)
2018年8月31日 金曜日
1 相談に至る経緯
相談者は,20年以上,勤務していた職場で,飲食業務等に従事し,何十回も有期雇用契約を更新されてきた方でした。
次回の更新の段階になって,相談者は,会社から突然,次回の契約を更新しないと告げられました。
会社が挙げてきた理由は,いずれも事実無根であったり,問題が無いことばかりであったので,相談者は,会社に対し更新するように求めました。
すると,会社は,雇止めを撤回すると言ってきましたが,相談者に対し,代わりに,一定の不明確な条件で更新しない旨の不更新条項が記載されている書面にサインするように言いました。
そこで,相談者は,数名の弁護士に相談しました。ですが,受任を断られてしまい,労働問題を労働者側で行っている当職に相談を申し込みました。
2 本件の主な争点
本件の争点は,
① 雇用継続への合理的期待が生じているか,
② 雇止めに客観的合理的理由があるか,社会通念上相当であるかどうか
という点にありました。
3 相談後の経緯
相談者のお話を伺うと,20年以上,同じ就労場所で,同じ業務を行ってきたことから業務内容が臨時ではないこと,雇用期間が長いこと,更新回数が多いこと,一度雇止めを撤回したこと,雇用の目的からして必要以上に短い期間を定めていることから雇用継続への合理的期待が生じていると考えられました。
このように,雇用継続への合理的期待が生じている場合に,労働者が契約更新を求めていれば,客観的合理的理由を欠き,社会通念上相当ではなければ,雇止めできず,従前の契約内容で更新されます。
次に,会社が挙げた雇止めの理由について,いずれも,客観的合理的理由を欠き,社会通念上相当ではないことは明らかでした。
なお,確認書については,サインする義務もない上,抽象的な条件での不更新条項が入っていましたので,サインしないように助言しました。これにサインすると,後で,条件が成就したことにより不更新とすると言われかねないからです。
そこで,まずは,当職は,会社に対し,内容証明郵便を送付し,相談者に対する雇止めが労働契約法19条2号に反し,許されないことから雇止めの撤回,確認書のサインの強制をせずに,更新することを求めました。
その結果,会社は,雇止めを諦め,従前通りの条件で契約を更新しました。
4 さいごに
契約期間が満了したことをもって,契約終了と会社から言われると,その通りであると思ってしまう方も多いかと思います。ですが,今回のように,雇用継続への合理的期待が生じている場合で,雇止めが客観的合理的理由を欠き,社会通念上相当ではない場合には,従前の契約内容で更新されます。また,実質的に無期契約と同視できる場合にも,雇止めが客観的合理的理由を欠き,社会通念上相当ではない場合には,従前の契約内容で更新されます。
今回のように,交渉のみで,復職できるケースは,あまり多くはありません。ですが,更新しないことを通知された場合に,すぐに相談頂ければ,今回のように雇止めを撤回させることができる場合もあります。また,訴訟で争うことも可能です。
諦めずに,まずは,ご相談ください。
投稿者 | 記事URL
最近のブログ記事
- 酒酔い、赤信号無視… 起死回生の逆転劇(弁護士 西村隆雄)
- 日本に住むフィリピン人がなくなったとき、相続放棄はできるの?(弁護士 長谷川拓也)
- 離婚事件を通して知り合った女性の話(弁護士 三嶋 健)
- 「事実婚のままでは相続できない!?」 ~大切なパートナーに財産を遺すために遺言書を作りましょう~(弁護士 前田ちひろ)
- 無戸籍児の特別養子縁組~解決事例のご紹介~(弁護士 畑福生)
- 孤立出産による乳児死体遺棄・殺人事件で執行猶予判決を獲得!(弁護士 長谷川 拓也)
- 追突事故の後遺障害につき、後遺障害等級12級該当として解決した事例(弁護士 小林展大)
- 性暴力が性暴力と認められた─Aさんの5年間のたたかい─(弁護士 川口彩子)
- 相談者にとって今本当に必要なことは何か(弁護士 藤田温久)
- 雇止め(更新拒絶)されても、働きつづけることができる場合もあります!(弁護士 山口毅大)