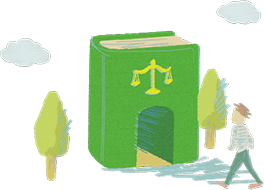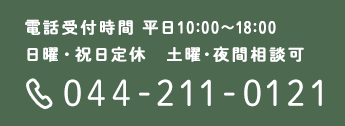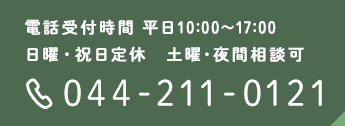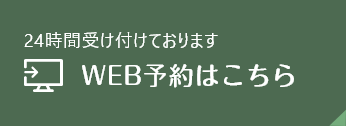Q&A
Q 離婚に際して相手に慰謝料を請求したいのですが、どのくらい請求できるのでしょうか。
2019年4月5日 金曜日
A
慰謝料は、不貞(浮気)、暴行、虐待、侮辱など、相手方から受けた不法行為による精神的苦痛に対して支払われる損害賠償です。通常は離婚前に、協議、調停、裁判の場で慰謝料の話し合いをします。請求できる慰謝料の金額、いわゆる相場についてはケースバイケースです。不法行為の程度、婚姻期間等が考慮要素になりますが、相手方に支払能力があるのかないのかが、一番大きなポイントです。なお、慰謝料請求権には時効があり、離婚が成立した時から3年経つと請求ができなくなりますので(民法724条)注意しましょう。
投稿者 | 記事URL
Q 夫(妻)との離婚を希望しており別居しているのですが、相手が生活費を渡してくれません。どうしたらよいのでしょうか。
2019年4月4日 木曜日
A
夫婦は、その財産、収入、その他いっさいの事情を考慮して、生活費を分担する義務を負います(民法752条)。これを婚姻費用といいます。婚姻費用は、通常、収入が多い方が少ない方の負担をすることになります。その際、金額の目安となるのが、婚姻費用の算定表です。当事者間で協議しても相手が生活費を渡してくれないままのときは、家庭裁判所に、婚姻費用の分担を求める調停を申し立てましょう。相手方が調停で調停委員会の解決案に応じない場合は、調停は不成立となりますが、自動的に審判に移行して、家庭裁判所が当事者双方の収入を見て、審判によって婚姻費用を決定することになります。離婚調停の申立てと同時に婚姻費用分担の調停を申し立て、離婚が成立するまで婚姻費用を受け取りながら離婚手続を進めることもよくあります。
投稿者 | 記事URL
Q 調停では相手方が離婚に応じてくれず調停不成立となりました。その後の手続はどうしたら良いのでしょうか。
2019年4月3日 水曜日
A
裁判に移行して離婚の判決を得るしかありません。相手方が離婚を拒否しているにもかかわらず、判決で強制的に離婚を成立させるものであるため、お二人の間に法律の定める離婚原因があることが必要です。民法770条1項は離婚原因として、
【1】不貞行為(浮気)、
【2】悪意の遺棄(勝手に出ていく等)、
【3】(相手方の)3年以上の生死不明、
【4】(相手方の)回復の見込みのない強度の精神病、
【5】その他婚姻を継続し難い重大な事由を規定しています。
あなたの考える離婚原因が、法律上の離婚原因に該当するかどうかは、別居期間等も考慮した具体的事情によって判断することになります。あなたのご事情を弁護士にご相談ください。
投稿者 | 記事URL
Q 夫(妻)と、離婚したいのですが、相手が離婚に応じてくれません。その後の手続はどうしたら良いのでしょうか。
2019年4月2日 火曜日
A
相手方の住所地にある家庭裁判所が管轄の裁判所となりますので、そこに調停の申立書を提出して離婚調停を申し立てることになります。調停を経ずにいきなり裁判を提起することはできません(調停前置主義、家事審判法10条)。調停は裁判とは異なり、非公開の場で、家事審判官(裁判官)1名と、調停委員2名で構成される調停委員会が、1か月に1回程度行われる調停期日の中で、当事者双方に事情を尋ねたり意見を聴いたりして、双方が納得のうえで問題を解決できるように解決案を提示します。相手方が調停期日に出席しない場合や、当事者の双方あるいは一方が調停委員会の解決案に同意できない場合は、調停は成立しません。
投稿者 | 記事URL
Q 夫(妻)と、離婚することに合意しました。その後の手続は、どうしたら良いのでしょうか。
2019年4月1日 月曜日
A
まずはお近くの市区町村役場で離婚届用紙をもらってきてください。そこに住所本籍等の必要事項を書き込み、当事者双方が署名捺印したうえ、2人の成人に証人として署名捺印してもらいます。未成年の子がいる場合は、協議で親権者を決める必要があり(民法819条)、親権者を決めない限りは離婚できません。そうして完成した離婚届を市区町村長に届け出ることにより、協議離婚が成立します(民法765条)。協議離婚に際して、慰謝料、財産分与、養育費等の金銭的条件を決定する場合には、公正証書を作成することをお勧めします。
投稿者 | 記事URL
Q 最低どのくらいお金がかかりますか?
2018年11月15日 木曜日
A
依頼いただく内容やどのような手段をとるかによって、金額は異なります。当事務所では、裁判、交渉等の着手金は最低10万8000円となっておりますが、文書作成のみでしたら3万2400円ということもあり得ます。
ご自身の事件について、どのくらいの費用がかかるのかについては、相談の際に弁護士にお尋ねください。
投稿者 | 記事URL
Q 遺言の内容に納得できない場合、どうしたらいい?
2018年8月11日 土曜日
父が「長男Aに全財産を相続させる」という遺言をして亡くなりました。兄(A)が母の面倒をみるならばそれでよかったのですが、私Bと妹Cが母の面倒をみることになったので母と私たち姉妹(B・C)も父の財産を相続したいと考えています。可能でしょうか?
A
1.お父様の相続人は、妻であるお母様と子A・B・Cですから、話し合いをして、お母様・A・B・Cの全員が同意すれば相続財産を自由に分配してかまいません。
2.では、話し合いがまとまらない場合はどうでしょう。その場合、お母様・B・Cは「遺留分減殺請求」をすることができます。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に、相続財産のうち、法律上留保されることが保障された割合のことです。
ご相談のケースの場合には、
◆お母様には、
「相続財産」×「法定相続分1/2」×「遺留分1/2」=相続財産の4分の1
◆B・Cには、それぞれ
「相続財産」×「法定相続分1/2×1/3」×「遺留分1/2」=相続財産の12分の1
を相続することができることになります。
◎遺留分減殺請求(内容証明郵便)
(遺留分減殺請求権は、相続の開始および減殺請求しようとする贈与等があったことを知った日から1年以内)
⇒ 1.話し合い
⇒ 2. 話し合いで解決しない場合、調停
⇒ 3.調停でもまとまらない場合、裁判
3.では、「遺留分減殺請求」はどのような手続きで行うのでしょう。まずは、遺留分減殺の意思をAに伝えます(その際には、後で証拠として使えるように文書にし、内容証明郵便で送りましょう)。そのまま話し合いで済めばいいのですが、解決しなかった場合には、調停を、それでもまとまらない場合は裁判を行うことになります。
ここで注意しなければならないのは、遺留分減殺請求権は、相続の開始および減殺請求しようとする贈与等があったことを知った日から1年以内に行使しなければならないということです(相続の開始から10年を経過したときも請求できなくなります)。
4.親族間の紛争は、感情的な行き違いによって、当事者どうしではなかなか話し合いで解決することが難しい場合が多々あります。そのような場合には、専門家である弁護士が間に入ることで、スムーズに解決に向かうことができます。また、そもそも、せっかく相続人間でのもめごとをさけるために遺言をのこしても、このケースのように内容いかんによってはその目的を達成できません。弁護士は、遺言作成にあたって配慮・注意すべきことをアドバイスすることができます。是非、お気軽にご相談ください。
投稿者 | 記事URL
Q 遺留分-相続人なのですが、遺言書をみると、私の相続分がありません。相続分を主張できないのでしょうか。
2018年8月1日 水曜日
A
遺言書が有効であれば、法定相続分をもらうことはできません。しかし、遺留分の主張ができます。遺留分とは、被相続人が有していた財産の一定割合について、最低限の取り分として、一定の法定相続人に保障する制度をいいます。ただし、遺留分に違反する贈与や遺贈も当然には無効とされず、遺留分減殺請求(相続の開始および減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年以内に主張しないと時効消滅するので注意しましょう)を待ってその効果が覆されます。
遺留分を有する者は、法定相続人のうち兄弟姉妹を除いたもの、すなわち、配偶者、子、直系尊属です。
遺留分の割合について、総体的遺留分は、直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の3分の1、その他の場合は2分の1です。個別的遺留分は、総体的遺留分を法定相続分に従って各相続人に配分して算定されます。例えば、相続人が配偶者と子3人である場合には、総体的遺留分は相続財産の2分の1であり、個別的遺留分は、配偶者が相続財産の4分の1、子がそれぞれ12分の1となります。相続人が父母のみの場合 (直系尊属のみの場合) には、総体的遺留分は相続財産の3分の1であり、個別的遺留分は父母それぞれ6分の1となります。
投稿者 | 記事URL
Q 遺言-遺言書を作成しようと思っているのですが、どのような方法で遺言書を作成すれば良いですか。
2018年7月31日 火曜日
A
民法上、遺言を有効になし得る年齢が規定されており、満15歳に達した者に遺言能力が認められます。また、成年被後見人の場合、遺言の時に本心に復し意思能力を有していれば有効な遺言となります。但し、医師二人以上の立会が要求されています。
遺言書の形式は、民法上3種類あります。
まず、(1)自筆証書遺言があります。遺言者が、遺言の全文、日付、および氏名を自署(ワープロは無効)し、署名の下に、印を押せば完成です。この方法の場合、費用もかかりませんし、遺言の存在を秘密にしておけますが、隠匿、破棄のおそれが高く、遺言者の死亡後に、家庭裁判所において検認や開封の手続をとる必要があります。
次に、(2)公正証書遺言があります。証人2人以上(相続人や、その妻、未成年者はなれません)が立会い、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して読み聞かせ、遺言者と証人が筆記の正確なことを承認して署名押印し、公証人が方式に従って作成した旨を付記して署名押印して、完成です。(1)に比べて、公証人の手数料がかかり手続も煩雑ですが、遺言の存在や内容を明確にさせておくことができ、滅失、偽造の恐れも少なく、検認手続も不要なので、有効な方法です。
さらに、(3)秘密証書遺言があります。遺言の内容を秘密にし、自筆証書遺言よりも安全にしておく方法です。遺言者が作成して署名・押印した証書を封印し、公証人と証人2人以上の前で申述し、公証人が日付と申述を記載し、遺言者・公証人・証人が署名・押印して完成です。
遺言制度は、人の最後の意思を尊重するものですので、いったん、遺言書を作成しても、その後、気が変わって、その内容を変更したいと考えたら、いつでも自由にその内容を撤回することができます。撤回の方法は、遺言の方式によって、されなければなりません。なお、被相続人の死亡後、複数の遺言書が見つかった場合には、最後の日付の遺言書が有効になることを覚えておきましょう。
投稿者 | 記事URL
Q 特別縁故者-身寄りのない人の資産はどうなるのですか。
2018年7月21日 土曜日
A
相続人がいないことを相続人の不存在といいます。このような場合、相続債権者等の利害関係人の請求により、家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、相続財産を管理・清算させることにしています。相続財産管理人は、官報に相続人であることを名乗りでるよう公告し、名乗り出ない場合は、相続人の不存在が確定します。相続人が存在しない場合には、特別縁故者(内縁の妻、療養看護に努めてきた親族友人等)が、一定の手続により、相続財産の分与を受けることができます。
投稿者 | 記事URL
最近のブログ記事
- 相続あるある(弁護士 渡辺登代美)
- 離婚した後、旧姓に戻る? それとも夫の姓をそのまま使う?子どもが大きくなった後、旧姓には戻れるの?という疑問にお答えします(弁護士 川口彩子)
- 遺言作成は元気なうちに~遺言作成のすすめ~(弁護士 星野文紀)
- よりよい遺言書を作るために~「遺言執行者」をご存知ですか?~(弁護士 中瀬奈都子)
- 老後に備えた新しい「家族信託」活用のすすめ(弁護士 川岸卓哉)
- 知っておくと安心!初回の調停で気をつけること(弁護士 川口彩子)
- 夫(妻)が通帳や保険証券を見せてくれない。どうしたらいい?~ちゃんと財産分与を受けるために今できること~ (弁護士 中瀬奈都子)
- 空き家問題の対処法(弁護士 星野文紀)
- 民法・不動産登記法等の改正等 その2(弁護士 山口毅大)
- 改めて遺言について考えませんか?(弁護士 小野通子)
月別アーカイブ
- 2025年11月 (1)
- 2025年10月 (1)
- 2024年11月 (2)
- 2024年9月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年7月 (1)
- 2023年6月 (1)
- 2023年2月 (1)
- 2022年9月 (1)
- 2022年6月 (1)
- 2021年7月 (1)
- 2021年5月 (1)
- 2021年4月 (4)
- 2021年3月 (13)
- 2021年2月 (2)
- 2021年1月 (1)
- 2020年2月 (1)
- 2020年1月 (3)
- 2019年9月 (1)
- 2019年8月 (3)
- 2019年6月 (2)
- 2019年5月 (3)
- 2019年4月 (9)
- 2018年11月 (1)
- 2018年8月 (2)
- 2018年7月 (5)
- 2018年6月 (4)
- 2018年5月 (1)
- 2017年12月 (2)
- 2017年6月 (2)
- 2017年2月 (2)