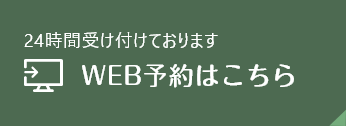トピックス
東京裁判とニュルンベルク原則/根本孔衛 2007
2016年8月17日 水曜日
1 東京裁判とニュルンベルク裁判の40周年
東京裁判というのは、日本国が行った15年戦争について、東條英機をはじめとする政府の政治、軍事、外交、官僚と言論界の指導者と目された28名に対して、極東国際軍事裁判所条例に基づいて、その戦争責任の追及がされた裁判です。東京の市ヶ谷台にあった元陸軍士官学校(現在防衛省庁舎)講堂に設置された法廷で1946年5月3日から審理が始まり48年11月12日に判決が言渡されるまで2年余にわたって連合国側の裁判官、検察官によって国際刑事裁判が行われました。今ここに書いておくことは、この裁判自体のことではなく、国際法律家協会が主催して、1986年6月7日に始めて89年3月25日にその総括の集まりまで11回にわたった「東京裁判と戦争責任を考えるシンポジウム」のことです。それとその企画の契機となった、1985年11月23、24日の両日、国際民主法律家協会(IADL) 、レジスタンス運動者インターナショナル、社会民主法律家協会等の7団体が主催し、西ドイツのニュルンベルク市で開かれたニュルンベルク裁判40周年国際会議についてです。
ニュルンベルク裁判は、第2次世界大戦の連合国側によるロンドン協定で制定された国際軍事裁判所憲章に基づいてニュルンベルク市裁判所の建物に設置された法廷で、1945年11月20日から46年10月1日まで行われたナチス党支配下のドイツ「第3帝国」の党、政府、軍部、経済界等の指導者たち24人の戦争責任が刑事裁判として問われました。しかし、そのうち1名は重病による免訴、1人は自殺しましたので現実に法廷に立ったのは22名です。これらの被告人のほかにナチス親衛隊、国防軍統合司令部等6つの集団ないし組織があわせて訴追されたのは、東京裁判にはなかったことです。これは、日本の政治が、いつ誰が決定を下すかはっきりしていない「無責任」体制としておこなわれたのとナチスの1党支配の違いからきたものでしょう。
ニュルンベルク裁判は46年10月10日に判決の言渡があり、12人が絞首刑、7人が拘禁刑、3人が無罪となりました。彼らを有罪とした根拠となった戦争犯罪の法理の集約がニュルンベルク原則であり、それは同年12月11日の国連総会によって確認されました。
1985年はこの裁判の開始から40年にあたり、この裁判と係り合いの深かった諸団体によってその記念の国際会議を開くことが決定されました。この企画と内容についての案内がその年の9月にIADL本部からその支部である日本国際法律家協会にの招請状とともに送られてきました。その文書にある会議の目的は、この裁判の歴史的総括とその成果を、とりわけ国際法の発展という観点から点検し、そこから今日の時代に対処するための教訓を学びとる、というものでした。案内では、この目的と会議の開催は諸国がおかれた内外の状況に照らし、法的政治的にアクチュアルな意義があることが強調されていました。
当時の情勢をかえりみますと、1979年の12月にソ連がアフガニスタンに侵攻しました。翌年11月に米国大統領に当選したレーガンは「強いアメリカ」を掲げて、多弾頭(MZ)ミサイルの開発促進、「戦略防衛構想」(SDI)など軍備大拡充に乗り出して、「新冷戦」時代を招来しました。83年9月には中距離ミサイルの西独、英、伊などへの配備が決定され、これに対して西ヨーロッパ全域で平和運動が盛り上がりました。各地の都市では群衆が反核を叫んで通りや広場を埋めつくし、西ドイツでは10月22日に30万の「人間の鎖」が米軍基地を包囲しました。
一方では米ソ間の平和への動きも見られ85年3月にはジュネーヴで米ソの包括的軍縮交渉が開始されました。ソ連ではプレジネフの死(82年9月)に続く2人の最高指導者が相次いで病死するという不安定の政情の中で、85年3月にはゴルバチョフが、共産党書記長に就任して「ペレストロイカ」(改革)を唱え、時代は大きく動き始めました。
日本では、「タカ派」として知られてきた中曽根康弘氏を総理大臣とする内閣が82年11月に成立しました。
▲上へ戻る
2 日本の戦後と憲法9条の制定
日本の戦後は、敗戦の結果としてのポツダム宣言の受諾から始まります。この宣言の条件の実施として、日本国憲法の制定があり(1946年11月)、東京裁判が行われました。ポツダム宣言の受諾にあたって、日本政府は天皇の統治権の存続を保留しました。戦後なお権力の座に居残ったこのような人たちが旧体制の一掃の仕事を進んでする訳がありませんでした。東京裁判の実施はは勿論、日本国憲法の制定でもそうでした。そのことは、幣原喜重郎内閣が連合国軍総司令部(GHQ)から促されて作成し差し出した憲法改正要綱(松本試案)を見てもわかります。そこには天皇の統治が残され、あらためられた部分は大日本帝国憲法に一寸民主的な色付けをしてお茶を濁したものであった、と言っても言い過ぎではないでしょう。あとになってのことですが、憲法9条の戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認の発案者が占領軍の最高司令官マッカーサーか幣原かと論議されましたが、松本試案にはそれはありません。幣原首相の戦前戦中の言動からして彼がGHQが示した9条原案を容認したであろうことはうなずけますが、その発案者であるということは、この事実からしても肯定できません。
戦後の日本の戦力不所持は米国側、ことにGHQから出たもので、これは戦間期の世界思潮であった戦争の違法化を一歩進めたのであります。それは米国の中にあった理想主義の現れであるとともに日本の軍国主義に対する制裁とその再発防止のための保障措置としてなされたものでしょう。9条の考え方はいわゆるマッカーサー3原則が示したものです。彼が9条は幣原が発議したと言ったのは、彼が1950年6月におこった朝鮮戦争の中で、彼が占領軍の最高司令官として日本軍隊の再建を指令したことと9条制定を指示したこととの間にある矛盾を取り繕うための、後になってからの弁明であった、と思われます。
日本国憲法上では日本国民がその制定権力になっていますが、現実にはそうなっていなかったというというのが、「皇軍」の一兵士として戦争終結をむかえ、戦後の混乱の中で生きていくのに精一杯であった私の実感でもありました。ほとんどの国民は、敗戦の現実に直面して茫然自失の状態であり、今日明日の命を繋げていくための食物を求めて動きまわる毎日でした。そんな生活状態と荒廃した社会を何とかしたい、国の建て直しも考えなくてはならないというのが民集の思いでありましたが、憲法をどうするかにまでは、とても考えが及ばなかったのが実情でしょう。
この憲法を制定した議会の衆議院議員の総選挙が行われたのは45年12月17日です。松本試案を拒否した連合国軍総司令部(GHQ)が自分で作った憲法草案を日本政府に手渡したのは46年2月13日です。それを受け入れて日本政府が作成した、主権在民、人権尊重、戦争放棄、象徴天皇制の憲法草案改正要綱を発表したのは3月6日ですから、先に行われた総選挙の結果にはこの憲法改正案は全く反映されていないわけです。この憲法改正要綱が発表された後食糧メーデーなど生活をまもるための大衆運動はありました。しかしGHQは、このような民衆の動きを見て、日本政府に指令を発し、占領目的に有害とされる行為を処罰する政令を6月12日出させて大衆運動の盛り上がりを抑えようとしました。こうしたことで、改正要綱発表後も憲法制定についての論議は国民のなかにひろがらず、そんな状態では新しい憲法は国民が自主的に制定したものであるとは言えなかったと思います。
戦争の放棄は、終戦直後の苦しい生活にあえいでいた国民の、戦争はこりごりだ、2度としたくない、という気持ちとぴったりだった、と思います。国民のそのような心情がが戦力の不所持、交戦権の否認といった平和に対する理念にまでなっていたか、は疑問です。むしろ国民の大多数は、打ちひしがれた日本が再び軍隊をもって海外に進出して行くといったことはみじめな現状からはとても考えられない、といったところではなかったか、と思います。
権力者の側でも、連合国軍の占領下におかれているという現実がありました。GHQがその占領政策実施の便宜を考慮してか、とにかく天皇制が残されたこともあり、当分は軍事力がなくとも我慢するほかない、という考え方が多数だったでしょう。その中には吉田茂に代表された人たちのように、このことを積極的にとらえて軍事費の負担から免れることによって、その余力を経済にそそぎ、国家の復興と再建に傾注しようという後の保守本流となる考え方もありました。
憲法制定の議会答弁で吉田首相は、野坂33共産党議員から出された、侵略戦争は否定さるべきだが、自衛のための戦争は正しい戦争ではないか、という質問に対して、近年の戦争の多くが国家防衛の名で行われたことは顕著な事実であり、過去の日本の戦争もそうであったのであるから、正当防衛権を認めること自体が有害であると思う、と言って、自衛権をも否定しています。彼が、本心からそう信じて発言したのか、占領の圧力をできるだけ早く軽くしていくための政略上そう答弁したのかは、彼がその後の冷戦の影響下で米国側と軍再建について協議をした事実から見てにわかに断定できません。しかし、憲法制定議会当時の政府見解が憲法9条を文字どおりに受け取り、自衛のための戦争をも否認していたことは事実です。
▲上へ戻る
3 安保条約の改定と憲法9条の活性化
戦後間もなく始まった冷戦の深まりの中で、米国は日本をその側に引き込み、自らの役に立てるために占領政策の変更をおこないました。それには連合国と日本の約束でありましたポツダム宣言の拘束をはずすことが必要でした。そのための措置として、日本を米国のほうにとりこんでいくための対日講和が51年9月に行われ、同時に日米安保条約が締結されました。これによって占領は終わりましたが、日本の全土にわたる米国の「半占領」状態が続きました。再建された日本の軍隊は強化され、警察予備隊から保安隊となり、さらに自衛隊となりました。戦後公職から追放されていた政治家たちをはじめ、各界の旧指導者たちの追放が続々と解除され、再び彼らの活動が始まりました。戦争犯罪容疑者として収監されていた岸信介元商工大臣も解放されて政界復帰をとげ、57年2月には首相に就任しました。彼によって、60年6月、基地許与協定であった日米安保条約が、日本の領域に限るとはいえ日米共同作戦がおこなわれ、また日本の防衛力強化を約束する軍事協力協定に変質しました。積極的な戦争反対というよりは、厭戦、戦争回避という心情から9条を支持していた国民も、安保条約の改定によって戦争は他人事ではなくなりました。その危険を安保条約改定のかたちで現実として突きつけられて、国民の各層の人びとがその反対に立ち上がったのが安保改定反対の大闘争であった、と思います。
1954年3月1日米国が南太平洋ビキニ環礁で行った水素爆弾爆発実験で、そこから約160㎞離れた海域で操業中の焼津漁港所属の第5福竜丸がそれから放出された放射物質「死の灰」をあび、久保山愛吉さんが死亡したということがおこりました。それを契機にして、国民は広島、長崎への原爆投下による被害の惨状を思い起こし、平和と生きることの大事さを問い直す原水爆禁止運動が全国的に広がりました。安保反対運動の背景には国民のこのような平和意識のひろがりがありました。こうして憲法9条の存在は法文上のことに止まらず、国民の心の中で生きてきたのだ、と思います。
安保改定反対運動が革新政党、労働組合、学生などが主力であった範囲から、一挙に一般大衆の中に広がり文字どおり国民的大運動となったのは、5月19日、政府・自民党が衆議院で質疑を一方的に打ち切り、警官隊を導入して翌日未明に改定安保条約を自民党単独で採決をしてからでした。国民はこのような民主主義を破壊する暴挙に怒り、17万人のデモ隊が空転状態の国会を取り囲み、560万人が参加する各種の実力行使する等、全国にわたる大衆行動が繰り返し行われました。このような反安保の国民的統一戦線のひろがり、組織の結成とが圧力となって予定されていたアイゼンハワー米大統領の訪日は中止されました。岸内閣は、6月19日新安保条約を「自然承認」のかたちでかろうじて成立させることが出来ましたが、総辞職をせざるをえなくなりました。 新憲法の三大原則の一つである平和主義は、占領中には米軍がおり、その下での朝鮮戦争に際して日本軍隊が再建され、それらが講和後も引き続かれ強化される有様でしたから、その意味では9条2項は「空文」でありました。しかし、憲法が制定された後国民の中で平和の理念が育ち、それが安保闘争、反核などの平和運動となって9条に活気を与え、その力が権力側をして自衛隊をあからさまに軍隊と呼ぶことを憚らせ、各地の反基地闘争などによって軍事的行動を抑制させることになり、また日本国をアジア周辺で行われた米国の戦争に直接参加させませんでした。また国民主権の原則も息づき、国民の主権者としての自覚も強まってきていたことは、安保改定国会においての政府・自民党の国民の意思無視に対する抗議行動のひろがりの有様が示したとおりです。
▲上へ戻る
4 国際的「契約」としての日本国憲法
日本国憲法制定時には、国民は、実質的な主権者としての地位を獲得しており、その確認として憲法の条項を定めたとは言いにくい状態だったのです。国民が主権者であるというためにはその後の憲法関連の諸運動によって憲法の諸条項を実体化して、自分たちの憲法と言えるようになることが必要であったわけです。その成果は制定後の国民の憲法闘争をはじめ民主主義と平和のための運動における奮闘いかんにかかっていたわけです。
日本国憲法の制定は、ポツダム宣言受諾の履行にほかなりません。それは米国ばかりでなく連合国、ことに日本が侵略したアジア諸国民に対する日本国民の国際的な誓約でありました。日本国民が主権者になるということは、その誓約実行の責任者の位置に立つことになります。戦力を持たない日本国家と国民の平和と安全が保たれるためには、その人たちの私たちに対する信頼と友好がなければなりません。その実現には日本国民の過去の戦争に対する反省があり、それを具体的なかたちで表す必要がありました。
新憲法の前文には過去に対する反省があり、世界の恒久平和建設に邁進すべきことの決意がなされ、その実現を可能にする国内措置の指標が指示されています。それは憲法の各条項に具体化されています。しかし日本の戦後の実情は、大日本帝国的状態がなお残存し、そのような心情の持ち主が政財界の有力な地位を占めておりました。また日米安保条約と自衛隊の存在によって憲法の平和主義は蝕まれており、それが強化されていくことによって近隣の国からの軍国日本復活への警戒心はなくなったことがありません。憲法の精神の発揮の妨げとなっているこのような障碍を取り去っていくことが国民に残された責務でありました。
もう一つの平和実現への決意のあらわれは侵略戦争が引き起こした被害に対する償いの実行でした。米国は、日本を冷戦体制の西側陣営に組み入れ強化するために、講和について被害国側の要求を抑えつけ、しかも賠償を現物と役務としました。それは戦後の日本産業の復興を促進し、資本の海外進出の手がかりとなりました。しかし日本が誠実な償いをしなかったことによってアジアの中で心からの友人を持たないことになりました。
▲上へ戻る
5 占領と「国際的」裁判
講和によって占領下の抑圧がとれて、労働運動は上昇をたどり、教職員の勤評反対闘争などがありました。一方安保体制強化の基地拡張に反対する砂川事件とその裁判闘争がありました。これらの動きを抑えるための警察官職務執行法改正の企てに対して立ち上がった国民の統一闘争はこれを阻止しました。このような激動の中に新米弁護士として放り込まれた私は無我夢中というのが本当のところでした。この頃は弁護士の数も少なかったものですから、全国各地を東に西に飛び歩いておりました。
翌60年には安保改定問題が具体化し、これに反対する国民的大闘争には勇んで参加し、毎日のように国会の周辺に行っていました。国会構内で樺美智子さんが死亡した日には国民救援会の人たちと一緒に検視が行われていた警察病院に行き、その実相の説明を要求したといったこともありました。6月19日に新安保条約が自然承認になると、それまでの昂揚が1気に抜け去って索漠とした気分になりました。安保海底反対と併行して、日本産業のエネルギー源が国産の石炭から海外から入る石油に変わる転回点であった三池炭坑の整理解雇反対闘争がたたかわれていました。私はその頃「東北の山の夜明け」といわれた国有林労働者の雇用の近代化闘争で山まわりをしていたため、当時の労働組合運動の頂点ともいうべき三池争議には参加しませんでした。日本の労働運動は否応なしに国際情勢にかかわることになりました。国際的労働問題として、1950年6月に朝鮮戦争が始まって間もなく8月頃から行われたレッド・パージの問題があります。冷戦の中で「反共」を強めていったGHQの指令に資本家が乗っかって、多くの労働者が共産党員もしくはその強調者ということで職場から排除されました。その不当性を抗議し、解雇の理由を問い糾す労働者に対して、資本の側は具体的理由について何も答えることができませんでした。解雇された労働者は裁判所に、レッドパージが憲法19条に定める思想の自由に反するとの理由で解雇無効の裁判を求めましたが、裁判所は占領下を理由にこれを斥けました。ポツダム宣言はその10項で思想の自由と人権の尊重の確立を約束していますから、これに反するGHQの指令は無効なはずです。しかし、占領下の裁判所は指令はどうすることもできない、というのです。
52年4月に講和条約が発効し、占領はなくなり、裁判所は憲法に従った裁判ができるようになり、またそうしなければならなかったはずです。それに着目した被解雇者たちは、その後の民主化の進展と労働組合の盛り上がりの中で、レッド・パージの不当性をあらためて裁判所に訴えようという動きが出てきました。自由法曹団では、私たち新人弁護士にそのような事件の担当を要請してきました。私は山形県酒田市に工場があった鉄興社という電気化学関連会社の事件を担当しました。訴えた原告たちは皆真面目に勤務し、非行も欠点も見当たらない人たちばかりでした。会社側の答弁書では原告たちが協調性に乏しいとか、反抗的だとか抽象的な事由をあげるだけで、解雇は結局GHQの指令だったということに帰するというものでした。要するに占領中の指令は占領解除後も有効だ、というのです。この裁判は会社側の主張に沿って原告敗訴の判決となりました。私の同僚が担当したレッド・パージ無効裁判も同じような結果になりました。
もう一つ私の国際関連事件としては65年に起こされた沖縄在住者の、本土渡航許可拒否の是正要求と原子爆弾被爆者医療法の適用を請求する事件です。当時の沖縄は、日本の他地域が講和によって占領状態がなくなったにもかかわらず、平和条約3条によって切り離され、なお米軍政下におかれ、日本国の施政権が及ばぬものとされていました。沖縄住民の原告らは、同じ日本国民でありながら何故このような差別扱いを受けなければならないのか、ポツダム宣言10項には占領軍は日本の民主化が達成されれば撤収するとの約束があり、他地域ではそれが実現されたのに、沖縄地域だけが何故に除外されたのか、米国が沖縄に対し対日講和後もなお行使している施政権とは何ものなのか、その根拠と権限範囲は国際法のどのような法源に由来し、正当づけられるのか、を裁判で問いただしたのです。この裁判も敗訴に終わりましたが、判決はその理由を納得できるかたちで少しも解明していませんでした。沖縄は日本国の領域ではありますが、憲法は全く遮断されていたわけです。
私の国際法に対する関心はこの二つの事件でひきおこされました。
▲上へ戻る
6 「安保効用論」と高度経済成長
このように、講和後の日本国は独立国であって独立国でないような何とも訳のわからない状況におかれていました。安保改定反対闘争で倒れた岸内閣を引き継いだ池田勇人を首相とする内閣は、安保条約改定の強行で離れ去っていった民心をひきとめるために、ひたすら「低姿勢」に出て「寛容と忍耐」をとなえ、「10年で国民所得を2倍にする」という所得倍増計画を打ち上げました。その裏付けは「安保効用論」でした。その言い分は、日米安保条約によって日本の安全を米国の軍事力に委ねることによって非生産的な軍事支出を最小限におさえられ、ひたすら経済発展に励むことができるのだ、ということであります。
米国は64年頃からベトナム問題に深入りをし始め、65年初めには本格的な軍事行動に出てベトナム戦争の当事者となってゆきました。ベトナム人民の抵抗によって戦争は泥沼化し、米国は4万6千余名が戦死し、1450億ドルという巨額の軍事費を支出しましたが、インドシナ半島に覇権を打ち立てるというその意図は打ち砕かれました。73年初めには米全軍の撤退となり、76年にはベトナムの南北統一がなりました。
米国はこの間日本に対して一層の協力、分担を要求してきましたが、日本政府は直接的な軍事協力については憲法9条の存在を理由にして応じませんでした。そして米軍行動を後方から支えました。軍需品の製造、供給、装備の修理等のベトナム特需によって日本経済は折からの不況を乗り越えて発展しました。一方日本国民の中からはベトナム戦争反対運動が起こり、日本政府が軍事協力に走ることを抑止してきました。こうしてみると、「安保効用論」の反面は「憲法9条効用論」ということです。
日本が軍事費支出を抑えて経済発展につとめた結果は、1960年には米ドル表示で430億ドルであった国民総生産(GNP)は、85年には13,433億ドルになりました。それと米国のGNPとの比較では、60年には米国は日本の11.7倍でしたが85年には2.9倍に縮まりました。この間は日本を「経済大国」化させた高度成長のの時代です。
この時代の口火を切った池田内閣以来、82年暮れに中曽根内閣が成立するまでの間、佐藤栄作、田中角栄、三木武夫、福田赳夫、大平正芳、鈴木善幸と続いた内閣の政治はこのような方針にそって進められてきました。勿論それは国民が一生懸命になって働いたことの結果ではあります。
これらの内閣は吉田茂の系統を引いて米国の政策に追随はするが、その軍事的協力強化の要求に対しては憲法9条を理由にして可能な限り抑え、その力を経済建設に注いでいくという、いわゆる保守本流に属する人たちです。三木、福田の両内閣は保守本流とはそれぞれ少しづつ毛色も方向も違いますが、経済、外交政策では広義の保守本流といってもよいのではないでしょうか。ベトナム戦争、ソ連との間の核兵器と宇宙開発競争などによって起こった米国の国力の低下の中では、政策としては、米国の要求にそのまましたがい、軍備強化によって日本の国際的地位と威信を高めようという選択肢もあったわけですが、「安保効用論」によるこれら保守本流の内閣はそのような方針をとりませんでした。その意味では、それらの内閣によって憲法9条は一層傷つけられてきたとはいえ、彼らによって守られてきた、ということもできると思います。
▲上へ戻る
7 中曽根内閣の登場と「戦後政治の総決算」
日本の国力が、絶対的にも相対的にも高まってきた80年代になり、それまでつづいてきた自民党の保守本流の政治の裏側にいた、「自主憲法制定論」者である中曽根康弘氏が82年11月に首相となり政治の表面におどり出てきたわけです。日本の戦後政治の転換期が迫ってきたのでしょう。
中曽根首相は、年が明けた1月に早速訪米し、その18日のレーガン大統領との会談で「日米は太平洋をはさむ運命共同体であると認識している」という表明をしました。翌18日の「ワシントン・ポスト」紙記者との会見で、ソ連機の日本侵入阻止に言及し、「日本列島を不沈航空母艦とする」と言い、またソ連軍事行動に対しては3海峡の封鎖をもって対処する、という発言をしました。このことが日本に伝えられ、国民を驚かせました。訪米から帰った直後の24日、彼は国会での初の施政方針演説で、日本は今、戦後史の大きな転換点に立っている、と述べ、戦後にできてきた制度や仕組みをタブー視することなく、根本から見直すことが必要であることを強調しました。
83年3月には日米防衛協力小委員会でシーレーン防衛の共同研究を行うことが合意されました。84年12月には首相の私的諮問機関の「平和問題研究会」が三木内閣が定めた防衛費の国民総生産額の1%という枠をはずすという報告書を提出しました。85年になると、中曽根首相はレーガン大統領とのサンフランシスコ会談で、そのSDI構想に理解を表明しました。このような中曽根政治の結論的言明が、同年7月27日の自民党の軽井沢セミナーで発言した「戦後政治の総決算」です。彼から「戦後政治の総決算」の決意をきかされ、彼の言動に不安を感じていた私たちとしてはいやが上にも警戒心を高め、これに対する備えを作り出さなければならないと決心せざるをえませんでした。
戦後政治といえばその出発点は日本国憲法の制定でした。新憲法は日本の改革の結果の確認というよりは目標の設定でした。私たちは、以来、憲法の平和主義、人権に関する諸条項を実のあるものにすることに持てる力を注ぎ込んできました。そして一定の成果を上げてきました。例えば、平和の問題では反安保改定、反核、反基地、ベトナム戦争反対などの運動であり、高度成長の過程では公害に反対し規制する法を要求してこれを実現し、また朝日訴訟などの生存権を確立しようとする運動が起きました。また革新自治体を成立させました。これは地方自治においての住民主権の確立でした。そのほか色いろな自由と人権の伸長があります。中曽根首相の発言は、これらの成果を取り崩していくのだ、ということを意味しています。
「戦後政治の総決算」には、過去の日本を裁き、軍国主義の清算をはかった東京裁判に対する批判と、その成果の打ち消しも含まれています。日本政府は、平和条約11条で東京裁判を受諾していましたが、中曽根首相をはじめ保守の中の「タカ」派は、この裁判の事実の認識とこれを裁いた法理を「東京裁判史観」といって攻撃をしてきていました。東京裁判は、日本が中国侵略を始め太平洋戦争に拡大していった過程、その中での政府、軍部の動き、戦地・占領下での日本軍の暴虐行為など、日本国民がそれまで知らされていなかったことを白日の下にさらけ出し、またそれらの行為が国際法に違反し、許されないものであったことを国民に認識させ、今後の日本がとるべき行動の指針を示すものでありました。「タカ」派の「東京裁判史観」批判は、その対立物である「大東亜戦争史観」の復活強化であります。
▲上へ戻る
8 ドイツと日本の復興と国際秩序への参入
軍国主義の日本とナチズムのドイツとは第2次世界大戦で同盟国として戦って共に敗北しました。日本は事実上米国の単独占領でしたが、ドイツは東西に分割され、その東側はソ連、その西側は米英仏3国の占領下におかれました。西ドイツは、占領中の1949年5月に「ドイツ連邦共和国基本法」を制定しましたが、憲法は東西ドイツの統一後に予定されていました。
1954年10月のロンドン9ヵ国会議の結果55年5月5日に西ドイツは主権を回復しました。この決定には、(1)西ドイツの防衛計画は北大西洋軍(NATO)の勧告に従う、(2)NATO軍司令官は平時には西独軍の視察権を持ち、戦時には西独軍の全作戦遂行権を持つ、という再軍備とNATO加盟が裏付けがなされていました。それは対日講和と日米安保条約の関係と同じです。
西ドイツは日本に数年先んじて奇跡の高度成長を遂げていました。西ドイツ成立以来の首相のアデナウアーが63年に引退し、同じキリスト教民主同盟のエアハルトが跡を継ぎましたが、69年には社会民主党のブラントが首相となり、「東方政策」を進めて、ドイツの平和と安定に努めました。70年にはソ連との間にモスクワ条約を締結し、ヨーロッパの戦後現存の国境の確認とその不可侵、武力の行使と威嚇の放棄を約束しました。70年12月にはポーランドとの国交正常化条約に署名のためワルシャワを訪れたブラント首相は、ドイツ軍によって壊滅させられたユダヤ人の住居地域であった旧ゲットーの記念碑の前に跪きました。チェコとも同様の条約が結ばれました。72年12月に東西両ドイツの間で関係正常化条約が調印され、翌73年9月には二つのドイツの国連への同時加盟が実現しました。
これらの経緯は、日本が56年に日ソ共同宣言で国交を正常化して同年12月に国連加盟が実現し、71年7月のニクソン大統領の訪中後72年9月に日中共同声明により国交が回復したことと比較されます。ヨーロッパでは75年夏のヘルシンキ宣言で人権と自由を尊重する新しい欧州の共存体制がうたわれましたが、日中国交回復には米中の対ソ政策が影を落としていました。79年12月にはソ連のアフガニスタン侵攻があり、新冷戦といわれる状態となり、欧州全域に中距離核ミサイル配備の問題が起こりドイツでその反対大運動が起こったことは既に記したとおりです。日本では82年6月の国連軍縮特別総会に向けて8千万に及ぶ反核・軍縮要求署名が集まりました。
第2次世界大戦で同じく糺弾され敗戦国となった日本とドイツは、このようにしてその後の冷戦の中で共に西側に組み込まれて復興していき、1985年には「大国化」していました。この二つの国が違うところは、日本は専ら米国に追随することにつとめ近隣の国々から孤立化していましたが、西ドイツの平和と繁栄は「宿敵」であったフランスをはじめ周囲の国々と結ばれた欧州共同体(EC)などの友好と信頼の関係に支えられていたことでした。
▲上へ戻る
9 ニュルンベルク裁判40周年国際会議への参加
(1) それまでの準備作業
私は、このような西ドイツの行き方について、日本の有様を重ね合わせて、その相違について、気にかけていました。そこにニュルンベルク裁判40年にあたって国際会議を開き、日本側にも出席してほしいという呼びかけがきたのです。私としては中曽根首相の昨今の言動を思うにつけ、誰かこれに出席して東京裁判の成果にてらし合わせてその意味を再確認し、それを深め広げるための運動の3考にしたら役に立つのだが、と思いました。ところが協会の中からは自分が出席しよう、という声が聞かれませんでした。
私は、ドイツ語は全くといってよいほどできませんし、英語も読むことはとにかく聞くのも話すのも駄目ですので、この参加について声を出すのをためらっていました。しかしなお出席者の声がきこえてきませんでしたので、仕方がない、自分が行こうという気になりました。幸いに斉藤鳩彦弁護士の妹の斉藤暎子さんがベルリン大学で比較文学を教えておられ、ヨーロッパで開かれる諸会議に参加する日本代表を援助されていることを聞き知り、お願いをしてみると通訳をしてもよいということでしたので、私は出席することに決しました。
ところで私は、それまでニュルンベルク裁判のことはおろか、東京裁判のこともろくに知っていませんでした。出席するからには、同じような意味をもつ東京裁判のことを紹介する発言をすれば何か役に立つのではないかと思い、会議が開かれるまでの2ヵ月余りの短い間ですが、にわか勉強を始めました。まず松井芳郎名古屋大学教授にお願いしてこの二つの裁判についてレクチャーを受け、おおよそのところがわかりました。
次は文献探しとそれを読むことで、東京弁護士会図書室のカタログにあたりました。そこで見つかった本で感銘を受けたのが、大沼保昭東京大学教授の「戦争責任論序説」でした。この本は国際法学者の立場から、第1次世界大戦後の世界で進展してきた戦争の違法化と違法な戦争の指導者個人の責任論が、国家間の条約などの実務と学説によって成立してきた歴史を解明した実証的な分析の本でした。国内でいわれてきていた、東京裁判が問うた「平和に対する罪」は「勝者の裁き」であって法的根拠がない、といった論説は、第1次世界大戦の戦後処理や戦間の国際関係とその学説の発展の歴史的事実を無視するもので、却って根拠に乏しいことがわかりました。さらにこれらとの関係で日本国憲法の平和主義の由来と意義の理解をさらに深めることができました。
もう1冊は、ニュルンベルク裁判で米国の主席検察官として戦争犯罪追及の先頭に立ったロバート・ジャクソンの報告書でした。これは彼が、ニュルンベルク裁判が拠った「国際軍事裁判所憲章」の基礎となった、1945年6月から8月にかけて行われてロンドン協定となって結実した会議に出席して、米国政府を代表して発言し説得して会議をまとめ上げた経過の報告書です。第1次世界大戦後の米国は、講和会議で国際連盟の結成を先導したウィルソン大統領の願いと期待に反して、再び戦前の孤立主義の立場に戻り、交戦国への武器輸出を禁止した中立法を1935年に制定していました。1939年9月ヒトラーのポーランド進撃により、第2次世界大戦が開始されて、時の大統領ルーズベルトはこの戦争のもつ平和への脅威を察知し、米国の世論に対し連合国への支援を訴えました。米国の世論は連合国に同情を示しましたがこの中立法があることによって米国政府は具体的な支援はできませんでした。その中で司法長官として大統領を助け、41年3月に武器貸与法を成立させて、連合国側への軍事援助を可能にしたのがジャクソンでした。このように彼は、米国を事実上「宣戦布告なき戦争」に踏み込ませたことについて、その責任を分かち持つ者でした。彼としては、この戦争に参加した米国の立場の正当性をなんらかのかたちで論証する必要がありました。それは同時にまた自らの戦争中の言動の正当性を明らかにし、その責任を弁明するものでした。彼がロンドン会議で、ソ連、フランスと法の組み立て方の違う人たちの中で戦争の戦争責任の追及を共同謀議という訴因によって組み立て、また通例の軍事裁判方式にこだわる英国を説得して、ナチス・ドイツの侵略の根源にまでさかのぼってその罪悪を明らかにする裁判を実現しようとする、その気迫あふれた発言内容には胸を打たれるものがありました。
▲上へ戻る
(2) 報告書の作成
このにわか勉強の結果は「東京国際軍事裁判とその遺産」という報告書にまとめました。その1部は「東京法廷の経過と概要」として、2部は「日本の国内法と人民の運動に与えた影響」としました。
この概要は、東京裁判とニュルンベルク裁判との比較に重点をおきました。 東京裁判で適用された法理と訴訟手続を定めた極東国際軍事裁判所条例は、連合国によってなされた「戦争犯罪処理に関するモスクワ宣言」(1943年10月30日)、「ヨーロッパ戦争犯罪人裁判に関するロンドン協定」とこれに附属するニュルンベルク裁判について定めた「国際軍事裁判所憲章」にならっています。その内容は、後者にあった犯罪団体処罰が前者にないなどいくらかの相違はありますが、本筋は同じです。
東京裁判の特徴は第一に、ニュルンベルク裁判が米英仏ソと連合国の裁判であったものに対し、東京裁判は米国の影響が強く、この裁判条例が米国が任命した占領軍最高司令官によって制定されたことです。これを手続から見れば、ニュルンベルクでは4ヵ国の主席検察官がいるのに、東京では主席検察官は米国人一人だけで、彼が訴追を主導しました。
日本の国制によれば国最高の権能者、国政の決定権者であり、また軍隊の統帥権者であった天皇の訴追が行われなかったのが特筆すべきことでした。米国は、戦後も天皇の統治権の存続を強く望んでいた日本の支配層を手なずけて冷戦下に組み入れ、また天皇を民心慰撫の道具としてその占領行政に役立てようとするつもりであったからです。天皇不訴追は初めから決めていたと見えるのは、ニュルンベルク裁判の国際軍事裁判所憲章では公務上の地位による行為の不免責の規定で元首もその例外でありえない、という明文があるのに東京国際軍事裁判所条例ではそれが消えています。
東京裁判で裁判所に提出された訴状の訴因は、平和に対する罪、殺人、通例の戦争犯罪及び人道に対する罪の3部に分けられていました。条例には、平和に対する罪、通例の戦争犯罪、人道に対する罪が犯罪類型にあげられています。殺人の訴因は判決ではほかの訴因の中に吸収されました。この法廷の被告人が通例の戦争責任を問われたのは、この戦争犯罪についての司令官としての責任であり、あるいはそれを放置したことの責任です。ニュルンベルク裁判では、ナチスと軍部の人種差別による殺害、虐待等に対する人道に対する罪がこの法廷設置の一番大きな動機であったし、裁判の実際でもその主役ともいうべき扱いをされたのに対して、東京裁判では人道に対する罪は通例の戦争犯罪の添えものとして少しばかり取り上げられたに過ぎませんでした。
平和に対する罪の訴因は、1928年1月1日から45年9月2日の長きにわたっています。日本の侵略は、ドイツのそれがナチスの政権強奪によって集中的に行われたのに対して、天皇統治下の「正当」政府によって「適法」行為のかたちでなされ、しかも大日本帝国憲法では国家の全権能が天皇に集中しているにもかかわらず、天皇の「神聖、不可侵」規定をはじめとして統治の責任の所在がぼかされていたことが、共同謀議の成立とその実行についての認識と責任の所在の確認を困難にしました。
弁護人らは、裁判所の管轄権の不存在、戦争という国家行為の非犯罪性とその指導者の個人責任の不存在、条例の事後法的性格等をあげて争いましたが、判決はニュルンベルク判例の判示をあげてこれらの主張を斥けました。近代法として制度が整えられてい国内法の問題ならば、このような主張は当然でしょうが、国際法は、主権国家関係の中での条約、国々、人々が行うことによる慣習が法的確信となって徐々に出来上がってくるのですから、これを国内法の形成と同一に扱うことはできません。その足跡は、大沼教授の著書やジャクソン報告書等でもたどれます。形成過程の中にある国際法についてその未熟性の面を強調するのか、それが生まれ出てくる世界正義の流れを確認し、歴史の進展によってでき上がる法的確信を肯定的に受けとめようとするのかによって、その評価が分かれるのでしょう。国際法関係の裁判に未熟なところや不十分なところがあるとしても、それらは道理による法の一般原則によって補われ、、正義を求める諸国民の努力によって築き上げられるべきものであることは、基本的人権の確立について日本国憲法97条が指示しているのと同じではないでしょうか。
東京裁判が日本国内に及ぼした影響の第一は、国民の侵略戦争の実情について証拠をもって知らされたことです。それは、新憲法の国民主権、平和主義、人権尊重の三大原則の根拠が事実によって裏付けられました。また新憲法の前文は諸国民の平和共存権をうたっていますが、それが実現されるについてのよりどころとなるであろう、日本によって侵略された国と地域の人々が日本に対して抱くであろう心情を理解するための糸口も東京裁判によって与えられました。
しかし、東京裁判について日本国内の評価は必ずしも高くありませんでした。その原因は東京裁判の中にもあったと思われます。日本国民にとって最大の戦争被害であった米軍機による広島、長崎への原子爆弾投下について、東京裁判は触れていませんでした。非戦闘員である市民たちに対する無差別攻撃であり惨害を与えた兵このような器の使用が何故戦争犯罪にならないのか。法の適用に勝者といえども免れることはできないのではないか、という疑問は容易に拭い去ることはできないでしょう。
東京など都市に対する米軍機の無差別じゅうたん爆撃についても同じ琴がいえます。またソ連による中立条約が効力をもっている間の侵攻、捕虜の戦後の長期拘束もそうです。
東京裁判にかけられた被告人以外には、横浜法廷と被占領地の各地の軍事法廷で通例の戦争犯罪についてのいわゆるBC級裁判が行われ、920名の死刑を含む4221名が処罰されています。極東国際軍事裁判所条例は、平和に対する罪と通例戦争犯罪のほかに、人道に対する罪があげられています。この罪に対する本格的な訴追は東京裁判でもほかの戦犯法廷でもなされていません。この点がドイツにおける戦争裁判との大きな相違です。このことによって、植民地統治における殺人等の非人道行為と、戦前、戦中に国内で行われた政治的または人種的理由に基づく迫害行為が見逃されてしまいました。そのこととともに、いわゆるA級裁判も東京裁判の判決をもって打ち切られたことが、日本国民の軍国主義の暴虐政についての認識を深める機会を失わせ、戦争責任について深く思いをいたすことの動機を弱めることの一因となった、と思われます。
2ヶ月間の勉強の成果として、とにかく7千字の報告書にまとめ、英訳をしてもらい、ドイツに出発の用意がととのいました。
▲上へ戻る
10、ニュルンベルク裁判40周年国際会議
(1) 国際会議を前にして
私は、このニュルンベルク裁判40周年国際会議への旅まで、外国旅行の経験は1980年11月に地中海のマルタで行われたIADL第11回大会に出席したことだけでした。その時は日本国際法律家協会代表団の一員であって、同行者は大勢であり、専門の通訳もついていて、全く気楽な旅でした。今度は全く一人旅であり、ドイツ語については、読めない、聴き取れない、話せない、ということで心細い限りでした。成田からデュッセルドルフ空港に着き、ケルンまでは電車で行き、そこからニュルンベルク行きの急行列車に乗り換えるわけです。ケルンで列車に乗るまでいくらか時間がありましたので、名高い大聖堂を見に行きました。それには荷物が重いので駅のコイン・ロッカーに入れたのですが、見学を終えて駅に戻ってみると、そのロッカーの場所がわかなくなりました。探しまわっている間に発車時間が迫り大慌てをし、ようやく探しあてて列車に飛び込むという失敗もありました。ケルンからライン川を左手に見てその岸をさかのぼっていくと車窓から川の流れが大きく曲がるところに大きな岩が車窓から見え、「ローレライ」と日本のカナ文字で書かれた大きな看板がかかげられていました。ドイツでは、日本人がハイネの詩によってここを懐かしいものとしていることが知られていたからでしょう。
ニュルンベルクで夕方たどり着いた駅前の宿は、日本人の旅行団体が行くようなホテル様式ではなく、扉を開けて中に入ると目の前にカウンターがあるという、いわば西洋宿屋でした。宿では、その晩に会うことになっている斉藤さんからの連絡を待っていたのですが、それがなく心細い極みでした。斉藤さんには翌日の朝会議場で会うことができましたが、その日は飛行機の切符が取れなかったとのことでした。
ニュルンベルクでドイツのナチス戦犯法廷が開かれたのは、1927年から38年までここが毎年ナチス党大会の開催地であったからえらばれたのでしょう。国際会議の会場は、マイスタージンガーハレという新しい立派な建物でした。聞いたところによるとニュルンベルク法廷が開かれたのは、もっと古く小さい建物だったそうですが、それが取り壊されてその跡にこの建物が建てられたとのことでした。
会場のまわりは木立のある小公園という風でした。斉藤さんは会場に直接行っているかとも思い早めに出かけました。すると会場の入口附近に若者たちが15人程集まって立ったり腰かけたりしていました。見ると顔写真の貼ってあるプラカード風のものを持っていました。私はそこに書かれてあるドイツ語が読めませんので、この人たちは政治運動か何かで逮捕されたり、弾圧された仲間の救援を会議に3集する人たちに訴えに来たのだろう、と思いましたが、それにしては様子が変で何か鬱屈したような表情をしているのです。私は斉藤さんを探し出して打ち合わせをすることが先決なのでとにかく中に入りました。
中では、マルタ大会で顔見知りとなったIADLドイツ支部のシュテュビューさんを見付けました。彼はこの会議の運営側の一人でしたが、私の顔を見ると、遠い日本からよく来てくれた、と言って大変喜んでくれました。私がここに出席することは、その前に開かれていたIADLの書記局会議があり、そこで斉藤一好さんから私の出席と東京裁判との関連について報告する、と話されていたためでしょうか、会議の演壇のすぐ下に席が用意してくれてありました。会場で配布されたプログラムを見ますと私の発言は2日目になっていました。間もなく斉藤さんと会うことができ、ようやく気持ちが落ち着きました。
▲上へ戻る
(2) 会場内で
出席者は、米、英、仏、ソ連、東・西ドイツ、オーストリア、ベルギー、チェコ、デンマーク、ノルウェー、ポーランド、ユーゴスラビア、伊、蘭等々全ヨーロッパにわたり、大戦中敵味方として戦った国々から多彩な階層の人々が集まっていました。
アジアからはベトナム、パレスチナ、アフリカではアルジェリアなど、200名ほどが出席していました。フランスのフォール元首相からはメッセージを寄せられてきました。私はここに集まった人々の広がりを見聞して、ヨーロッパの大戦中の反ファシズム闘争が国境を越えて強く結ばれていたことを実感しました。またその中で活動した法律家たちが戦後IADLに結集するにあたり、レジスタンス運動が大きな役割を果たしていることがよくわかりました。
会議の討議事項は二つに大別され、はじめは国際軍事裁判所憲章の起源とテヘラン、ヤルタ、ダンバートン・オークス、ポツダム等の会議との関連が論じられ、戦争犯罪の3つの類型についての内容の検討とそれのニュルンベルク裁判への適用が論じられました。ドイツの戦犯裁判ではニュルンベルク法廷のほかに米軍による軍事裁判として12の継続裁判がなされたことを、私はこの討論の中で知りました。その継続裁判の被告人は、ナチス党幹部、軍人のほかに医師、法律家、外交官など官庁関係から、実業家に及んでいました。さらにその後も西ドイツ政府によって時効期間を延伸し、重罪についてその時効を適用せず訴追が続けられていることもわかりました。日本においては、東京裁判をもって終わり、BC級戦犯以外の責任追及がなされなかったのは何故か、それが過去の残滓を根強く残すことになり、旧来の勢力に「逆コース」への道を許し、また国民の間の戦争責任の自覚を弱めることになったのではないか、と考えさせられました。
第2部は、ニュルンベルク裁判が国内法と国際法の発展にどのような影響を与えたかの問題でした。国際軍事裁判所憲章とニュルンベルク裁判判決をベースとする国際法の発展が国連の国際法委員会(ILC)の法整備作業、例えば国際犯罪の成文化、侵略の定義、国家責任、ジェノサイド、差別撤廃などにどのような作用をしたのか、などの問題です。国連がおこなったファシズム、植民地主義、人種差別、アパルトヘイト等への反対決議への反映が論じられました。また人権の国際的発展について、世界人権宣言(1948)、国際人権規約(1966)、あらゆる形態の人種差別撤廃条約(1969)などとこの裁判の関係も論じられました。
しかし、私がこれらの諸問題について論議を十分には理解できなかったというのが本当のところです。何しろ私の国際法についての知識といえば、基地、沖縄問題やレッド・パージ裁判にかかわって必要なところを拾い読みするぐらいでしたから。通読したものといえば上田誠吉さんからお借りした、日本の海軍将校クラブであった水交社の建物が占領中に撤収され、米国の教会関係者の所有になっていたのを講和後に取り戻そうとする裁判が行われた際の記録でした。そこにのせられてあった条約等の公文書と関係論説は一応目を通しておりましたが、田畑茂二郎京都大学法学部教授の鑑定書だけはしっかりと読んでいたつもりです。
発言内容の理解を困難にしたのは何といっても言葉の問題です。私はイヤホーンからの英語を少しでも聞き取ろう、と努めました。隣にいた斉藤さんは発言内容をメモにして渡してくれます。それを見た私が自分の理解にしたがって斉藤さんに説明を求めるという具合で、その繰り返しですから大変くたびれましたが、要点はとにかくつかんだつもりです。
私の発言は、用意した報告を縮めたものでした。私は英語の発音には全く自信がありませんので、斉藤さんと2人で壇上にあがって斉藤さんに代読してもらうという提案をしたところ、やはり本人が言うべきだというので自分で読み上げましたが、果たしてどれだけ理解されたことでしょうか。
英文の発言要旨は会議事務局に渡しておきました。この会議みら記録はドイツ文でまとめられ、後日私のところにも送られてきましたが、関係方面に配布されていたようでした。東京では、かねてから法学者、歴史学者、ジャーナリストなどの人々が集まって「東京裁判」研究会がもたれておりました。この研究会から招かれてこの国際会議の出席者としてその模様を報告したことがありました。その席上に、この発言記録に載せられていた私の発言要旨を日本語訳したものが配布されました。それを見ますと私の原文とは変わっているところが大分ありました。日本語、英語、ドイツ語、さらに日本語と翻訳が重ねられたことの結果でしょう。「翻訳は原文から」といわれていることの意味が、この自分の経験からしてよくわかりました。余談ですけれども。
会議初日ノーマン・ピーチ教授が西ドイツ政府のニュルンベルク裁判に対する態度についての発言があり、この裁判が示した法の原則がその後の国内の裁判で十分生かされていないという意見でした。それに通じているものであるとして、当局側はこの会場の前でネオ・ナチのデモを許したという批判をしました。私はこれを聞いて会場の前でさきほど見た青年たちがネオ・ナチで、この会議に反対するデモンストレーションであったことがわかりました。もし、日本でこの会議と同じような東京裁判40周年国際会議が開かれるとすればどうなるでしょうか。おそらく右翼の街頭宣伝車が3集し、そのスピーカーががなり立て周囲は騒然とした空気になったでしょう。そして会場の所有者は、その騒音を理由にして会場の使用を断ってくることもありましょう。この会場の前のネオ・ナチの青年たちは黙って座っているだけで、むしろおずおずしているように見えた様子は、日本の右翼が大威張りで傍若無人といった宣伝をするのとは大違いです。
西ドイツ基本法にはナチス体験による、そのような言動を積極的に抑えていく「戦う民主主義」条項(9条2項、21条2項、18条)がありますが、日本国憲法には軍国主義に対する特別条項がないことによる、という法の上の相違ばかりではなく、同じく「反共」国家といわれていますが、西ドイツと日本の間には、政府と国民の中への反ナチズムと反軍国主義の浸透度に大きな差異があることが実感させられました。
この差が、ニュルンベルク裁判の判決が下されその執行がなされ、米軍による12の継続裁判が終わっても、西ドイツ政府が戦争犯罪人に対して時効を停止し、さらに時効の適用を廃止して、その責任追及の裁判をその後も続けさせたことの原因でしょう。また国外、国内の戦争被害者に対する補償について、西ドイツ政府は国民の中の被害を受けなかった者から財産の拠出を求めて戦争被害者にできるだけの補償をして戦争の被害の痛みを国民の間に分かち合ったことも、ここが出発点でしょう。これに対して、日本の戦後補償は、国内では軍官関係者に偏っていました。国外への償いでは米国が日本を1日も早く西側の有力な一員に育成するために被害国の要求を抑え、国家間賠償は「値切られた」賠償となっていました。これらが、日本の戦争責任の自覚を弱めることになり、戦争の遺物を戦後も数多く残すことになりました。その結果として「経済大国」日本となっても周辺の国との間に友好感情が生まれず、かえって絶えず疑いの目と警戒心をもってむかえられていることになりました。
このような状態は、日本政府が戦争に対する反省から生まれたはずの日本国憲法の諸条項の実施を怠ってきたことによるものであり、これに対する責任の追及がなされなければなりません。しかし国民自身も憲法制定権者としてこれらの問題についてどれだけの自覚をし、その責任を果たしてきたかと自問してみますと、内心忸怩たるものがありました。これを東京裁判についていえば、国民の間にその内容をもっと広く知らせ、その意義を深く理解してもらって、いわゆる「東京裁判史観」批判を克服していくことです。この会議に参加してみてドイツの様子を知り、私たち法律家、否何もしてこなかった私の懈怠、責任を痛く感じさせられました。
会議の最後に、米国代表のラムゼイ・クラーク元司法長官とリチャード・フォーク、プリンストン大学国際法学教授の2人から、核時代における法律家の任務として、ニュルンベルク原則の公正かつ厳格な適用を確保するため国際社会における法的な枠組みの樹立を追及することを約束する「ニュルンベルクの誓い」をしようとの提案がありました。会議出席者がこれに署名して確認をし、世界の各界の人々に配布し、その署名を呼びかける、という決議がなされました。
私がこの会議に出席して受け取ったものは、世界から戦争をなくしていく上での戦争責任の確認と戦争犯罪類型の定立とその実現方式としての裁判手続の確立を、日本の中でどのように進展させるべきかを考えてみる、という課題でした。具体的には、この作業を東京裁判について行う、ということです。発言者の論旨を聞いていく中でそのための仕事の輪郭はおおよそつかめてきたように感じました。それよりも東京裁判について何がわかっていないか、がわかってきたこと、それをどこから取りかかっていったらよいかの見当がついたことが1番の収穫であったか、と思います。そのために会場で売られていたニュルンベルク裁判記録を1揃いを買い求めて手荷物として持ち帰りましたが、しかし未だに読めていないのは我ながら情けない次第です。
▲上へ戻る
11、ヴァイツゼッカーのドイツと中曽根の日本
ドイツの敗戦40周年にあたるこの年の5月8日に西ドイツのヴァイツゼッカー大統領は連邦議会でドイツの終戦についての演説を行い内外の人々の大きな感動を呼び起こしました。私は、ニュルンベルクから帰ってきてから、このことを知り、その演説が雑誌「世界」の11月号に「40年目の5月8日に─過去に目を閉ざす者は現在に盲目となる」という表題で掲載されていることを聞き、買い求めました。後に「荒れ野の40年」という題名で岩波ブックレット・シリーズの中の1冊になりました。その中に「1945年5月8日がドイツ史の誤った流れの終点であり、ここによりよい未来への希望の芽がかくされていたとみなす理由は充分であります。5月8日は心に刻むための日であります。心に刻むというのは、ある出来事が自らの内面の一部となるよう、これを誠実かつ純粋に思い浮かべることであります。とりわけ誠実さが必要とされます。」という1節があります。私たち日本国民にとっては8月15日がその日です。さらに「罪の有無、老弱を問わず、われわれ全員が過去を引き受けなければなりません。われわれ全員が過去からの帰結に関わり合っており、過去に対する責任を負わされているのであります。・・・・・・・・・問題は過去を克服することではありません。後になって過去を変えたり、起こらなかったことにするわけにはまいりません。しかし過去に目を閉ざす者は現在にも盲目となります。非人間的な行為に心を刻もうとしなかった者は、またそうした危険に陥りやすいのです。」と演説は続きます。日本の首相で、8月15日をこのように位置づけた人はいませんでした。終戦の日にあたって過去の歴史を「心に刻」んで、それを「よりよい未来」への出発点にしようと国民に訴える演説をした、あるいはできる首相が日本の戦後に一人も出てこなかったことを国民の一人としてまことに口惜しく思いました。 一方日本では、敗戦を仕方のなかったものとするのはまだよいほうで、歴史の逆行が冷戦の下に行われてきました。
東京裁判はその審理が始められて間もなく始まった東西冷戦の影響を強く受けていることを指摘しなければなりません。これにより戦争犯罪容疑で収監されていた戦争中の指導者の多くが裁判を受けることなく釈放され、政界に復帰しました。
47年には戦犯容疑者24人、48年には岸信介ら17人が釈放され、東京裁判で有罪となり無期懲役などで服役し生きていた18人全員も50年代には全部釈放され、この間に公職を追放されていた人々は解除となりその後の政界で活躍する重光葵、賀屋興宣、鳩山一郎などその中にいます。首相となった岸信介によって安保条約の改定が行われたことは既に述べました。日本の再軍備は憲法9条の解釈改憲という迂回路をとおって進められました。
中曽根首相は84年1月5日現職首相として戦後初めて靖国神社に公式参拝を行いました。靖国神社は1879(明治12)年に戦争で死亡した人々を神として祀る国家の施設として設置され運営されてきましたが、戦後は宗教法人となりました。この神社に、1978年10月、東京裁判で戦争犯罪人として、死刑に処せられた東條英機元首相ら7名を含む有罪宣告を受けた者で死没した14名が、神社と政府の協力によって合祀されました。そのことが翌年4月に表沙汰になることによって問題化しました。この合祀は憲法20条の政教分離に違反するばかりか、それまでは合祀されたことのない軍人以外の文官が含まれていることが問題を一層複雑なものにしました。軍人死没者を祀る慰霊施設であった筈の靖国神社が、戦争の遂行、指導、政治的行為故に責任を問われ死亡した「犠牲」者を神として崇めることによって、その性格を変えることになったからです。それは15年戦争の指導者たちとその公道を国家が肯定し崇敬することになり、それによって東京裁判をはじめとする連合国が進めた戦後処置に対する反対意思を表明することになり、戦後の世界秩序と国際法への挑戦になるからです。
この合祀が明らかになってから、天皇は靖国神社参拝を止めてしまいました。天皇は、1946年1月1日に、自らその「神格」を否定する人間宣言を発し、また47年9月22日にはマッカーサー元帥に対して米軍の占領を継続することを希望する旨のメッセージを送るなどをすることによって、国体護持しえたものと考えていたのでしょう。天皇はこのような自らの努力によってなしとげたと思われる天皇制の継続を水泡に帰させるおそれのあるA級戦犯合祀という「心なき」「臣下」のはからいに対する「声にはしない抗議」の表明として、靖国神社参拝を止めてしまったのでしょう。そのことが、最近複数の天皇の側近の口からもらされることによって明らかになりました。
中曽根首相は、84年1月の年頭参拝につづいて、翌85年には終戦記念日である8月15日に靖国神社にその閣僚ともども公式参拝をしました。これに対して野党、市民団体からは抗議がなされました。首相が政府の代表として終戦の日にA級戦争犯罪人を神として祀る靖国神社に参拝することは、東京裁判否定をあからさまにすることであり、日本の侵略戦争を正当視することになりますから、この戦争によって甚大な被害を受けた国々からは「アジアの心を傷つける」ものと厳しい非難がなされました。中曽根首相の靖国参拝は、日本の中では再軍備の強化ばかりでなく、心の「復元」が進んできていることを示したものです。これらの出来事は私のニュルンベルク行きの決意の大きな動機となりました。
この中曽根公式参拝に対する国際的批判の大きさに驚いた政府は、それ以降首相の靖国参拝を取り止め、小泉純一郎首相が2001年8月13日に公式参拝するまでは、日本遺族会長であった橋本龍太郎首相が96年7月に参拝したことを除いて、絶えてありませんでした。
しかし、中曽根首相が靖国神社参拝を取り止めたことは、日本の政権の座にあった人たちがこのような国際的批判によって過去の戦争についての歴史認識をあらためたものではなく、東京裁判の判定を心底から承認したものでもありません。靖国神社参拝中止は外交政策上の政治的な措置でありました。そのことは、中曽根内閣が86年4月29日に昭和天皇在位60年式典を行うことにより、日本国憲法の象徴天皇と大日本帝国憲法の絶対的天皇との「同一化」をはかったことにあらわれています。また藤尾正行文部大臣が雑誌「文藝春秋」の86年10月号への寄稿文の中で、日韓併合は文書形式上も実質的にも日韓両国政府間の合意で成立したものであり、その結果について韓国側にもいくらかの責任がある。もし日韓併合がなかったら、清国やロシアが朝鮮半島に手をつけなかったという保証があるのか、と主張したことでも示されています。これは日韓併合の経緯についての事実の歪曲であり、軍事力による併合強制の「正当化」でありました。これらが中曽根首相とそれを引き継いだ人たちの本心でしょう。
ニュルンベルクから帰った私は、ヴァイツゼッカーを読んで、その演説の結びとして世界の人々に呼びかけている次の言葉が、会議が採択した「ニュルンベルクの誓い」と一致していることに気付きました。これによって「ニュルンベルクの誓い」を日本で実行することにあたっては、心のあり方を教示されました。
「たがいに敵対するのでなく、たがいに手をとり合って生きていくことを若い人たちに学んでいただきたい。民主的に選ばれたわれわれ政治家にこのことを肝に銘じさせてくれる諸君であってほしい。そして範を示してほしい。
自由を尊重しよう。
平和のために尽力しよう。
法を遵守しよう。
正義については内面の規範に従おう。
今日5月8日(日本国民にとっては8月15日)にさいし、能うかぎりの真実を直視しよう。」
▲上へ戻る
12 東京裁判と戦争責任を考える連続シンポジウム
(1) 企画と目標
帰国して直ぐ、11月30日に日本国際法律家協会の第8回総会が開かれました。そこで私はニュルンベルク裁判40周年国際会議についての報告をしました。協会のこの年の活動方針討論の中で「ニュルンベルクの誓い」の問題が取り上げられました。86年が東京裁判開始40周年にあたるので、この年に行われた「核時代と法律家」シンポジウムの成果とあわせて、東京裁判の再検討をし「戦争と戦争責任」について法律家として考えていくための企画をたてることの決定がされました。その後の理事会での討議の結果、この活動方針の具体化として、「東京裁判と戦争責任を考える連続シンポジウム」を実施することが決まりました。
そういうことになれば私もそれを実行する他tばにおかれますが、東京裁判につい私は知らないことばかりでしたので、「極東国際軍事裁判速記録」(10巻)をはじめ東京裁判に関する本などを買い集め、それらを読むことから仕事を始めました。
86年4月18日に、このシンポジウムの実行委員会が結成されました。この結成については国際法律家協会の会員の外にも広く呼び掛けましたので、法律家以外に若手の学者、中国帰還者、一般市民などが集まり、本屋さんもこれに参加しました。その中での討議の結果、そこで取り上げるテーマを決め、それぞれについて詳しい専門の方を招いて講義をしていただき、3集者がそれについて質疑、討論をするというかたちの集まりとすることにしました。この実行委員会の事務運営の責任者として内藤雅義さんと私があたることになりました。
実行委員会で取り上げようとした項目と議論された問題点については、その際に作成されたメモがあります。それによってシンポジウムの中味がわかると思いますのでここに再録しておきます。
東京裁判再検討のためのメモ
(1) 軍国主義に対する日本政府の態度とナチズムに対する西ドイツ政府の態度
ア) 西ドイツ、ヴァイツゼッカー大統領のドイツ敗戦40周年国会演説。
イ) 西ドイツにおける戦争犯罪人に対する訴追の続行、時効の不適用。
ウ) 内閣総理大臣の靖国神社公式参拝。
エ) 教科書検定における侵略の否定。
オ) 天皇在位60周年キャンペーン。
(2) ニュルンベルク原則=戦争犯罪と戦争責任についての到達点
ア) 平和に対する罪。
侵略戦争は違法であるのみならず、国際法上の犯罪である。
イ) 侵略戦争の計画、謀議、準備、実行者は国家の機関として関与した場合でも、それからの受命者であっても、元首をはじめとして個人責任を問われる。国内法上の合法性からは国際法上の犯罪責任は免除されない。
ウ) 人道に対する罪。
戦前、戦時中の民間人に対してなされた殺人、追放等の行為、政治的、人種的、宗教的理由による迫害国内法違反であるか否かを問わず処罰せられる。
エ) 通例の戦争犯罪。
ハーグ陸戦条約などの戦争の法規または慣例の違反に対する処罰。侵犯者に対する国際軍事裁判所を設置できる。
オ) 犯罪集団、組織の宣言。
その所属者が裁判にかけられた場合その集団、組織の犯罪性は争えない。被告人は加入していないこと、強制された加入を証明してのみ処罰を免れる。
(3) ニュルンベルクと東京の二つの国際軍事裁判に対する批判
1、実体法的観点
a 侵略認定の根拠の不明確性。国連決議「侵略の定義」は条約として未成立。
b ある戦争に侵略性ありと判定する基準は不明確であり、それを違法とまではいいえない。違法であるとしても犯罪ということはできない。
c 国家の機関としての行為者、下級受命者に対し個人責任を問うことは根拠がない。
d 平和に対する罪、人道に反する罪は事後立法であり、それによる処罰は法律不遡及の原則、罪刑法定主義に反する。
e 共同謀議は英米法的概念にすぎず、国際的には法的確信になっていない。また責任の範囲を徒らに拡大する。
2、手続的観点
a 国際軍事裁判所の設置は国際法上の根拠を欠く。設置される裁判所の管轄権の不存在。
b 戦勝国が訴追し、戦勝国民裁判官が裁判することは公正ではない。「勝者の裁判」。
c 戦勝国の戦争犯罪(原爆投下、無差別都市爆撃等)を不問に伏すことは公正ではない。
d 証拠法原則の排除、証拠の採否、予審の欠如、公用言語、翻訳、弁護人の選定等裁判手続における公正が欠けていた。
3、政治的観点
a 戦勝者の敗者に対する懲罰的な軍事的、政治的処分であって裁判の名に値しない。
b 二つの国際軍事裁判はその後の侵略と戦争を防止しえていない。
c 敗者となって裁かれないために、かえって軍備拡大が促進される。
d この裁判の訴追・裁判国側のその後の侵略は裁かれていない。
e 東京裁判の「正義」の肯定は米国のベトナム介入を合法化した。
(4) 東京裁判の特徴
1、条例の面から
a 連合国最高司令官(事実上米国)が制定した。
b ニュルンベルク条例にある元首の責任の明文がない。
c 訴追権限は主席検察官(米国人を任命)にある。他の国出身検察官は補助的地位。
d 犯罪団体の宣言がない。
2、訴追、審理、判定の面から
a 平和に対する罪についての共同謀議期間が長く(1928から1945年)、謀議の具体的特定が弱い。
b 右の①との関連からか、ニュルンベルク裁判になかった戦争による殺人を訴因に加えている(判決はこの訴因について特に判断していない)。
c 天皇の不起訴と天皇の責任に触れる発言に対する検察側からそれを除外する工作があった。
d 財閥関係者の不起訴。
e 弁護人として米国人も参加した。
f 通例の戦争犯罪について不作為責任を問うている。
g 判決に多くの少数意見がついた。
3、政治の面から
a 米国の政策に従属する面が強い(右1の③、2の③、④、後記②)。
b 東京法廷以外にA級裁判が行われず、多くの戦犯容疑者はその責任を問われず釈放された。 c 日本国民の関与が弱かった。
(5) 二つの国際軍事裁判の影響
ア) 国連総会におけるニュルンベルク原則の国際法としての確認決議。
イ) 国連における「侵略の定義」決議採択と国際法委員会における戦争裁判法定立への努力。
ウ) 戦後における人権保護諸条約の成立。
エ) ジェノサイド禁止条約の成立。
オ) 戦争犯罪人に対する時効不適用条約の成立(日本は未加入)。
カ) ベトナム戦争等における侵略行為の弾劾、アパルトヘイト非難の法的根拠となった。
(6) 今後の課題
ア) ニュルンベルク原則の世界史における積極的意義を明らかにし、国際法として各国政府がそれを遵守すべきことを各国人民運動として要求する。
イ) 二つの国際軍事裁判の影響のもとに成立した人権保障条約の意義を国民と共に明らかにし、日本政府に加入を要求する。
ウ) 二つの裁判が持っていた弱点についても解明し、その補強について立法運動を含めて考える。特に、民族解放運動の法理との関係、国連機構との関連など。
エ) 東京裁判の研究
a 侵略行為についての計画、謀議、準備、実行はどのようなものであるか等の事実の究明をさらに進め、より明確にする。
b 戦前、戦中の日本の侵略行為について天皇をはじめとする当局者の関与を事実上及び法律上明らかにし、その責任を国際法、国内法の観点から、また刑法、賠償法の観点から考える。
c 戦後の天皇、日本政府当局者の言動を右の①、②との関連で考察する。
オ) 戦争を再び起こさせないために
a 15年戦争が起こされ、遂行される中で、国民として何が出来たのか、何をなさなければならなかったのか、あるいは何をしてはならなかったのかを反省し、戦争、敗戦に至った政治的、道義的責任を考える。また今の情勢の中でその教訓を考える。
b ナチズムについて西ドイツ国民がどのように考え、対処しているかを調査研究する。
c 日本軍国主義が日本国民及び被侵略国民に与えた害悪の実情及びそれに対する日本政府の態度及び被害回復について東京裁判の法理から考える。
d 国際法の規定上の不備、実行上の不足を人民の連帯運動によって補強し、効果あらしめるための方策の探求。
このメモにより、東京裁判の問題点と参加者の関心のありかがわかります。
▲上へ戻る
(2) 討議の内容
シンポジウムの第1回は同年6月7日に開かれ、東京裁判の概要とその歴史的意義については、粟屋健太郎立教大学教授にお願いし、その法律的意義と問題点については、国際法学者でり、協会の副会長であった宮崎繁樹明治大学教授が話されました。この日の話はいわば序論にあたり、このシンポジウムの展望を示すものでした。参加者の中には、青山学院大学で国際法を教授されている佐藤さんという方がおられ、東京裁判批判の立場から発言されました。それが講師の話とかみ合うかたちになり、東京裁判の論点の所在が一層よくわかったと思われます。
次の集まりは、大沼保昭東京大学教授をお招きして、戦争犯罪、ことに平和に対する罪の内容とその成立の歴史について話していただきました。教授は、私が感銘を受けた「戦争責任論序説」の著者ですが、同じ内容でも本人の口からの言葉として聞くのと本を読むのとでは別の良さがあることがよくわかりました。
次いでの集まりには、広瀬善男明治学院大学教授には、国内・国外の戦争被害について国家責任の発生とその補償の法理と現実について話していただきました。 これまではいずれも法の面からの接近でしたので、その次回は転じて「戦争報道とジャーナリズムのあり方」について戦争報道の実状とその責任の問題が取り上げられました。問題をさらに国民の側に移して、中国で捕虜虐殺の戦争犯罪容疑者として囚われ、中国側から獄中教育を受けて不起訴処分で帰国された富永正3さんからその体験談をうかがいました。これらによって戦争責任の問題がより身近なものになりました。
その後靖国神社問題を取り上げたのは、戦争について、何らかの責任を負い、しかも自らはその中で死没した人たちについてどのように考えるべきか、また国家がその人たちをどのように位置づけてきたのかをできるだけ客観的に評価してみようとする企画でした。
さらに戦争とその被害をできるだけ客観的にそして人間として考えるために、また日本の戦争の侵略性を確認するためにアジアの民衆から見た「大東亜戦争」がテーマに選ばれました。
ここまでくれば、この戦争によって、彼の軍隊によって、アジアの人々が殺傷され、日本国民も生命と財産が失われていった天皇の政治的倫理的責任を問いあらためざるをえませんでした。天皇は法的には国内法上は無答責とされていましたが、そのもつ権力の絶対性はかえって天皇の国際法上の責任を重からしめる理由が明らかにされ、またその政治的倫理的責任も考えなければなりませんでした。天皇の戦争責任については、従軍兵士のあり方と戦場の実状に詳しい藤原彰一橋大学教授に解明をしていただきました。
天皇の責任問題として、権力の内側からも退位論がささやかれていました。それにもかかわらず戦後も象徴天皇として残された経緯とその政治的意味については、なお天皇が少なからぬ影響をもっていることから、戦後における天皇の位置と言動を確かめておく必要があります。この問題を東京裁判を通して考察する集まりを別にもちました。
この二つの天皇制に関するシンポジウムの間に、新倉修國學院大学助教授が共同謀議論を中心として、東京裁判と国際刑事法について話される集まりが入りました。共謀謀議は英米法以外の刑法論ではその法的確信の程度がなお疑われており、実態としても日本の指導者の間の長期にわたる関係でそれが成り立つものであるか疑いの声が多かったからです。
以上の10回にわたったシンポジウムの最後として88年10月6日に、名古屋大学の国際法教授であり、協会の理事である松井芳郎さんから「民衆の平和のための武器としての国際法─ニュルンベルク原則の発展とその今日的意義」についての報告と問題提起がありました。これはニュルンベルク原則が世界と日本に適用されていることの現状分析とニュルンベルク国際会議が採択した「誓い」の実行について述べられたものでした。
そしてこの連続シンポジウムの総括として89年3月25日に、日本国民の戦争責任と戦後責任について、研究者、ジャーナリスト、宗教者、旧軍人、教育者、法律家など各界からの参加者が自らの立場から陳述する最終集会がもたれました。この日は100名ぐらいが参加していたと思いますが、そのほかの日は30名から50名位であったと思います。
▲上へ戻る
(3) 成果と課題
こうしてこの連続シンポジウムに参加された方々は、日頃の活動や関心に応じてそれぞれの成果を持ち帰られて、その後の活動に生かされたことと思います。私の場合は、例えば日本弁護士連合会で取り組まれていた原爆被爆者問題調査や戦争被害補償調査で役立てることができました。
日本の戦後処置の欠陥、不備とドイツに比べての立ち遅れが、日本の平和と安全の確立にとって、現在でもどれほど多くの障害となっているかは、心ある人たちが常に感じておられるところであろうと思います。このシンポジウムで取り上げた問題は現在もなお生命をもっているわけです。話をしていただいた方々は、それぞれのテーマについての第一人者とみなされていた方々で、その知見と問題意識を参加者に伝えて下さいました。その内容が公刊され、広く国民に伝えられたとしたならば、このシンポジウムの意義はさらに大きなものとなっていたでしょう。 今なお心残りになっていることは、このシンポジウムで話されたこと、討議されたこと、また提出した資料をまとめて本にしておかなかったことです。その計画はあったのですが色々と手違いがあって実現しませんでした。つまりは私の怠慢に帰することであり、残念に思っており、責任を感じております。
この小文のまとめとして、この連続シンポジウム実行委員会が、最終集会への参加の呼びかけとして起草した文書の一部を援用しておきます。その後一連の家永教科書裁判での証言、判決によって政府による歴史教育の歪曲が明らかにされ、また95年8月15日の終戦50周年にあたっては、村山富市首相の談話によって日本の植民地支配と侵略によってアジア諸国をはじめ多くの国々とその国民に損害と苦痛を与えたことの過ちの確認とそれに対するお詫びが表明されました。それにもかかわらず、今なお少なからぬ政治家等の口から「妄言」がなお後を絶えません。また内外の戦争被害者に対して、相当な償いがなおなされていないのが現状です。
ニュルンベルク裁判の主任検察官であったジャクソンがその報告書の中で、国際軍事裁判所憲章を制定し、これに基づいて戦争犯罪人を裁くことによって、今後はこの制定者側もこれによって裁かれることになるのだ、と言明している部分は、米国の中にある理想主義の現れとして私は評価しました。米国民にも自国の代表が確信をもって述べたこのことをしっかりと記憶にとどめておかれることを期待されるものがありました。しかしその後の米国が関係した諸々の事件について、また国際刑事裁判所問題でもそうはなっていないことが残念です。
これらの反省として、このシンポジウムのまとめを再録しますが、それが今なおその意味を失っていなものと考えられますのを、残念なことに思います。
「東京裁判は日本の行動を侵略と判定しました。日本国民もまた第2次大戦にいたった経験に学び、その反省の上にたって日本国憲法を制定しました。憲法前文は政府の行為によって戦争が起こされたことを確認し、私たちの安全と生存とを平和を愛する諸国民の公正と信義に依拠する決意を明らかにしています。また国連憲章とその後の国際法の発展に即して平和を守ることを約束しています。日本国民にこの反省と決意を条文のかたちにのみとどまらせず、その決意を具体化し、実現していく姿勢があったならば東京裁判に対して傍観者ではあり得ず、国民の立場からする戦争責任者に対する裁判その他の追及が行われたでしょう。事実はそれが行われませんでした。戦争は国民の反対が強く、不協力であったならば行われなかったでしょう。日本に軍国主義がはびこるについては国民の側にも無関心、容認、追随、あるいは協力があったとみなければなりません。広島・長崎の被爆者は国民でしたが、南京で、シンガポールで直接手を下したのも普通の国民でした。軍需生産により戦争の遂行を助けたのも国民です。侵略に身を挺して反対した者以外、その地位、行為に応じて道義的責任を負わなければならないと思います。
責任は自由にともないます。戦時中は国民の多くにとって判断の自由も、言論・行動の選択の余地も乏しいものでした。国民の耳目をふさぎ、消極、積極の抵抗を弾圧し、戦時体制をつくった、戦争促進者の責任は重大です。しかし、自由は一挙に失われたものではありません。そこにいたる経過において国民の側で可能な限りの努力をしたかどうか具体的事実に即して検討されなければなりません。この認識と自覚のなかから戦争の促進者に対する怒りと責任追及の力がわいてくるでしょう。また、この反省とそれにたつ償いの行動によって戦争推進者を裁く者の立場にたつことができるし、国の内外の戦争犠牲者と悲しみを共にすることができます。被害地域民との平和と繁栄のための連帯ができるのです。そして、再び戦争と侵略を行わない日本をつくりあげることができましょう。ニュルンベルク原則はそのための判断の基準であります。これに依拠することにより自由を奪ったものたちの行為を厳正に評価することができ、その責任を追及することができます。日本国民は占領政策がポツダム宣言の線からそれていったことにより、また、それを推進すべき国内の主体的力量の不足から裁判その他によって指導者たちの戦争責任をより一層明らかにすることができませんでした。このことについては国民の側の意識にも問題があり、軍国主義の影響力と大国意識の余影が残されていたと思います。軍国主義の清算は不徹底に終り、残された戦時中の指導者とその承継者たちは戦後間もなく生じた国際民主戦線の分裂に乗じて、新憲法の下においても日本の政治を主導してきました。日本の現状はその延長のうえにあります。日本の復興は残された古い根に米国の冷戦政策が継木されて出発しました。その後の高度成長のなかで、この部分もまた強化されているとの疑をぬぐいさることは出来ません。この点も東京裁判の基準と判断に照らし点検する必要があります。社会的退廃は肉体の病気と同じではありませんが、社会的癌細胞が一時的な見せかけの繁栄とともに大きくなりやがては全体的な破滅に至らせることはナチスによる景気振興策の結果が示しています。戦後の日本では軍国主義の遺産を富と力の拠り所としているものがあり、現在の日本がこの上に「繁栄」しているだけにその存在を見定め、これを抑え、摘出するには困難がともないます。病の再発による被害を受けるのも、また、この禍根を絶つのも主として戦後に生まれた人たちです。軍国主義下に生きた者は、その痛みと苦しみを後に続くものに伝えていく責任がありましょう。また、自らの体験にてらして現在の状勢について診断し、それを皆に告げることができましょう。」
最後に私事にわたることですが、私は治安維持法と普通選挙法が制定された直後に生まれその余生はいくばくもありません。東京裁判とその対象になった事実についてなお学ぶべきこと、なすべきことが沢山あります。一方、憲法「改正」問題など直ちにに取り組まなければならない事案に追われ、東京裁判についての自らの上の課題を果たしえていない状態です。この有様は非才の身にとってやむをえないという弁解でしが果たして許されますでしょうか。心ある若い人々に後事を託すという心境で、私の手元に集まった東京裁判関係の資料はすべて川崎市の平和館に寄贈しました。それらを詮索すればもう少しましなものが出来たともと思われますが、時間に追われてそれも出来なかったので、この小文も蕪雑なものとなってしまいましたが宥恕をお願いいたします。
投稿者
最近のブログ記事
- いよいよ山場を迎える 台風19号多摩川水害訴訟 (弁護士 西村隆雄)
- 2/25(水)所内行事のため 16時30分に閉所します
- かわさき市民オンブズマンによる川崎市議会議員海外視察住民訴訟(弁護士 小林展大)
- 2026年劈頭にあたり 新年のご挨拶を申し上げます
- 畑福生弁護士が小田原市立下曽我小学校ホームページに掲載されました
- 不動産問題専門サイトを開設しました!
- 自衛隊配備が進む先島諸島─様々な不安と隣り合わせの住民生活を現地レポート(弁護士 前田ちひろ)
- 過労事故死事件解決の先の約束の書「睡眠科学・医学・労働法学から考え直す日本の労働時間規制」(日本評論社)を出版しました(弁護士 川岸卓哉)
- 2024年総選挙の結果生まれた国政革新のチャンスを大きく広げよう(弁護士 藤田温久)
- 篠原義仁弁護士を偲ぶ会 ~「挑戦と闘い」の軌跡 そして絆~ のご報告(弁護士 川口彩子)
月別アーカイブ
- 2026年2月 (3)
- 2026年1月 (1)
- 2025年9月 (1)
- 2025年5月 (1)
- 2025年4月 (6)
- 2025年2月 (1)
- 2025年1月 (1)
- 2024年12月 (3)
- 2024年11月 (1)
- 2024年9月 (1)
- 2024年4月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年7月 (1)
- 2023年6月 (2)
- 2023年5月 (2)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (1)
- 2023年1月 (1)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (3)
- 2022年10月 (1)
- 2022年8月 (1)
- 2022年7月 (1)
- 2022年3月 (1)
- 2022年1月 (2)
- 2021年12月 (2)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (1)
- 2021年7月 (2)
- 2021年6月 (1)
- 2021年5月 (1)
- 2021年4月 (2)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (1)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (2)
- 2020年8月 (1)
- 2020年7月 (3)
- 2020年6月 (2)
- 2020年4月 (6)
- 2020年3月 (1)
- 2020年2月 (3)
- 2020年1月 (5)
- 2019年12月 (2)
- 2019年11月 (4)
- 2019年10月 (2)
- 2019年8月 (1)
- 2019年7月 (3)
- 2019年6月 (1)
- 2019年5月 (1)
- 2019年2月 (1)
- 2019年1月 (2)
- 2018年11月 (2)
- 2018年9月 (2)
- 2018年8月 (4)
- 2018年7月 (3)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (3)
- 2018年4月 (1)
- 2018年3月 (2)
- 2018年2月 (1)
- 2018年1月 (3)
- 2017年10月 (4)
- 2017年9月 (4)
- 2017年6月 (1)
- 2017年5月 (1)
- 2017年3月 (1)
- 2017年2月 (2)
- 2016年12月 (1)
- 2016年10月 (2)
- 2016年8月 (76)