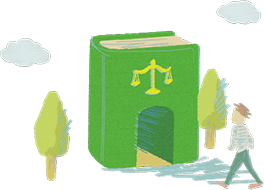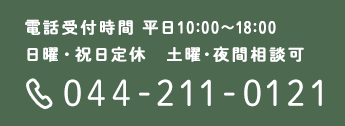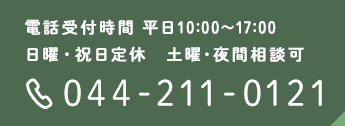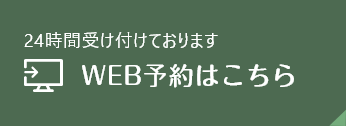トピックス
労働者追い出しに加担するブラック産業医 客観性、中立性を担保する制度導入を(弁護士 川岸卓哉)
2019年5月7日 火曜日
パワハラや過重労働によるメンタル疾患によって休職を余儀なくされる従業員は近年、増加の一途を辿っている。メンタルヘルス問題への対応が、社会的にも重要な課題となっている。
2015年12月より企業で労働者に対するストレスチェック制度が始まり、強いストレスを抱えた労働者の面談指導に関与することなど産業医の果たす役割が重要性を増している。
しかしその職責を裏切り、企業のクビ切りに露骨に加担する「ブラック産業医」の問題がクローズアップされている。
1 ブラック産業医問題とは
産業医の重要な仕事の1つに、職場復帰の支援がある。休職した従業員の復職可否の判断に当たっては産業医の判断が重視されているが、従業員の復職を認めず、休職期間満了で退職に追い込む「クビ切りビジネス」に手を染める産業医も存在する。すなわち、メンタル疾患に罹患する労働者の増加に伴い、産業医に期待される客観的・中立的・専門的立場に反し、専ら会社に迎合して労働者を退職に追い込む「ブラック産業医」が増加している。この問題について、実例とともに厚生労働省申し入れ、その後の法改正について報告する。
2 産業医によって2人が退職に追い込まれた神奈川SR事件
復職不可の産業医意見を正面から争った事件として、神奈川SR経営労務センター(以下「SR」という)事件をめぐる裁判がある。
SRの職員だったAさんは、職場のパワハラやいじめに悩まされ、うつ症状を発症。2014年5月に休業に入った。その後体調が回復したので、復職を可能とする主治医の診断書を添えて復職を申し出たが、SRは復職を認めなかった。産業医がAさんの復職を否とする意見書を出したからであった。Aさんは2015年6月、休職期間満了で退職扱いにされた。
産業医はAさんと30分ほどの復職面談を1回しただけであった。主治医に対して問い合わせをすることは一度もなく、心理検査もしないで「統合失調症」「混合性人格障害」など、Aさんがこれまで一度も受けたことのない病名をつけて復職不能の進言をした。
同じくSRの職員であるBさんも、この産業医の「復職不可」判断によって2015年、SRから退職させられた。AさんとBさんがSRを相手に提起した地位確認請求訴訟は、一審横浜地裁、二審東京高裁ともAさんBさんが勝訴し、復職が認められた。裁判では、産業医の意見の信用性は完全に否定された(現在、SRが最高裁に上告中)。
その後、AさんとBさんはさらに2018年12月、産業医及びSRに対し①違法な復職妨害②「人格障害」「統合失調症」「自閉症スペクトラム障害」という根拠のない病名を付されたことなどによる名誉棄損に基づく損害賠償を求めて提訴。「ブラック産業医」問題の責任の追及を続けている。
3 ブラック産業医が生まれる温床と厚生労働省申し入れ
医師にとって産業医への参入障壁は低い。医師であれば専門分野を問われず、わずかな時間の講習を受けるだけで産業医の認定を受けることができるからである。
大企業では専属産業医の選任が義務付けられている。しかし専属産業医を選任する義務のない中小企業では、嘱託産業医が多数の企業を掛け持ちすることによって、手軽に高額の報酬を受けることもできる。
産業医の職務については客観性、中立性、専門性を担保する制度が事実上ない。産業医個人の自覚に拠るしかない。こうした現状が、高額な報酬につられて使用者への安易な迎合に走る「ブラック産業医」が生まれる温床になっている。
AさんBさんを始め、主治医の復職可能判断が産業医によってひっくり返され復職を拒否された3人の労働者が2017年4月、厚生労働省や関係機関に対し、産業医の客観性・中立性の担保を求める申し入れを行った。
申し入れたのは、(1)復職の可否について、産業医と主治医の判断が異なる場合、産業医が主治医に十分な意見聴取を行うことを法令で義務化すること、(2)法令による産業医に対する懲戒制度の創設、(3)メンタルが原因による休職の場合、精神科専門医でない産業医が復職の可否を判断できないようにすることなどであった。
厚生労働省への申し入れは、メディアを通じて「ブラック産業医」の存在を広く社会に問題提起するきっかけになった。産業医関連団体へのインパクトは大きく、問い合わせも多く受け、その後の法改正にも影響を与えたようである。
4 労働安全衛生法改正と産業医の在り方
近年、産業医に関する労働安全衛生法の改正が進められている。労働者の健康管理における産業医の義務の強化として、労働安全衛生法第13条と14条で、産業医は知識と能力の維持向上に努め、誠実に職務を行わなければならないという項目が追加された。他方、産業医の権限強化として、事業者は、労働時間に関する情報やそのほか必要な情報を産業医に提供しないといけないこととなった。このほかに産業医の権限を担保するため、産業医の勧告と地位の確保、健康情報管理の構築なども定められた。
かつて労働災害の発生原因は、製造工場などでの危険作業等が主であったが、最近は、オフィスでの長時間労働や人間関係のトラブルが心理的負荷となって精神疾患を発症するという労働災害が急増傾向にある。法改正による産業医の権限の強化は、これらの変化を背景としている。
産業医は、労災予防のため、職場巡視で外見からわかる職場の危険だけでなく、職場の内実に迫り危険性を把握する必要がある。法改正の趣旨に則って産業医の的確な権限行使がなされれば、現代の職場における精神疾患発症を防ぐことに役立つ可能性はある。
しかし残念なことに産業医が十分に機能していないというケースは少なくない。機能していないどころか、職務の客観性、中立性を曲げて、労働者の不当な追い出しに加担する「ブラック産業医」まで散見され、多くの労働者が泣き寝入りせざるを得ないケースも少なくないと考えられる。
本来、産業医には、労働災害を防ぐ「番人」としての役割が期待されている。産業医には、長時間労働の実態など職場状況をしっかりと把握し、会社に対して臆することなく意見を述べ、是正を求める姿勢が求められる。
産業医の職務の中立性は、これまでは職業倫理に支えられてきたものの、それだけでは不十分である。産業医の職務怠慢や会社への不当な迎合を制度的に防ぐため、産業医の客観性・中立性を担保する懲戒制度などを設けることも課題である。
(以上は公益社団法人自由人権協会の会報に寄稿した内容です)
投稿者 | 記事URL
大気汚染によるぜん息等患者の医療費助成制度の創設のために、公害等調整委員会に公害調停を申請しました
2019年2月19日 火曜日
2019年2月18日、全国公害患者の会連合会、東京、川崎、横浜、千葉、埼玉、名古屋、大阪の大気汚染公害患者は、大気汚染によるぜん息等患者の医療費助成制度の創設のために、公害等調整委員会に公害調停を申請しました。
トヨタ自動車等自動車メーカーらは、これまで公害対策の不十分な自動車の大量製造・販売、とりわけ1970年代後半以降のディーゼル化、1980年代以降の直噴化の積極的作為による侵害行為によって、深刻な大気汚染を発生させ、甚大な健康被害を生み出してきました。
1988年に公害健康被害補償法の地域指定が解除された後も都市部を中心に深刻な大気汚染が継続しており、多くの公害被害者が生まれています。
その最大の原因は、自動車排ガス、特に粒子状物質(PM)に対する国の規制が遅れたことにあります。これらの公害被害者の救済は、環境省をはじめ自動車メーカーなどの関連業界にとっては喫緊の課題となっております。
実際に、今なお、大気汚染によるぜん息等の患者の方々は,ぜん息や医療費の負担等で苦しんでいる状況にあります。
自動車メーカーらは、東京大気汚染公害裁判の和解に基づき、東京での医療費助成制度に資金拠出したものの、その後の追加拠出を拒否したのみならず、その他の地域の被害者に対しては、何らの負担もされていません。
環境省も、財源確保ができないとして、医療費助成制度の創設を行うに至っておりません。
医療費助成制度の創設のためには、公害等調整委員会の場において、環境省、自動車メーカーらを含めた協議の場が必要であり、公害調停を申請するに至りました。
当事務所からは、大気汚染公害全国調停団に、団長篠原義仁弁護士、副団長西村隆雄弁護士、山口毅大弁護士が参加しております。
裁判等をしなくとも、公害患者の方々が救済される医療費助成制度の創設のために、弁護団一同粉骨砕身する所存です。
2月18日時点で、NHK、毎日新聞、日本経済新聞、時事ドットコム、朝日新聞等で報道されました。
ご支援を宜しくお願い致します。
投稿者 | 記事URL
メンタル疾患労働者を強制排除するNECディスプレイソリューションズ会社と意を通じた指定医 提訴の概要(弁護士 川岸卓哉)
2019年1月31日 木曜日
2018年1月28日、NECディスプレイソリューションズと、会社と意を通じた指定医によって、退職に追い込まれた事件について、提訴をしました。
神奈川新聞記事
http://www.kanaloco.jp/article/385245
産経新聞記事
https://www.sankei.com/region/news/190130/rgn1901300036-n1.html
1 事件の概要
本件は、被告NECディスプレイソリューションズ株式会社(「被告NECDS」)において、新卒採用で就労を開始した新入社員であった原告が、業務に起因して適応障害を発症したところ、被告は違法な逮捕解禁で原告の職場から強制的に排除し、その後主治医から復職可能の診断が何度も出されているにも関わらずこれを無視し、休職期間満了により退職に追い込んだという事案。これに対して、被告NECDSに対して、地位確認及びバックペイ、慰謝料等を求めると共に、被告NECDSと意を通じた指定医に対して、十分な聴取も必要な検査もないまま発達障害の診断をし、原告に対し障害者のレッテル張りをして、退職に追い込んだ行為に対する慰謝料を請求する事件である。
2 適応障害の発症と強制排除 指定医と意を通じた復職拒否
2014年4月、原告は、被告NECDS生産技術グループにおいて、大卒新入社員として就労を開始した。同グループにおいて原告は唯一の20代の若い新人であり、一身に期待を背負い、業務に務めていた。しかし、同グループにおける、原告に対するセクシャルハラスメント、違法行為への加担指示、上司の無理解な叱責等により、2015年5月頃より、原告に適応障害の症状が発症するようになった。
2015年12月、被告NECDSは、適応障害を発症した原告を職場から出すため、職場で業務従事中だった原告の抵抗を抑え込み、4人がかりで両手両足を抱えて逮捕、拉致し職場から追放した。その後も、被告NECDSは、原告の主治医ら専門医から適応障害は回復しており復職可能との診断が何度もなされ、個人加盟労働組合であるの電機情報ユニオンとの交渉が重ねられていたにも関わらず、一切、診断書を無視し、復職を認めず2018年10月31日付けで、休職期間満了による退職を一方的に通知した。
さらに、本件では、被告NECDSと、指定医が意を通じ、一体となって、必要な診断を行わないまま、結論ありきで「発達障害」の病名を付け、障害者のレッテル張りをし、障害者雇用枠でのNECグループ企業での採用をすすめ、これを拒否した原告を退職に追い込んだものである。
2 本件の社会的意義
(1)急増するメンタル疾患者に対しての復職支援の拒否を糾弾
今、わが国において、精神疾患の急増と、休職者への復職支援は社会問題となっている。厚生労働省においても、「心の健康問題により休業した労働者の職場支援手引き」が制定され、各企業において復職支援が進められているところである。しかるに、被告NECDSは、一度、業務に起因して適応障害という精神疾患を発症した労働者に対し、違法行為を用いて強制的に排除し、「復職可能」と診断する主治医の数々の診断書を徹底して無視し、交渉を重ねてきた労働組合と約束も反故にし、復職を拒否する態度を貫いており、極めて悪質である。
(2)急速に広がる「発達障害」の病名を利用しての職場からの排除
さらに、本件では、今、急速に社会においてひろがっている「発達障害」の病名を悪用し、労働者を障害者扱いにし、退職に追い込む手法も併用されている。
「発達障害」の病名の広がりの一方で、それぞれの「発達の個性」まで「障害」であり社会的に排除される風潮が危惧されている。このため、「発達障害」の診断を的確に実施すべく、近年では、診断アセスメントツールが開発されている。しかし、被告医師は、必要な検査や診断をほとんど行わずに、原告を「発達障害」という障害者とし、被告NECDSの職場排除に加担したものである。
3 原告の復職を認めない背景-NECグループの電機リストラ
(1)電機リストラ
本件が、大手電機メーカーNECグループで起きたことは偶然では無い。昨今、電機産業においては、選択と集中という名の下で、企業の雇用責任も社会的責任も顧みることなく、様々な事業から撤退を決めて、大量の労働者の職を奪っていく電機リストラが猛威を奮っている。犠牲になった正規労働者は、既に44万人にまで及んでいる。特に、その中で、NECの場合、目先の利益のために事業からの撤退を繰り返す縮小経営と、安易な人減らしリストラが顕著で、大手電機メーカーの中でも際立っている。
縮小経営の象徴としては、かつて、世界一であった半導体、業界を席巻したパソコンや携帯電話の事業さえも撤退ないし売却を行っている。
人減らしリストラでは、2002年に1万4000人リストラ、2009年に2万人リストラ、2012年に1万人リストラなどの大規模なリストラを繰り返し、2018年からは3000人リストラを強行している。
その結果、2001年には5兆4097億円をあげていた売上高は、現在では2兆8444億円(47%減)に激減させ、社員も14万9931人から11万1200人(26%減)に大きく減らしている。
(2)表面化しない特異な大量リストラ
しかし、それにもかかわらず、電機リストラは、社会問題にもほとんどなっていない。
これは、電機リストラの手口が、法的には違法無効な整理解雇を、事実上の圧倒的な力関係の差の中で個別に合意を取り付けることで、埋めていくというものだったからである。
NECにおいては、特別転進支援制度と呼ぶ早期退職制度が用いられ、早期退職制度への応募を強いる人権侵害の違法な退職強要面談が組織をあげて行われている。2012年の1万人リストラでは、密室・会議室での退職強要面談は10回以上にも及び、国会でも問題にもなった。
(3)本件事件と電機リストラ
本件は、高いストレスの労働現場で、一度、メンタル系疾病に罹患した労働者については、様々に口実を設けて職場から排除し、最終的には休業期間満了で退職させるという身勝手な企業の本質が、典型的に現れた事件である。それは、企業の最大限の利益追求の前では、労働者保護規制を乗り越えるべき障害と位置づけて、確信犯的にこれを突破していく、現在も進行中の一連の電機リストラとその本質を同じくするものといえる。
また、被告NECDSを含むNECグループでは、現在、2018年からの3000人解雇が強行されており、一度は、メンタル系疾病に罹患した原告を被告NECDSが職場に受け入れることは、第一線でフルに働き続けている労働者から困難な退職合意を取り付けるにあたっての障害となると考えてのこととも推測出来る。
4 本件提訴に至る経緯
被告NECDSは、原告が所属する電機・情報ユニオンとの団体交渉において、原告の職場復帰を繰り返し表明していた。ところが、結局は、一方的に、休職期間満了による退職通知を送りつけてきた。このため、やむをえず、本件提訴となったものである。
5 原告伊草さんの提訴の思い
NECDSに入社できて家族や親戚も含めてみんなにお祝いの言葉をいただきました。
私も入社試験の合格通知が来て、人生で一番嬉しかった瞬間だったというのをよく覚えています。私はNECDSに入社して、一生懸命業務をまっとうし、社会に貢献できる人間になりたいと思いました。
入社時の仕事への意欲と職場からの期待感を背負いながら一生懸命業務をまっとうしておりました。
年の離れた職場の皆様に1日でも早く認めてもらいたい、1日でも早く1人前になりたいという気持ちで満ち溢れていました。
しかし、飲み会の席での部長からセクハラを受けてから、私の中ので部長への嫌悪感、セクハラ行為を黙認していた職場の人たちへの不信感が強まりました。「こんなことがNECの職場で許されるのか、なんで誰も止めてくれないんだ」という思いです。
業務中でもセクハラ被害を思い出すたびに涙を流し、誰にも相談することもできませんでした。
そして2015年12月18日、職場の人に囲まれて拘束されて会社の外へ排除されました。
言葉では表現しきれない屈辱感と恐怖感で身体がうまく動かず、「なんでこんなことするんだ、なんでこんなことをされなければいけないんだ、」という気持ちでいっぱいでした。
復職可能の診断書を会社に提出して、職場に戻れると思ったのですが、復帰は認められませんでした。
無理に出社しようものなら、「また拉致されて職場から排除されるのではないか」という恐怖感がありました。
私は会社の言うとおりリワークに通い、今度こそ復帰できると思ったのですが、それでも復帰は認められませんでした。
今までの努力はなんだったのか、なんのためのリワークトレーニングだったのか、
初めから私を解雇するために行われた計画な事件だったのだとおもい、私は怒りで満ち溢れていました。こんなことあってはなりません。同じようなやり方でみんな辞めさせられていったのかもしれないとおもうと、悲しみとそれ以上の怒りが沸いてきます。
大企業であるNECとしてそんなことして恥ずかしくないのか、入社時の新入社員説明会で言っていたNECwayや企業行動憲章とはなんだったのか。今NECがやっていることを自信を持って世界中に向かって発信することができるのでしょうか。
医者は患者を病気を治すのが最大の役割りだと思います。
しかし、指定医は私に発達障害であるかのような病名をつけました。
これは診断するために必要な検査などを行わずにつけたものです。
無知である患者を医者という優位な立場を利用し、会社の意を汲んで病人にしたてる。
この事件が起きてから、今でも他の病院に行くときも心が苦しくなります。
なぜ、精神科の医者に心を傷を傷つけられなければならないのか、傷を癒すのが医者の役割りではないでしょうか。
私の不当解雇撤回のたたかいはとても大変かもしれません。
相手は大企業のNECです。しかし、大企業だからといってそれは許されるものではありません。
私がここで諦めてしまえば、今後、私と同じような扱いをされる人が出てくると思います。
去年1月30日、NECの3000人リストラが発表され、退職強要面談で精神疾患になってしまった人も居るかと思います。
精神疾患になって、会社から優しく「体調が悪いなら休職という制度がありますよ、ゆっくり休んでください」と休職の提案を受け入れた人たちもいるかと思います。休職して一時的には退職強要面談から回避することができたかもしれません。
しかし、それは休職という制度を悪用したリストラ策の一環かもしれません。
私はそのことを多くの労働者の皆様に知っていただきたいです。
休職という本来の目的に反したリストラ活用作は絶対に許しません。私のたたかいは自分を救うたたかいだけではなく、
現在休職されている方、これから休職されるかたなどを救うたたかいにもなると思います。
投稿者 | 記事URL
2019年劈頭にあたり,新年のご挨拶を申し上げます。
2019年1月1日 火曜日
昨年4月,川崎合同事務所は,地域の皆さまに支えられて,50周年を迎えることができました。これもひとえに,依頼者の皆さま,事件や運動をともにたたかってきた労働組合,民主団体の皆さまのご愛顧・ご支援の賜物です。心より厚く御礼を申し上げます。
昨年は,「安倍9条改憲NO!」で一致した,3000万人署名などの反対運動の広がり,安倍政権下で蔓延する権力の私物化・民主主義の破壊に対する市民の強い批判により,改憲発議を阻止できました。また,辺野古新基地建設の是非を問う沖縄県知事選挙においては,新基地建設反対の玉城デニー氏が勝利しました。
今年は,統一地方選挙,参議院議員選挙があり,改憲を許さないたたかいが重要になってきます。また,人間らしく働くことができる労働法制を確立、消費税10%への増税阻止等様々なたたかいの年でもあります。
事務所所員一同,事件処理に万全を期すことは,もちろん,平和で,暮らしやすい社会を目指し,全力で奮闘していく所存です。
今年も宜しくお願い申し上げます。
川崎合同法律事務所
投稿者 | 記事URL
労働法律旬報2018年11月上旬号に掲載されました。
2018年11月15日 木曜日
労働法律旬報1923(2018年11月上旬号)特集「過労死防止大綱」の見直しについての特集記事に、川岸卓哉弁護士の「勤務間インターバル制度の意義と法規成果へ向けた課題」が掲載されました。
投稿者 | 記事URL
「差し迫った安倍改憲に反対する川崎市民集会」を開催しました!
2018年11月2日 金曜日
2018年10月29日(月),川崎市産業振興会館ホールで,「差し迫った安倍改憲に反対する川崎市民集会」を開催しました。当事務所も,共催者として,名前を連ねました。
集会では,法政大学法学部教授の山口二郎先生を講師としてお招きし,自衛隊明記論の問題点とともに野党共闘の重要性等についてご講演頂きました。
また,立憲民主党,日本共産党,社会民主党の立憲野党の皆さまにもご参加頂き,自由党の方からもメッセージを頂いた上で,立憲野党として,安倍改憲に反対する旨の力強いご挨拶を頂きました。
参加者は,200名を超え,大盛況の集会でした。
当事務所では,今後とも,立憲主義,平和主義,民主主義を破壊する安倍改憲に反対する運動に取り組んでいく所存です。
投稿者 | 記事URL
労働判例2018年9月1日号に掲載されました
2018年9月7日 金曜日
藤田温久弁護士、山口毅大弁護士が弁護団として活動している、日産自動車派遣切り、期間工切事件についての、神奈川県労働委員秋命令が、「労働判例2018年9月1日号」に掲載されました。
投稿者 | 記事URL
労働判例 2018年8月1・15日号(1180)に掲載されました
2018年8月14日 火曜日
労働判例 2018年8月1・15日号(1180)の巻頭に、特別掲載として、川岸卓哉弁護士が主任を務める
グリーンディスプレイ(和解勧告)事件、横浜地方裁判所川崎支部平成30年2月8日決定~長時間労働後帰宅途中の交通事故死(過労事故死)と安全配慮義務違反~
が掲載されました。
投稿者 | 記事URL
弁護士ドットコムニュースに掲載されました
2018年8月14日 火曜日
弁護士ドットコムニュース「無期転換逃れで雇い止め「6カ月後にまた来てよ」 雇い直されなかったらどうなる?」に、山口毅大弁護士がに掲載されました。
是非、ご覧下さい。
投稿者 | 記事URL
最近のブログ記事
- いよいよ山場を迎える 台風19号多摩川水害訴訟 (弁護士 西村隆雄)
- 2/25(水)所内行事のため 16時30分に閉所します
- かわさき市民オンブズマンによる川崎市議会議員海外視察住民訴訟(弁護士 小林展大)
- 2026年劈頭にあたり 新年のご挨拶を申し上げます
- 畑福生弁護士が小田原市立下曽我小学校ホームページに掲載されました
- 不動産問題専門サイトを開設しました!
- 自衛隊配備が進む先島諸島─様々な不安と隣り合わせの住民生活を現地レポート(弁護士 前田ちひろ)
- 過労事故死事件解決の先の約束の書「睡眠科学・医学・労働法学から考え直す日本の労働時間規制」(日本評論社)を出版しました(弁護士 川岸卓哉)
- 2024年総選挙の結果生まれた国政革新のチャンスを大きく広げよう(弁護士 藤田温久)
- 篠原義仁弁護士を偲ぶ会 ~「挑戦と闘い」の軌跡 そして絆~ のご報告(弁護士 川口彩子)
月別アーカイブ
- 2026年2月 (3)
- 2026年1月 (1)
- 2025年9月 (1)
- 2025年5月 (1)
- 2025年4月 (6)
- 2025年2月 (1)
- 2025年1月 (1)
- 2024年12月 (3)
- 2024年11月 (1)
- 2024年9月 (1)
- 2024年4月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年7月 (1)
- 2023年6月 (2)
- 2023年5月 (2)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (1)
- 2023年1月 (1)
- 2022年12月 (4)
- 2022年11月 (3)
- 2022年10月 (1)
- 2022年8月 (1)
- 2022年7月 (1)
- 2022年3月 (1)
- 2022年1月 (2)
- 2021年12月 (2)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (1)
- 2021年7月 (2)
- 2021年6月 (1)
- 2021年5月 (1)
- 2021年4月 (2)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (1)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (2)
- 2020年8月 (1)
- 2020年7月 (3)
- 2020年6月 (2)
- 2020年4月 (6)
- 2020年3月 (1)
- 2020年2月 (3)
- 2020年1月 (5)
- 2019年12月 (2)
- 2019年11月 (4)
- 2019年10月 (2)
- 2019年8月 (1)
- 2019年7月 (3)
- 2019年6月 (1)
- 2019年5月 (1)
- 2019年2月 (1)
- 2019年1月 (2)
- 2018年11月 (2)
- 2018年9月 (2)
- 2018年8月 (4)
- 2018年7月 (3)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (3)
- 2018年4月 (1)
- 2018年3月 (2)
- 2018年2月 (1)
- 2018年1月 (3)
- 2017年10月 (4)
- 2017年9月 (4)
- 2017年6月 (1)
- 2017年5月 (1)
- 2017年3月 (1)
- 2017年2月 (2)
- 2016年12月 (1)
- 2016年10月 (2)
- 2016年8月 (76)