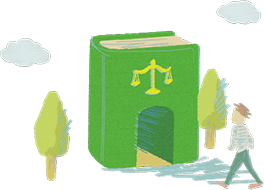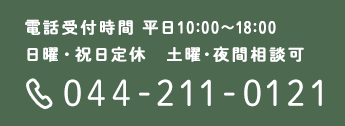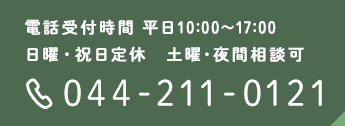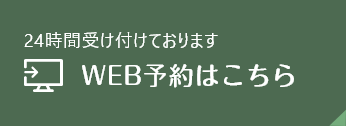ブログ
Q ちょっとだけ電話で相談したいのですが、電話でお話できますか?
2021年3月19日 金曜日
A
原則、予約を取って頂いて対面でのご相談をおすすめしておりますが、お電話頂いた際に、事務所に対応可能な弁護士がいる場合、短時間とはなりますが、できる限りお話をお伺いしたいと思っておりますので、まずはお電話ください。但し、事案によっては、対面でじっくりお話を伺わないと把握困難なご相談もありますので、ご了承ください。
投稿者 | 記事URL
家賃を払わない借主に、家を明渡してもらうには(弁護士 渡辺登代美)
2021年3月15日 月曜日
家を貸していて、「家賃を払ってもらえないので、出ていって欲しい。」というような場合、どうしたら良いのでしょうか。
1 1か月の滞納で出ていってもらうのは難しいです
賃貸借契約書には、「貸主は、借主が賃料その他の債務の支払いを1か月以上怠ったとき、何らの催告なしに契約を解除することができる。」というような契約解除条項が入っているのが一般的です。
しかし、賃貸借契約のような継続的契約は、貸主・借主相互の信頼関係のうえに成立っているといえますので、この信頼関係を破壊するに至ったと認められるような事情がなければ、なかなか賃貸借契約の解除は許容されません。病気や怪我など、突然賃料が払えなくなることはままあるのに対し、借主にとって住む場所を失うことは重大なことがらだからです。契約書に1か月と書いてあったとしても、通常、1か月賃料を滞納しただけで契約を解除して出ていってもらうことは難しいです。
裁判をやっている感覚では、最低でも滞納3か月、6か月あればまあ大丈夫かな、という感じです。
2 裁判で判決を得た後、強制執行しなければならない場合もあります
その後、裁判を起こして建物明渡の判決をもらい、それでも出てもらえない場合は、強制執行をします。裁判所の執行官が現地に赴き、まず、「いついつまでに明渡しなさい。」という警告と貼紙をします。その日は、とりあえず、それで終了です。
次に、もう一度、執行官が定められた明渡期日に現地に行き、まだ明渡されていない場合、建物内の物を運び出し、業者に保管させる措置がとられます。1か月程度保管した後、売却処分されるのが通常です。
強制執行費用や、未払賃料は、借主に請求することができますが、月々の賃料を支払えなくなっているような状態の人ですから、回収するのは困難です。そこで大事なのが、保証人です。近ごろは、保証会社が保証するケースも増えています。
3 明渡の完了まで1年、費用は100万円くらいかかることがあります
賃料の不払いが発生してから、明渡の強制執行が完了するまでには、1年くらいかかってしまうことも多いです。執行費用を借主や保証人に請求することはできますが、明渡の裁判を依頼するときの弁護士費用や借主が置いていった動産の保管費用は貸主が負担することになります。多くの動産を放置したまま借主が逐電してしまった場合など、弁護士費用と保管費用で合計100万円くらいかかってしまうこともありますが、自力救済が認められていない日本の法制度下では、借主の持ち物を勝手に処分してしまうことはできないため、健全な賃貸業を継続するためには、致し方ないことだと思います。
4 逆に賃料が払えなくなった場合は、話合いの余地があります
逆に、賃料が払えなくなってしまった場合でも、「明日すぐに、荷物をまとめて出ていけ。」と言われることはなく、家主との話し合いによって若干の猶予を得ることは可能です。上記したような建物明渡の裁判をし、強制執行をする費用や時間を考えれば、貸主が譲歩する余地も充分あると考えられるからです。
いずれにしても、弁護士に相談してみて下さい。法律的な解決方法が見出せるはずです。
投稿者 | 記事URL
終活について(弁護士 小野通子)
2021年3月10日 水曜日
最近、お一人暮らしやご夫婦二人暮らしの依頼者の方と雑談等をしていると、「将来のことが不安なんだよ」と言われることが多くなってきました。どういうことか詳しくお伺いすると、例えば、将来、ご自身が認知症になったら、または、亡くなったら、病院や施設との契約、遺品の整理、葬儀や納骨など、一体誰がやるんだろう、と心配になるということです。高齢化や家族関係の変化が進む中、このようなご心配をなさる方は増えていると思います。
そんな皆様に対して、我々の事務所では一体何ができるか。ここでは、「見守り財産管理」+「任意後見契約」+「遺言・死後事務委任契約書の作成と執行」をご提案したいと思います。
1 見守り財産管理
安心できる老後を送っていただくために、弁護士が、皆様に定期的なご連絡をし、必要な場合には面会で相談を行い、弁護士が代理して各種契約や支払等をする契約があります。どなたでも、高齢になってくると、消費者被害に遭ってしまったり、高齢者施設入所の資金捻出の為に不動産の処分が必要になったり等、法的なアドバイスが欲しい場合も増えてきます。入院することになっても、緊急連絡先となったり、安心して病院や施設との契約や支払いを任せられる親族がいないという場合もあります。このような場合に、見守り財産管理をご依頼頂ければ、電話やメールなどで日頃からつながっていて、困ったときに気軽に頼れる、みなさんの生活や人生観を良くわかっている弁護士がいる、という安心をお持ちいただけると思います。
2 任意後見契約
高齢化に伴い、認知能力・判断能力が低下してくる場合もあります。見守り財産管理は、あくまで最終的な判断はご依頼本人ですので、認知能力や判断能力があまりに低下してしまうと、見守り財産管理だけでは対応しきれないリスクがあります。このような場合の保険として、任意後見契約を締結することが考えられます。
認知能力が低下した後に親族等が申立を行う成年後見契約もありますが、そもそも、申立を任せられる親族がいない場合もありますし、成年後見契約では、後見人になる専門家は裁判所が独自に選任するため、ご自身が信頼する弁護士に後見人を任せることができません。
予め、任意後見契約を締結しておけば、認知能力が低下した時に、ご自身が選んだ弁護士を任意後見人として、裁判所の監督の下、ご依頼者の預金を払い戻したり自宅を売却したりして費用を確保し、ご依頼者が予め希望した高齢者施設に入所するための手続きをしたり、要介護認定を申請して介護契約を利用したり等することが可能になります。
3 遺言・死後事務委任契約書の作成と執行
仮にご依頼者が亡くなってしまった場合には、遺言や死後事務委任契約に従って、依頼を受けた弁護士が、皆様のご希望に添った手続きを執り行っていくことになりますが、その前提として、遺言や死後事務委任契約書の作成が必要になります。
遺言に記載するのは、主に遺産の取り扱いについてです。遺言を作成すれば、殆ど知らない遠い親戚に遺産を渡すのではなく、ご自身がお世話になったご友人や施設、団体等に遺産を渡し(寄付し)、感謝の気持ちを表すことも可能です。なお、遺言はご自身でその内容を書いて頂いただけでももちろん法的な効力はありますが、我々弁護士を遺言執行者として選任して頂ければ、せっかく作った遺言が誰にも気づかれないまま、実現されない等の心配が無くなります。
一方、遺言に記載するのは主に遺産の取り扱いについてである為、例えば、ご自身の葬儀やお墓、遺品の整理はどうするか、ご自身のPCやスマートフォンに入っている個人的なデータやSNS等のIDの処理はどうするか、飼っていたペットをどこに引き取って貰うか等、詳細な希望を記載することはできません。そこで、このようなことについては、死後事務委任契約をされることをおすすめします。
遺言と死後事務委任が矛盾しては困りますので、遺言と死後事務委任契約は同じ弁護士が作成するのが望ましいと考えられます。
4 最後に
ここでご紹介した以外にも、成年後見制度や家族信託契約など、我々弁護士にもできることがあります。終活は、皆様お一人お一人千差万別で、同じようには語れません。皆様とたくさん話をして、じっくり皆様に合った方法を考えたいと思います。「これが心配。。」ということがございましたら、一緒に悩み考えますので、遠慮無く我々に声をかけて下さい。
なお、川崎合同法律事務所では、「老後安心プラン」のパンフレットを作成しました。チャート図などで、皆様に必要なプランを選択できるしくみもご用意しておりますので、ぜひ、ご覧下さい.
なお、事務所にも備え付けてありますので、パンフレットをご覧になりたい方はお気軽にお声がけください。
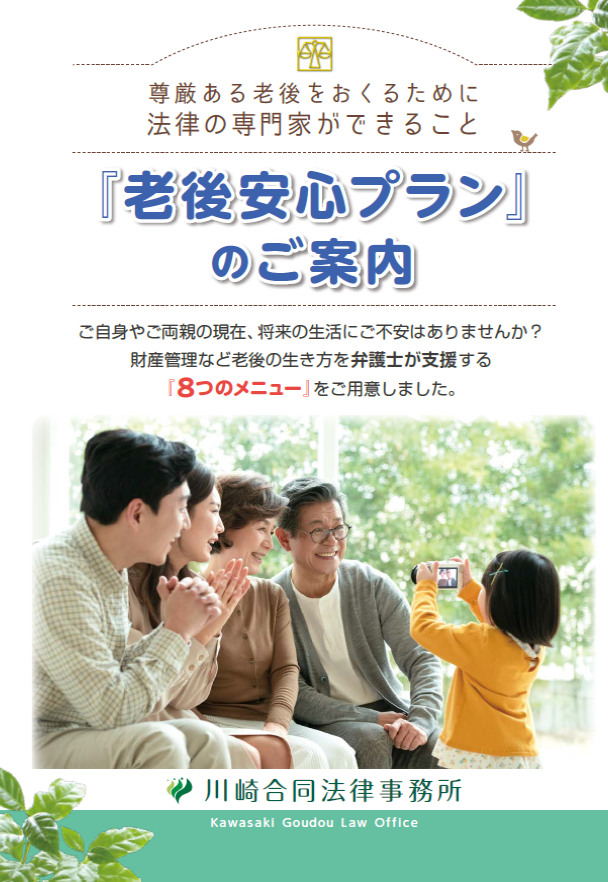
投稿者 | 記事URL
家業のある方、家業を引き継ぎたい方、引き継がせたい方は遺言書を書きましょう(弁護士 星野文紀)
2021年3月2日 火曜日
第1 家業を相続する場合は遺言書を必ずつくりましょう
事業を家族で行っている場合、事業は家族の大事な財産です。子供に引き継がせたい人も多いのではないでしょうか。
もしあなたが会社の社長やオーナーで、子が将来その事業を継ぐ(事業承継・事業相続)予定をしているなら、あなたが元気なうちに、遺言書を書くことを強くおすすめします。
1 遺言がないと事業が続けられなくなる可能性が
相続は、亡くなった人(被相続人)の死亡とともに発生し、被相続人の財産が相続人(被相続人の配偶者や子)に引き継がれます。
相続財産は、遺言書が無ければ基本的に法定相続分での分割になります。そして、事業に関係する財産的権利も相続財産になります。
相続人が複数いる場合、事業に関係する財産的権利は、相続人間で分割承継される可能性があるということです。そうなると会社の経営権はバラバラになり、事業の経営に関する意思決定で揉めたり、一時的に会社のキャッシュが流出したり、将来に渡って事業から得られる収益を按分しないといけなったりします。結局、会社の運営は滞り、最悪経営が続けられない原因となるのです。せっかく遺した財産が家族間の争いという最悪の結果になるのです。
2 遺言書があれば、スムーズに事業が続けられる
しかし、遺言書があれば、特定の相続人に事業に関係する財産的権利を集中することが可能になり、事業を引き継ぐことが可能になります。事業を引き継がない相続人にもあらかじめ配慮をすることによって家族間の争いも防げます。事業を相続させたいなら、遺言を書くことを強くお勧めします。
以下、遺言による事業承継について個人事業の場合と会社法人の場合に分けてポイントを説明してみます。
第2 遺言で、上手に事業を引き継ぐ方法
1 個人事業の場合
個人事業を父親から子へ引き継ぐ場合を例に考えます。
父親が個人事業で事業を営んでいる場合、法人格がないので、事業に関するすべての権利義務は、自然人である父親に帰属しています。事業主は父親個人であり、土地建物といった不動産や、機械設備等の動産、契約上の権利義務等に至るまで全て父親のものです。
これら財産的権利は、通常、相続財産になりますので、遺言書のない相続が開始すると、相続は法定相続分によって処理され,子はすべて同じく第一順位の法定相続人になり、その相続分は全て同じになります。したがって、遺言がなければ、事業用の財産が遺産分割でバラバラになり、最悪、事業が続けられなくなる可能性があるのです。
そこで、遺言書が必要になります。遺言書で跡を継ぐ人に事業用資産を集中させれば、遺言執行により跡を継ぐ人が事業用資産を承継することができます。
経営者が元気なうちに事業用資産を後継者に相続させる遺言書を作成するべきです。
2 株式会社(有限会社)の場合
会社の場合、事業に関する権利義務は、基本的に会社に属します。したがって、会社の株式をだれが承継するのかが問題となります。逆に株式さえ承継してしまえば、それで事業承継はできます。遺言書がなければ株式がバラバラになり、事業が承継出来なくなる可能性があります。
したがって、経営者が元気なうちに必要な株式を後継者に相続させる遺言書を作成するべきです。
第3 遺留分の対策重要
これまで述べてきたように、遺言書により事業承継は可能です。しかしまだ、遺留分という大きな問題が残っています。
遺留分とは、遺言書により、相続出来なかった(減らされた)相続人(兄弟姉妹以外)を保護するために認められる、最低限の割合であり、その割合分の相続財産は渡さなければいけません。
遺留分割合は直系尊属だけの場合、「遺留分算定の基礎となる財産」の3分の1。 それ以外の場合は、財産の2分の1となります。例えば、推定相続人が、妻と子二人の場合、法定相続分は、妻2分の1、子2人は4分の1ずつですから、遺留分は、妻が4分の1、子2人は8分の1ずつということになります。
したがって、仮に後継者に全財産を引き継ぐ場合、他の相続人から遺留分減殺請求がなされると、その割合の財産が持って行かれてしまうことになり、何らかの対策をしておかないと結局、事業が続けられないこともありえます。
以下に、遺留分対策の方法を書いておきます、紙面の都合上箇条書きにとどめます。いずれの方法を採るのかは個別の判断になりますので、弁護士にご相談ください。
① 生前から調整しておく
② 遺言書の付言事項で説得する
③ 代償分割に用いる資金として生命保険を活用する
④ 事業用財産を早めに贈与する
⑤ 相続発生前に遺留分放棄の事前許可の審判を得る
⑥ 事業承継の際の遺留分に関する民法特例を使う
⑦ 生命保険を使って遺留分算定の対象財産を減らす
⑧ 生前に事業用財産を売買により譲渡する
⑨ 相続人以外に生前贈与を使う
⑩ 種類株式を発行する
具体的な、遺言内容や、遺留分対策は個別の事例によって異なりますのでお気軽に弁護士までご相談下さい。
投稿者 | 記事URL
新型コロナウイルス関連解雇でお困りのみなさまへ(弁護士 山口毅大)
2021年3月2日 火曜日
2021年3月1日,厚生労働省は,新型コロナウイルスの影響による,解雇・雇い止め(見込みを含む。)の人数が同年2月26日時点の累計で9万人を超えたことを明らかにしました。
しかしながら,この人数は,全国の労働局やハローワークを通じて集計した数字ですので,実態は,もっと多いと考えられます。
また,2度目の緊急事態宣言により,解雇・雇い止めの数が増加傾向にあります。
このような状況下において,新型コロナウイルス感染症を理由とする解雇が全て適法,有効になるかといえば,そうではありません。
実際に,労働者が出勤したところ,熱があったので,新型コロナウイルス感染症の疑いがあるとして,帰宅するよう命じられ,しばらく自宅待機するように言われた挙げ句,熱があるのに出勤したとして解雇された事案,新型コロナウイルス感染症のために売り上げが減少したと述べて解雇した事案(実際には,多少の売り上げの減少があったものの,解雇が適法になる程の人員削減の必要性がなく,解雇回避努力義務を果たしていなかった事案),内定を取り消した等の事案(使用者が内定を出してないと強弁した事案,2020年3月下旬時点で新型コロナウイルス感染症による具体的な経営予測ができなかったとして内定を取り消した事案)において,解雇,内定取消が違法,無効として,職場復帰を果たし,あるいは,違法な解雇があったとして解決金を得た事案等があります。
解雇は,よっぽどのことがない限り,違法,無効となります。新型コロナウイルス感染症を理由とする場合も同様です。
新型コロナウイルス感染症関連の解雇でお困りのみなさまにおかれましては,お一人で悩まれることなく,ぜひ一度ご相談ください。
投稿者 | 記事URL
調停? 弁護士を入れて交渉? ―あなたの離婚に適切な方法選択―(弁護士 川口彩子)
2021年2月24日 水曜日
1 離婚するときに決めるべきこと
(1)離婚にあたり,最初の壁は「離婚をするかどうか」です。お互いに離婚を望んでいる場合もあるでしょうし,片方は離婚を決意していても,もう片方の気持ちが追いつかない場合もあります。条件次第では離婚してもよいという気持ちはあるけれども,条件が折り合わない場合は合意できません。
(2) 次に問題となるのは「親権者」です。20歳未満(2022年4月1日からは18歳未満)のお子さんについては,父母のいずれかを親権者に指定しなければなりません。
(3) 上記(1)(2)については,離婚の前に必ず決めなければなりませんが,養育費,慰謝料,財産分与,面会交流,年金分割などについては,何も取決めをせずに離婚することも可能です。とはいえ,離婚してしまうと夫婦は他人となるわけですから,あらかじめ離婚前に決めごとをしておくのが望ましいでしょう。
2 離婚の方法
「離婚届」を提出して離婚することを「協議離婚」といいます。3組に1組が離婚をする時代などと言われていますが,国内の大部分の離婚は協議離婚です。
当事者間で協議が整わないとき,あるいは当事者が家庭裁判所調停での解決を望むときは,家庭裁判所に調停の申立てをすることができます。調停で離婚についての合意が成立したときは「調停離婚」(場合により「審判離婚」)となります。
調停での合意ができなかったときは,離婚の成否について裁判で決着をつけることになります。判決で離婚が認められた場合は「裁判離婚」,裁判を進めるなかで当事者が合意し,裁判手続を利用して離婚を成立させることを「和解離婚」といいます。離婚の裁判は「調停前置主義」といわれ,調停での話合いを試みてからでないと提訴することができません。ただし,例外的に,相手方が行方不明の場合や,収監中であるなど,調停における話合いが不可能な場合には,調停を経ずに裁判に進むことができます。
3 協議離婚か調停離婚か
(1) 当事者間で話し合いが進められそうな場合
法律相談で解決水準を知る
当事者間の話し合いで決めごとができそうな場合は,協議離婚でよいと思います。ただし,協議離婚の場合,法的に決められるのは,離婚するということと親権者をどちらに指定するかということだけになります。
特に,養育費など,今後も支払いが続く場合には,公正証書を作成するなどして,万一,不払いがあった場合に速やかに財産の差押えができるよう,備えておいた方がよいでしょう。
取決めをしたい内容について,弁護士がご相談に乗ることが可能です。調停や裁判の事例をもとに,どこまで請求ができるのか,どの水準で解決するのが妥当かなどアドバイスをいたします。
(2) 弁護士を代理人に選任して,協議離婚を目指す場合
弁護士は中立な第三者ではない
ご相談を受けるなかで,「第三者に入ってもらって話し合いをしたい」と言われることがあります。ただ,弁護士は中立な第三者とはなりえず,ご相談を受けた方の立場に立ってしか行動できません。双方の言い分を聞いて,弁護士がジャッジするということはできませんので,そこはご理解をいただいています。
協議離婚で弁護士が前面に出てくるのは,ご相談を受けた方の「代理人」として,相手方と離婚の協議をする場合です。
話合いでの解決が可能そうか
ただ,相手方が離婚を頑なに拒んでいる場合,あるいは双方が強く親権を主張している場合など,弁護士が話をしたところで到底合意が得られなそうなケースでは,この過程を省略し,最初から調停を申し立てる場合も少なくありません。つまり,これまでの相手方の言動から,協議離婚が可能かどうかを見極め,可能そうだったら代理人として交渉にあたるということになります。
どこまで条件にこだわるか
離婚,親権では合意ができそうでも,金銭面等のその他の条件での合意が難しそうな場合は,ご相談者がその条件にどこまでこだわるかによります。こちらにも譲歩の余地があるのでしたら,弁護士を代理人として粘り強く交渉していくという道もありますが,交渉の余地が一切ない場合は,弁護士を立てたとしても協議離婚を目指すのは難しいということになるでしょう。
公正証書の作成が必要か
その他の判断要素としては,公正証書の作成までもっていけるかどうかということもあります。公正証書の作成には,相手方の協力が不可欠です。不払いのときに強制執行を受けることを了承する書類ですから,相手方によっては,応じてもらえないこともあります。公正証書までの作成はしなくとも,現時点では合意書が作成できればそれでよしとするのであれば,交渉による協議離婚の道も見えてきますが,強制執行を可能とする法的な効力を持たせたい,けれども公正証書作成につき相手方の協力を得ることが難しそうな場合は,やはり調停の申立てを選択することになります。調停で合意ができれば,裁判所が作成する調停調書をもとに将来強制執行をすることが可能となります。
公正証書を作成せずとも,相手方が最後まできちんと支払ってくれるだろうという信頼がある場合は,合意書の作成で終わらせてもよいと思います。また,そもそも将来にわたる支払いの約束がない場合(たとえば一括払いで既に支払いを受けた場合)は,あえて公正証書にする必要はないと言えます。
合意書に反して支払いがなされなかった場合ですが,未払金を強制的に回収するには,まず民事裁判を起こし,そこで勝訴判決を得てから強制執行手続に進むことになります。
(3) 調停離婚に適した場合
相手方の同意がすぐには得られないと思われる場合
離婚することに同意が得られず,あるいは親権での対立がある場合は,最初から調停を申し立てることになります。必ずしも調停で解決がはかられるとは限りませんが,時間をかけて話し合いをしていくことで,相手方との合意が形成できる場合もあります。調停では,「第三者」である調停委員が,交互に双方の話を聞いてくれますので,その中で気持ちの整理をつけていただくことが期待できます。
相手方と話をすることが難しい場合
調停の場では,原則として,個別に話を聞かれます。あなたがお話しした内容は,調停委員を通じて相手方に伝わり,相手方の考えは調停委員を通じて聞かされます。相手方の前では委縮して話をすることができない場合や,どちらかが一方的に話し続け口を挟む余地がない場合など,冷静かつ建設的な話し合いができない場合には,裁判所に間に入ってもらって,決めるべき内容に向かって話を整理してもらうことになります。
妥当な解決をはかりたい場合
相手方が離婚や親権について一応は同意してる場合でも,養育費を極端に低く設定することや,お子さんにとって過負担となる面会交流を条件としてくるなど,一般的な水準からかけ離れた要求をされることがあります。逆の立場では,法外な養育費を請求されているというような場合もあります。
調停離婚の場合には,裁判所が間に入って解決をはかることになりますので,一般水準とはかけ離れた要求を排除することが可能となります。
決めごとに法的効力を持たせたい場合
相手方との話し合いが可能な場合は,協議離婚及び公正証書作成でもよいのですが,公正証書を作成するには通常2万円前後の費用がかかります。弁護士をつけなければ,調停の申立て費用は郵便切手代を含めても2000円程度ですから,大きなご負担なく,将来強制執行が可能となる書類を作成してもらうことが可能となります。
4 弁護士をつけるメリット
交渉で協議離婚を目指す場合
概ね着地点は見えているにもかかわらず,当事者同士だとどうしても感情的になって決めるべきことが決められない場合があります。そのような場合,弁護士を入れることによって,淡々と決めるべきことを決めていくことができます。
また,法律の専門家が提案することで,こちらの提案の妥当性,正当性について信用してもらいやすくなるという効果もあります。
こちらが弁護士をつけることで相手方にも弁護士がつく場合があり,専門家同士で妥当かつ迅速な解決をはかることが可能となります。
調停での解決を目指す場合
調停ではその場その場で判断を求められることが多くあります。内容によっては次回までに検討してきますとして回答を留保することもできますが,当事者にはその判断が難しいことがあります。一人で調停に臨むと,裁判所の意図を汲みきれずに,表面上の言葉で一喜一憂し,思うように調停が進められなかったという話をよく伺います。弁護士をつけておらず,当事者一人で調停をしていると,紛争解決を優先するあまり,調停委員から不利な結論を押し付けられることがあります。もちろんこれは調停委員の良し悪しによるのですが,必要以上にあなたの権利が削られないように防御するのが弁護士です。
弁護士は,現在,裁判所がどのような方向性を目指して話を進めようとしようとしてるのか,言外にある意図を汲んでこちらの対応を組み立てます。こちらが検討すべき点,やっておかなければならない点を的確に把握し,しっかり対策をして,調停に臨みましょう。
また,財産分与については計算が複雑になる場合も多く,専門家の助言があるに越したことはありません。その他,対立点が多く, 論点が多岐にわたる場合や,たくさんの条件を決めなければならない場合,弁護士は豊富な事例をもとに,あなたの立場を最大限まもりながら,着地点を見つけます。
既に調停が始まってしまっている方,調停の申立てを考えている方,相手方から調停を申し立てられそうになっている方,ぜひ一度ご相談に見えてください。あなたの現在の状況に応じたアドバイスをさせていただきます。
投稿者 | 記事URL
お金を払ってもらえなくて困ったことはありませんか(債権回収入門)~2021年2月時効に関する記載を修正~(弁護士 星野文紀)
2021年2月20日 土曜日
お金を払ってもらえなくて困ったことはありませんか
(債権回収入門)
~2021年2月時効に関する記載を修正~
弁護士 星野文紀
第1 債権回収とは
「債権回収」とは、債権者が債務者から金銭支払いを受けること。それを受けるための活動をいいます。
取引先が、商品やサービスの代金を支払ってくれない場合や、工事を行ったにもかかわらず発注者や元請会社が「工事に問題がある。」「支払うお金がない」などと言って代金を一部しか支払ってくれない場合、貸したお金を返してくれない場合などが典型例です。
権利があることに争いがないのに、お金を払ってもらうことができないとき全般を含みます。
権利があるかどうかに争いがあるときはその確定の作業(例えば、裁判を起こして判決をもらう等)の作業が別に必要になります。
では、債権回収の方法を見ていきましょう。少し、難しいですが、実務的に役立つ情報を書きましたので、参考にしてください。
ただし、わからないことがありましたら、早めに相談に来られることをお勧めします。
第2 債権回収のために普段からしておくべきこと
1 一般的には
(1) 債権回収の極意は信用できない人とは取引をしないことです。そのためには相手をよく知ることが大事です。
個人なら・・・経歴、世間の評判、資産、人柄、交友関係
会社なら・・・経営者、会社概要(関連会社、業務内容、取引実績、取引先、決算書(推移)、会社資産、借入等、従業員の様子(活気、年齢構成、余裕)
などをよく観察することが大事です。大事な取引相手とは、雑談をするなどしてコミュニケーションを取るようにしましょう。そうすることで、取引後も、変化に注意できます。
(2) 取引をする時は契約書を作るのが基本です。作った書類等を保管・整理しておくことも必要です。
(3) 回収のための情報も得ておくことも大事です。
普段の情報収集がいざというとき役に立ちます。
具体的には、
・相手にとっての自分の位置づけ
・主要取引先(社名・所在地・どんな会社か)
・各取引先との取引の量
・各取引先との決済方法(手段・締日・支払日)
・各取引先との関係性
・メインバンク、資金調達手段
・相手方の実権は誰が持っているのか
・相手の取引における強みはなんだろう
・決算書類
などの情報があれば後々役立ちます。
(4) 債権請求の対価を履行した証拠を確保しておく。
反対債務の履行義務がある場合は反対債務の履行を証明しないと支払いを受けることができない場合があります、反対債務を履行したという根拠を確保しておきます
・(例)物の販売なら、物を債務者が受け取ったという受領書
2 建築請負代金債権の場合
基本的には、一般の場合と変わりありませんが、若干の特殊性があります。
(1) 契約書を作ってもらえない場合
契約書が作れない場合が多いです。
その場合は見積を細かく発行し、日付入りの受領書・受領印をもらう等の工夫をしましょう。
請負額を作業員数で決めているような場合は、人工単価だけでも、合意書、承諾書を作り、現場監督にでも署名捺印してもらう。
(2) 債権請求の対価を履行した証拠を確保しておく。
請負完了の場合は元請あるいは注文者に立ち会ってもらい引渡証明をもらうといいでしょう。各仕事毎に完了証明がもらえればベターです。
人工出しの場合=出面の証明(元請けの現場監督の証明書等)をもらうのがいいでしょう。
(3) できるだけ短い期間で、その期間内の代金回収を行うのが被害を少なくするコツですので、支払いの頻度はできるだけ短くしましょう。
第3 危ないと思ったら
危ないと思ったら、次のことを検討しましょう。この辺りから、弁護士に相談することをお勧めします。
(1) 取引を減らす。(損害を減らす)
(2) 契約を見直す。(支払猶予などの機会をとらえて)
契約条項の見直し、違約金条項、解除、公正証書にする
「減額請求」などがあった場合、意義を留保して相手方申し出の金員を受け取る。
(3) 担保を取る。
保証人を付ける(個人保障)。抵当権。譲渡担保。仮登記担保。売渡担保(買戻特約)
第4 いよいよ債権回収
いよいよ実際の債権回収です。よく作戦を考えて迅速に行動しましょう。
(1) 未払いの原因を考える
債権回収はまず、債務者の置かれている状況を知ることから。
払えないのか、払いたくないのか
(2) 計画をよく練ってから迅速に行動を
相手のお金の流れをつかむことが大事です。
計画のポイントは
・費用
・時間
・確実性
です。
どの方法が適切かわからない場合は弁護士に相談するのがよいでしょう。
第5 回収のための手順(複数を組み合わせる)
次の手段をつかって回収します。詳細はご相談ください。
1 交渉
内容証明、電話、FAX、夜討ち朝駆け
安易な交渉は、危険。さまざまな、手段を検討したうえで交渉する。
交渉するなら迅速に。長々と交渉しない。
払う気にさせることが目的(やさしく、厳しく、スマートに)
合意がとれたら必ず書面にする。
約束を守らせる工夫も(違約金条項、公正証書、即決和解)
すぐに払えないなら、分割や、担保を検討する。
2 仮差押・仮処分
押さえるものを特定できるか、担保金を用意できるか
3 訴訟・強制執行
4 支払督促
争いのないときに債務名義を取る。
5 担保執行
質権、抵当権、根抵当、留置権、先取特権、譲渡担保、仮登記担保、所有権留保、代理受領、振込指定
6 その他回収方法
商品引き揚げ、債権譲渡、相殺、手形、小切手
7 元請会社が倒産した場合
(1) 元請会社からの回収
破産、再生、 届出債権につき平等分配 但し、担保
任意整理 交渉
取締役の責任追及
(2)注文者からの回収
注文者がまだ支払っていない場合
(3)上述各手段で併用できるものは併用する
第6 時効に注意
(1) 時効
民法改正(令和2年4月1日施行)により、業種別の短期消滅時効は廃止となりました。
令和2年4月1日以降に発生した債権の消滅時効期間は、改正民法の規定により「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間」となります(改正民法166条)
(2) 迅速に請求(催告)
時効の中断
準消費貸借を使うことも考えて。
第7 最後に
事例によって適した方法は変わりますし、どの方法がとれるのかの判断が難しい場合も多いです。早めの相談が良い結果を生む場合が多いのは確かですので、気になったら、すぐに実際に弁護士に相談することをお勧めします。
投稿者 | 記事URL
子どもが自分で弁護士をつけられる!~子どもに対する法律援助について~(弁護士 畑 福生)
2021年1月25日 月曜日
親から辛い目にあわされてやっとの思いで家から逃げてきた。代わりに親と話してほしいけど、お金がないから弁護士なんて頼めないよね?
そんなことはありません。
「子どもに対する法律援助」という制度があります。
(※以下結論をいち早く知りたい方は「☆」の付いた太字の部分だけでも読んでみてください。)
1 「子どもに対する法律援助」とは
日本弁護士連合会という日本の全ての弁護士が登録している組織が、人権救済のために、弁護士から徴収した会費を主な財源とし、法テラスによる民事法律扶助制度や国選弁護制度等でカバーされていない方を対象として弁護士費用等を援助する法律援助事業を行っています。日弁連は、総合法律支援法に基づき、この事業を2007年10月1日から法テラスに委託して実施しています(日弁連委託援助業務)。
この事業の中に「子どもに対する法律援助」があります。
なお、日弁連は「子どもに対する法律援助」以外にも様々な法律援助事業を委託しています。こちらをご参照ください。
https://www.nichibenren.or.jp/activity/justice/houterasu/hourituenjyojigyou.html
☆ 要は、子どもが自分で弁護士をつけるための費用を出してもらえる制度があるということです。
2 「子どもに対する法律援助」でできること
援助の対象となる活動は以下のとおりです。
⑴ 行政手続代理等
・ 行政機関(特に児童相談所)、児童養護施設等の施設との交渉の代理
・ シェルターその他の施設等への入所へ向けた支援、入所中の支援、施設等から自立的生活への移行へ向けた支援
・ 虐待等を行う親との交渉に関する代理、親との関係調整活動
・ 児童虐待事件に関する刑事告訴手続の代理、刑事手続で証人として出廷する子どもの援助
・ 学校等において体罰、いじめ等の人権侵害を受けているが、保護者が解決しようとしない事件についての交渉代理
・ 少年法第6条の2第1項の調査に関する付添人活動
⑵ 訴訟代理等(⑶以外)
・虐待する養親との離縁訴訟、扶養を求める調停や審判手続等の法的手続の代理(親権者の協力が得られないため、民事法律扶助の申込みができない場合)及びこれに関わる法的手続の代理
⑶ 子どもの手続代理人
・ 家事調停手続、家事審判手続、ハーグ条約実施法に基づく子の返還申立事件の手続及び即時抗告の手続(ただし、除外事項あり)における手続代理又は当事者参加申出、利害関係参加申出、利害関係参加許可申立て及びハーグ条約実施法に基づく子の返還申立事件の手続への参加申出の手続代理並びにそれらの支援
⑷ 以上に関わる法律相談
☆ これらの中でもとりわけ、親との交渉や裁判手続のために弁護士をつけられるのがこの制度の良い所です。
3 「子どもに対する法律援助」を利用するために
利用するためには以下の3つの要件を満たす必要があります。
① 虐待や体罰、いじめ等により人権救済を必要としている子ども(20歳未満)等の対象者に該当すること(※貧困、遺棄、無関心、敵対その他の理由により、その子どもの親等各申立権のある親族から協力を得られない場合に限られます)。
② 資力要件(例えば手取り月収が単身者で20万1,000円以下であることなど)。
③ 事件について弁護士に依頼する必要性・相当性があること。
☆ 以上の要件はありますが、親などから辛い目にあわされている子はこの要件を満たす場合が多いです。利用に当たっては弁護士を通じての申込みが必要となりますので、お気軽にご相談ください。
原則として「子どもに対する法律援助」利用にかかる相談は、法テラスを利用して無料にて承ることができます。
4 よくある質問
Q1:本当に無料なの?
A1:原則として無料で、援助を受けた報酬、費用について、申込者の負担はありません(法テラスから担当弁護士に支払われます)。ただし、現実に利益が得られた場合などについて例外もあります。(詳細は次の法テラスウェブサイト参照。https://www.houterasu.or.jp/higaishashien/seido/kodomo_houritsuenjo/index.html)
Q2:弁護士をつけるのに親の同意はいらないの?
A2:子どもに対する法律援助の利用に当たって、親などの法定代理人の同意を得る必要はありません。
弁護士に事件を依頼する委任契約などの「契約」は、通常、民法5条1項本文及び同2項に基づいて、親権者の同意がない限り、取り消すことができます。しかし、親などの法定代理人を相手に交渉などを行う場合に、親などの法定代理人が、弁護士と子どもとの間の委任契約を取り消せるとしてしまうと、子どもは弁護士をつけられず、子どもに対する法律援助の意義がなくなってしまいます。そこで、子どもに対する法律援助では、子どもの金銭的な負担をなくすことによって、民法5条但し書き(「ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。」)に基づき、委任契約の取消しを防いでいます。子どもは負担なく単に法律サービスを受けるだけという扱いです。
5 最後に
☆ 川崎合同法律事務所では、子どもが 「自分のことは自分で決める」ことを応援します。困っている場合はすぐにご相談ください。
辛い立場に置かれた子どもを支援されている方も、子どもに対する法律援助の利用含めて、その子のために何ができるか一緒に考えて行けたらと思いますので、お気軽にご相談ください。
原則として「子どもに対する法律援助」利用にかかる相談は、法テラスを利用して無料にて承ることができます。
投稿者 | 記事URL
知る権利と情報公開請求(弁護士 小林展大)
2021年1月25日 月曜日
第1 知る権利
憲法21条1項は,「集会,結社及び言論,出版その他一切の表現の自由は,これを保障する。」と規定していて,これは表現の自由を保障したものです。表現の自由は,個人が言論活動によって自己の人格を形成・発展させる自己実現の価値,言論活動によって国民が政治的意思決定過程に関与するという自己統治の価値があるので,極めて重要な基本的人権とされています。
表現の自由は,思想・情報等の伝達の自由ですが,一方では思想・情報等の受け手を前提としているから,高度に情報化され,大多数の国民が情報の受け手に固定化されている現代社会においては,情報の受け手側から表現の自由を構成すべく,知る権利が保障されているのです。
第2 情報公開請求
1 知る権利を具体化するものとして,情報公開制度があります。
国の行政機関に対する請求は,行政機関情報公開法,独立行政法人に対する請求は独立行政法人情報公開法,地方自治体に対する請求は地方自治体の情報公開条例に基づいて請求することになります。
なお,裁判所については,行政機関情報公開法の適用はありませんが,司法行政文書開示申出という制度があります。
2 情報公開請求をするにあたり,請求書の書式をホームページ等に掲載している地方自治体,行政機関もありますので,案内にしたがって,請求書の必要事項を記入することとなります。
請求する情報,文書の名称等の欄には,どのような文書の開示を受けたいかを書くことになります(場合によって,問合せがあったり,補正を求められたりすることもあります。)。
請求書に必要事項を記入したら,手数料分の印紙を貼付して郵送すれば手続ができます(FAX送信を受け付けているところもあります。)。
3 請求後は,一定の期間内に請求者に開示・部分開示・不開示の決定がなされます(決定が延長されることもあります。)。
開示の実施の方法は,閲覧,写しの交付等の方法があります(コピー代等の費用負担を求められます。)。
4 開示・部分開示・不開示決定につき,不服がある場合には,一定期間内に不服申立をすることができます。
⑴ 審査請求という不服申立をする場合には,審査請求書という書面を提出して,不開示処分の取消しを求めたり,対象文書の追加特定を求めたりします。
行政機関,地方自治体からは,弁明書,理由説明書等の書面が提出されることがあり,それに対して,請求者は反論書,意見書等の書面を提出することがあります。
そして,情報公開・個人情報保護審査会,行政不服審査会に諮問され,その後,情報公開・個人情報保護審査会,行政不服審査会が答申を取りまとめて提出すると,これを受けて諮問庁が裁決することとなります。
⑵ 不服申立として訴訟をする場合には,不開示処分等の取消しの訴え等を提起することとなります。そして,裁判所で審理がなされます。
第3 マイナンバー違憲訴訟と情報公開請求
マイナンバー違憲訴訟が進行するにつれて,次々とマイナンバーが漏え いする事故が発生しています。
マイナンバーを取扱う業務については,委託元の許諾を得なければ再委託してはならないこととなっています(番号法10条1項)。しかし,委託元の許諾を得ずにマイナンバーを取扱う業務を再委託して,マイナンバーが大量漏えいするという事故が続発したことから,マイナンバー違憲訴訟弁護団は,知る権利を行使して,その事故が発生した地方自治体,行政機関に対し,情報公開請求及び審査請求をして,口頭意見陳述も行って攻勢をかけています。
マイナンバー違憲訴訟は,このようにして情報公開請求を駆使して,知る権利運動を展開しているのです。
以 上
投稿者 | 記事URL
相続、遺言の法律 大改正のQ&A(弁護士 西村隆雄)
2021年1月22日 金曜日
民法の内、相続、遺言法については、1980年以来大きな見直しはされてきませんでした。
しかしこの間、社会の高齢化が進展し、相続開始時における配偶者の年齢も高齢化しているため、その保護の必要性が高まっていたことなどから、大改正が行われ、一昨年7月から施行されるところとなっています。
そこでこの内、よくご質問のある点について、ご説明したいと思います。
Q 長期間婚姻している夫婦間の贈与について、配偶者に有利な改正が行われたのですか。
A これまでは、夫婦間で贈与をしたとしても、原則として遺産の先渡しを受けたものとして扱われるため、贈与がなかった場合と同じ額の遺産しか受け取れませんでした。
しかし、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与が行われた場合、配偶者の長年の貢献に報い、老後の保障の趣旨で贈与が行われていることを重視して、この贈与分は除外して、残りの遺産について遺産分割をすることとして、配偶者を有利に扱うこととなりました。
Q 配偶者の居住権を保護する改正がなされたというのは、どういう点でしょうか。
A 配偶者が、相続開始時に亡くなった方名義の建物に居住していた場合は、従来もその方との間に使用貸借契約が成立していたと推定されて、一定の保護がはかられてはいました。
しかし第三者に居住建物が遺贈されてしまったり、亡くなった方が居住を認めないと意思表示をしていた場合などは、居住が保護されませんでした。
今回の改正では、こうした場合でも、常に最低6カ月は配偶者の居住権が保障されることになりました。
Q 配偶者の居住権を長期的に保護するための改正も行われたと聞きましたが。
A これまでは配偶者が引き続きその建物に居住したい場合は、その建物を相続により取得するしか道はありませんでした。したがって住む場所は確保できても、他の預金などの財産は受け取れなくなってしまう事態となっていました。
今回の改正で、遺産分割の選択肢として、あるいは遺言において、配偶者に配偶者居住権を取得させることができるようになりました。
すなわちたとえば、配偶者と子供が相続する場合、配偶者は配偶者居住権と預金の一部を、子供は配偶者居住権という負担のついた建物所有権と預金の一部をそれぞれ取得するということが可能になったのです。居住の期間は終身とすることも一定期間とすることも可能で、その負担に見合った財産評価がされて、分割が行われることになります。
Q 相続人以外の者(例えば亡き長男の妻)の貢献を考慮するための制度が導入されたと聞きましたが、どういうことでしょうか。
A 例えば、亡き長男の妻が義父の介護に献身的に尽くした場合であっても、これまでは義父の相続人(長女、次男)は、介護を全く行っていなくても相続財産を取得することができたのに対して、亡き長男の妻は相続財産の分配にあずかれないという不合理が指摘されていました。
そこで今回、相続開始後、長男の妻は、相続人(長女、次男)に対して、介護の貢献度に応じて金銭請求することができるようになりました。
Q 死亡後は預金が凍結されて、生活費や葬儀費用の支払いにも充てられないと聞いていたのですが、いかがですか。
A 従来は争いがある限り、遺産分割が終了するまで、一部の相続人が単独で預金をおろすことはできませんでした。
それが、仮払いの必要性ありと認められる場合には、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようになるとともに、預金のうち一定額(預金額×1/3×払い戻しを行う相続人の法定相続分)については、裁判所の判断を経ずして、金融機関の窓口で支払いが受けられるようになりました。
Q 遺言書の保管について、新たな制度ができたと聞いたのですが。
A これまで遺言する方が自分で書いた遺言(自筆証書遺言)は、自宅(仏壇、金庫等)に保管されることが多く、遺言諸が紛失したり、相続人によって廃棄、隠匿、改ざんされるなど、問題が生ずることがありました。
そこで今回、法務局に保管の申請ができることになり、死亡後は相続人が写しの交付、閲覧請求ができる保管制度が創設されました。
Q 自分で書く遺言(自筆証書遺言)の方式が緩和されたというのはどういうことですか。
A これまでは遺言書の全文をすべて自分で書かなければなりませんでした。すなわち財産目録の、不動産や預金の内容まで、すべて手書きが要求されていたのです。
しかしこれは今の時代にそぐわないとして、パソコンで財産目録を作成したり、預金通帳のコピーを添付することも可能となりました。但しパソコン打ち出しやコピーについては、その1枚1枚に署名捺印が必要ですので気を付けましょう。
投稿者 | 記事URL
最近のブログ記事
- いよいよ山場を迎える 台風19号多摩川水害訴訟 (弁護士 西村隆雄)
- 2/25(水)所内行事のため 16時30分に閉所します
- かわさき市民オンブズマンによる川崎市議会議員海外視察住民訴訟(弁護士 小林展大)
- 2026年劈頭にあたり 新年のご挨拶を申し上げます
- 相続あるある(弁護士 渡辺登代美)
- 酒酔い、赤信号無視… 起死回生の逆転劇(弁護士 西村隆雄)
- 離婚した後、旧姓に戻る? それとも夫の姓をそのまま使う?子どもが大きくなった後、旧姓には戻れるの?という疑問にお答えします(弁護士 川口彩子)
- 畑福生弁護士が小田原市立下曽我小学校ホームページに掲載されました
- 【10/31開催】79期司法修習予定者向け学習会・事務所説明会に参加しませんか
- 【9/12開催】79期司法修習予定者向け学習会・事務所説明会に参加しませんか
月別アーカイブ
- 2026年2月 (3)
- 2026年1月 (1)
- 2025年11月 (1)
- 2025年10月 (2)
- 2025年9月 (4)
- 2025年8月 (1)
- 2025年7月 (1)
- 2025年5月 (2)
- 2025年4月 (6)
- 2025年2月 (2)
- 2025年1月 (1)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年9月 (3)
- 2024年4月 (1)
- 2024年1月 (1)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (1)
- 2023年9月 (1)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (3)
- 2023年5月 (2)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (6)
- 2023年2月 (2)
- 2023年1月 (1)
- 2022年12月 (5)
- 2022年11月 (3)
- 2022年10月 (1)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (1)
- 2022年6月 (2)
- 2022年5月 (1)
- 2022年4月 (1)
- 2022年3月 (1)
- 2022年1月 (2)
- 2021年12月 (3)
- 2021年9月 (3)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (5)
- 2021年6月 (2)
- 2021年5月 (2)
- 2021年4月 (6)
- 2021年3月 (13)
- 2021年2月 (2)
- 2021年1月 (3)
- 2020年12月 (2)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (2)
- 2020年8月 (1)
- 2020年7月 (3)
- 2020年6月 (2)
- 2020年4月 (6)
- 2020年3月 (2)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (8)
- 2019年12月 (2)
- 2019年11月 (4)
- 2019年10月 (2)
- 2019年9月 (3)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (3)
- 2019年6月 (3)
- 2019年5月 (4)
- 2019年4月 (9)
- 2019年3月 (1)
- 2019年2月 (1)
- 2019年1月 (2)
- 2018年12月 (1)
- 2018年11月 (4)
- 2018年10月 (1)
- 2018年9月 (3)
- 2018年8月 (8)
- 2018年7月 (10)
- 2018年6月 (6)
- 2018年5月 (5)
- 2018年4月 (1)
- 2018年3月 (3)
- 2018年2月 (1)
- 2018年1月 (3)
- 2017年12月 (3)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (7)
- 2017年9月 (5)
- 2017年8月 (2)
- 2017年6月 (3)
- 2017年5月 (2)
- 2017年4月 (3)
- 2017年3月 (3)
- 2017年2月 (5)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (5)
- 2016年10月 (5)
- 2016年9月 (1)
- 2016年8月 (76)